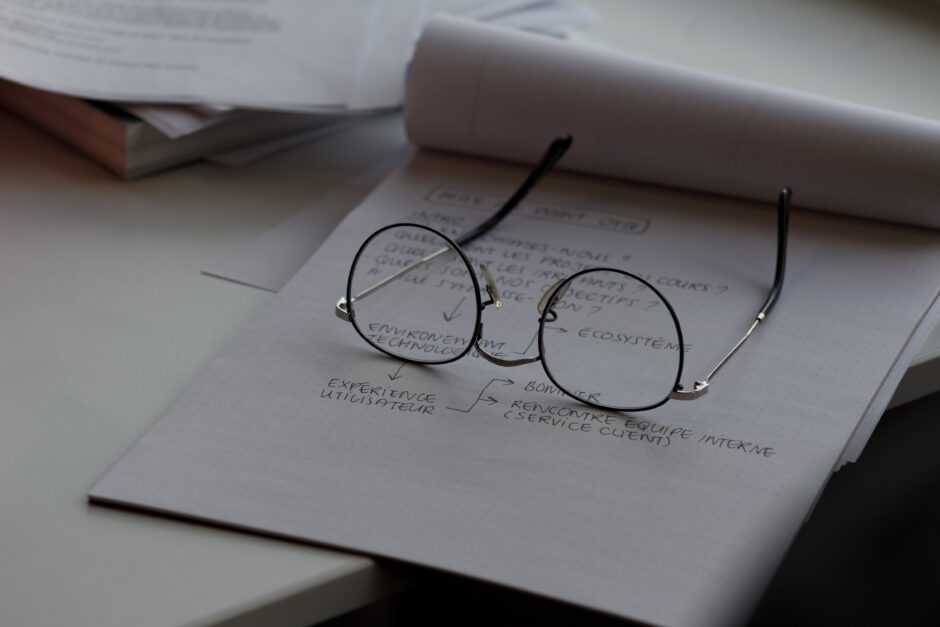療法士「研究とか、論文とか、やってみたいな。でも、お金がかかるなら無理だな。職場で負担してくれないし、自腹なんてイヤだし…」
このようなテーマで記事を書いてみようと思います。
- 論文はお金をかけなくても書ける
- 英語で論文を書く時には費用が必要
- 実績を積んで助成金をGETするのもアリ!
研究をしてみようと思ったときに、ネックになるのは費用の問題では?
実は、僕も研究を始める前には、お金がかけられないので執筆は難しいと思っていました。
でも、実際には研究の内容や投稿する雑誌によっては、ほとんど費用をかけずに論文を掲載させることができます。
この記事では、僕の経験を紹介しつつ、この問題についての意見を書いてみます。
お金を言い訳にしない!研究費がなくても論文は書ける



論文はお金をかけずに書けます。
体験談:5,000円以下で論文を書いた
僕の最初の論文は5,000円もかけずに仕上げました。研究で主に費用がかかるのが統計解析のためのソフト導入や、英語抄録の校正費でしょうか。
- 統計解析:フリーソフト「R」
- 英文校正:自力+先輩に頼る
僕の場合が上記のようにしました。ここまでだとお金はかかっていません。僕がお金を書けたのは「統計の学習」と「英文作成ツール」です。
まず、以下の本を購入しました。Rの導入から簡単な統計の実行まで、かなり分かりやすく解説されています。
この本を見ながら、パソコンに「R」をインストールして、実際にデータをいじりながら操作方法を学んだ感じです。
そして、慣れてくれば目的の解析に必要なコードはネット上に落ちているので、ググれば大体の検定方法は実行できます。


日本語の論文を書くときにも、タイトルと抄録だけは英文の提出が求められます。これが案外ハードルを高くするんですよね。
ただ、以下のツールを使えば、わりと簡単にできちゃいます。
この3つはマストかと。TrinkaとGrammarlyは有料プランもありますが、抄録を作るくらいなら無料プランで問題ないと思います。
あとは、英語論文の書き方みたいな本を1冊読んでおけば、それなりの抄録が完成するのでは?オススメは以下。
できれば、英語が得意な人に完成後に読んでもらえると安心ですね。
ネイティブが教える 日本人研究者のための論文の書き方・アクセプト術


多少の経費なら、職場が出してもらおう
その他に必要な費用としては、紙代・印刷代くらいでしょうか。
同意書を作成したり、作成過程で原稿を印刷したりすることもありますしね。このあたりは、職場にお願いして出してもらえると良いと思います。
ほとんどの場合、研究を開始する前に職場の「倫理委員会」に研究計画を提出すると思います。僕の場合は、研究計画と一緒に経費をまとめて上層部にお願いしました。
投稿する雑誌によっては、掲載料がとられる場合があります。しかも、ソコソコの金額とられたりするんですよね。
オススメ:掲載料がかかる雑誌には投稿しない
『この研究は、この雑誌に出さなければダメ!』といった強い気持ちがある場合は別ですが、そうでなければ掲載料がない雑誌を選びましょう。
- 言語聴覚研究
- 日本摂食嚥下リハビリテーション学会誌
僕は日本の雑誌なら、上記に投稿していました。
別刷りといって、掲載された自分の論文だけを小冊子にして販売してくれます。
ただ、これはいらないと思います。記念にはなるかもですが、大抵は50部単位とかでの購入です。
しかも、最近ではPDFでダウンロードできることがほとんど。別刷りをつかう機会なんてほとんどないので、PDFで十分だと思います。
ちなみに、僕はPDFのみで困ったことはありません。
実績をつくれば、助成のチャンスも出てくる
今回の研究に関しては、研究で機器などの高額なものを使用しない場合を想定して解説しています。
例えば、以下のような研究ですね。
- 症例報告
- 過去の検査データを利用した横断研究
- 今の職場にあるものを利用した研究
でも、内容によっては新しく機器を購入して研究したい場合もありますよね。
例えば、「今の職場には舌圧測定器がないので、研究のために購入したい!」など。でも、こういう理由で買ってもらえる職場ってめずらしいですよね。
僕の職場でも買ってもらえないので、自分で資金を調達することにしました。
有名なのは『科研費』ですが、ふつうの臨床家では応募すらできません。
などなど。研究助成を応募しているところは、案外たくさんあります。
自分がやりたい研究内容に近い領域の研究助成に申し込んでみるのも良いと思います。
僕が助成してもらったときは、年間30万円の研究費がいただけました。助成先への報告書の作成など手間も増えますが、やりたい研究ができてうれしかったです。
全く研究歴のない人に、ドカンと30万円以上を助成するのは基金側としても躊躇するのは当然ですよね。
なので、上記のような方法で「お金をかけずに」実績を積みつつ、研究助成のチャンスを狙うのが良いと思います。
でも…英語論文に挑戦する時には、お金がかかる



ただし、英語論文を書くときには、校正費がどうしてもかかってしまいます。
残念:英文校正費はどうしてもかかってしまう
海外雑誌に論文を投稿する時には、「ネイティブチェック」といって、その言語を母国語とする人に校正してもらう必要があります。
和文の英文抄録でもネイティブチェックが必要な場合がありますが、抄録だけなら数千円でできます。そして、そこまで高品質な校正会社を使わなくても「アイディービジネス」とかでも十分かと。
他には、「フルーツフルイングリッシュ
でも、英語論文のように全体をチェックしてらうとなると話は別です。論文のボリュームにもよりますが、僕の場合は2万円程度かかりました。
ちなみに、僕が利用してきた英文校正業者は以下。イマイチだったところは抜いてあります。
- エディテージ:業界最大手!少し料金は高めですが、信頼の校正です。
- エナゴ:親切な対応。サポートが充実しているのが特徴。
- フルーツフルイングリッシュ
目的別に、選ぶと良いと思います。
ただ、中にはネイティブの知人にお願いして校正してもらっている人もいるそうです。
医学・論文に精通しているネイティブの人なんて、なかなか出会えないような気もしますが…。
英文校正費を稼ぐ方法
上記のように、英語論文に挑戦しようと思ったときに、最初に立ちはだかるのが「校正費、どうしよう問題」かと思います。
最近は「実績作りに必要なお金は、実績で稼ごう」って思うようになりました。生活費とは財布を分けておくイメージです。
僕の場合は、日本語の論文を3つくらい掲載された頃から、セミナー講師や書籍執筆の話を頂けるようになりました。
セミナー講師なら1回1万円くらい、書籍の印税は年間2万円くらい入ってくるので、年間に1回分の英語論文の校正費は自分でどうにかできる感じです。
先日に知ったのですが、このあたりの研究費を職場が出してくれる場所もあるようです。自腹をきらずに論文を書いていきたい人は、こういう職場に身を置くのも良いですね。
臨床にいながら論文をだす価値
というわけで、論文執筆にまつわるお金の話について、僕の経験を紹介しました。
ここまでをまとめます。
- 日本語の論文なら数千円で書ける
- 統計ソフトは無料の「R」を使おう
- 英文作成に便利なツールを紹介
- 英語論文は校正費がかかってしまう
- 実績を積んだら助成金を狙うのもアリ
こんな感じでしょうか。
研究機関や大学病院のような職場であれば、研究も仕事の一つとして認めてもらえて費用を出してもらえるのかもしれません。
でも、研究費を職場が出してくれるところって、そこまで多くないですよね。出してもらえないなら、工夫するしかありません。
僕は論文を書いたことで、以下の3つが広がりました。
- キャリア
- 人脈
- スキル
論文を書く前は、「論文は特別な人が書くもの、自分には書けない」と思っていました。
でも、やろうと思って取り組んでいれば、助けてくれる人は案外いるものです。そして、やっているうちにスキルも上がってきます。


自分の臨床経験が、誰かの役に立つ
臨床にいながら論文を出す価値はここにあると思っています。実際に臨床をバリバリとやっているからこそ、気づける視点は多いはず。
ここだけの話、臨床にいながら論文を書いている人なんて一握りです。論文の実績は希少価値となって、今後のキャリアにつながりますよ。
臨床家が研究をして、成果を文章(論文)にして残す。こういったことも、この分野の発展のために大切なことだと思っています。
というわけで、論文に挑戦してみましょう。