
悩める言語聴覚士「論文って大変そう。論文を書くことのメリットって何だろう?どういうマインドで取り組めば良いのかな?」
こういったテーマで記事を書いてみようと思います。
- 言語聴覚士が論文を書くメリットは?
- 学歴がないと論文が書けないという誤解
- 論文執筆で上がる臨床の質



この記事を書いている僕は、日本語論文10本、英語論文2本を書き上げました。
正直、論文執筆はめちゃくちゃ大変。でも、論文が掲載されると世界が広がり、得られるものはたくさんありました。
論文を完成させたことで得られたメリットは何か?
今回の記事では、実際の経験を紹介しながら、論文を書くことの意義を解説します。
要するに、「みんな、論文書こうよ」って話です。
目次
論文を書いて広がる世界:言語聴覚士のキャリア・人脈・スキル



言語聴覚士が論文を書くことで広がる世界は、以下の3つだと思います。
- キャリア
- 人脈
- スキル
順番に説明していきます。
論文で広がる【キャリア】
論文の掲載はキャリアアップにつながります。
なぜなら、「論文=業績」となるから。
自分の頑張りを唯一、客観的に証明できる業績だと思います。
臨床や職場での雑務をどれだけ頑張ったとしても、それを客観的に証明する手段はないですからね。
筆頭著者として掲載された論文=名刺代わり
という感じです。
論文で広がる【人脈】
意外かもしれませんが、論文を書くと人脈も広がります。
論文は、最初から自分一人で書き上げようとするのはダメ。
論文の執筆経験のある人から教えてもらいながら取り組むことをオススメします。
なぜなら、論文や研究には型があるから。
基本をおさえるためにも、指南してくれる人を見つけるべきです。
論文の指導役を見つける取り組みを通して、良質な人脈が広がっていきます。
論文で広がる【スキル】
論文を書くためには、少なくとも以下のようなスキルが必要です。
- 情報収集
- 研究の計画
- ライティング
その他にも、「相談スキル」「論理的思考」など。
1つの論文を仕上げる過程の中で、あらゆるスキルを学ぶことができます。
これらのスキルは、学んでから論文に取り組むのでなく、『学びながら論文に取り組む』のが最適です。
例えるなら、筋トレをしまくっても野球が上手くなるわけではないように、論文も実践が大切。
とにかく「やってみる」が良いと思います。
》【体験談:例文あり】英語論文が掲載されるまでの流れと査読の期間と対応
言語聴覚士の学歴は関係ない【論文を書こう】



「大学院に行ってないし、学歴のない僕には論文は無理かな…?」
僕も最初はこう思っていました。でも、それは誤解。論文を書くのに学歴は関係ありませんでした。
「論文は大学院に行った人が書くもの」
これは誤解です。たしかに、大学院では論文の書き方などを丁寧に教えてもらえます。
でも、論文の書き方は大学院に行かなくては学べないものではありません。実際に僕も大学院に行かずに独学で論文を10編以上書いています。
あと、よくある誤解は「研究費がないと研究できない」というもの。日本語の論文なら、ほとんどお金をかけずに書くことができます。詳しくは以下の記事で解説していますので、お読みください。
論文執筆を応援してくれるような周囲の環境って大事ですよね。
正直、論文を完成させるのはかなり大変。
心が折れそうになることも多いです。
加えて、論文を書こうっていう言語聴覚士は少ないので、職場で浮いてしまうことも…。
案外、周囲の環境って大切です。
本気で論文に取り組みたいなら環境を整える必要がある場合もありますよね。
論文に取り組みやすい職場への転職を目指すなら、転職エージェントを利用すると職場の雰囲気なども教えてもらえます。
》【失敗しない】リハビリ業界の転職エージェントの選び方:ランキング&最大活用のコツ
僕の場合、大学院にはいかずにクリニックで働きながら「日本語の論文10本+英語の論文2本」を筆頭著者で掲載してもらっています。
なので、ある程度信頼性はあるのではないかと。
論文を書くことを目標に、まず独学すべきは以下の3点。
- 研究計画
- 統計学
- 論文ライティング
これらを勉強するなら、以下の書籍はオススメです。
独学しながら、まずは研究計画を立てましょう。
「どんな対象者に」「どんな介入をして」「効果をどのように比較するのか」
データ収集前に、しっかりと計画を詰めておくことが重要です。
研究計画を立てるためにも、日頃から論文を読んでおくこともオススメします。
》【英語が苦手な療法士】論文の読み方のコツ:ツールを活用セヨ【リハビリ業界】
論文を書くことは、言語聴覚士の臨床の幅を広げる



実は、論文執筆に取り組むことは、言語聴覚士としての臨床につながります。これは間違いありません。
論文で必要な視点が、臨床の客観性につながるからです。
先行文献の調査で知識を吸収
臨床で疑問を感じた時に、教科書で調べても解消しないことってありませんか?
恥ずかしながら、僕は論文執筆を経験するまでは、教科書で調べても分からない事象は「しょうがない」として諦めていました。
しかし、論文では臨床の疑問を突き詰めて理解しようとします。
先行文献にヒントがあるのではないか?過去に報告された事例に共通点はないか?など。
そうすることで、案外ヒントが得られます。能動的に調べた知識は吸収しやすいですよね。
客観的な指導効果という視点
論文執筆を経験すると、指導効果についても出来るだけ客観的に把握しようとう姿勢が身につきます。
なぜなら、論文では対象者の言動を数値化して比較することが多いからです。
言語聴覚士が行う指導の効果は数値化しにくい特徴があるものの、可能な限り客観的な効果測定をすべきなのは間違いない。
客観的な指導効果という視点を持ちながら臨床できると、臨床スキルは高まるはずです。
論文を書いた言語聴覚士の体験談
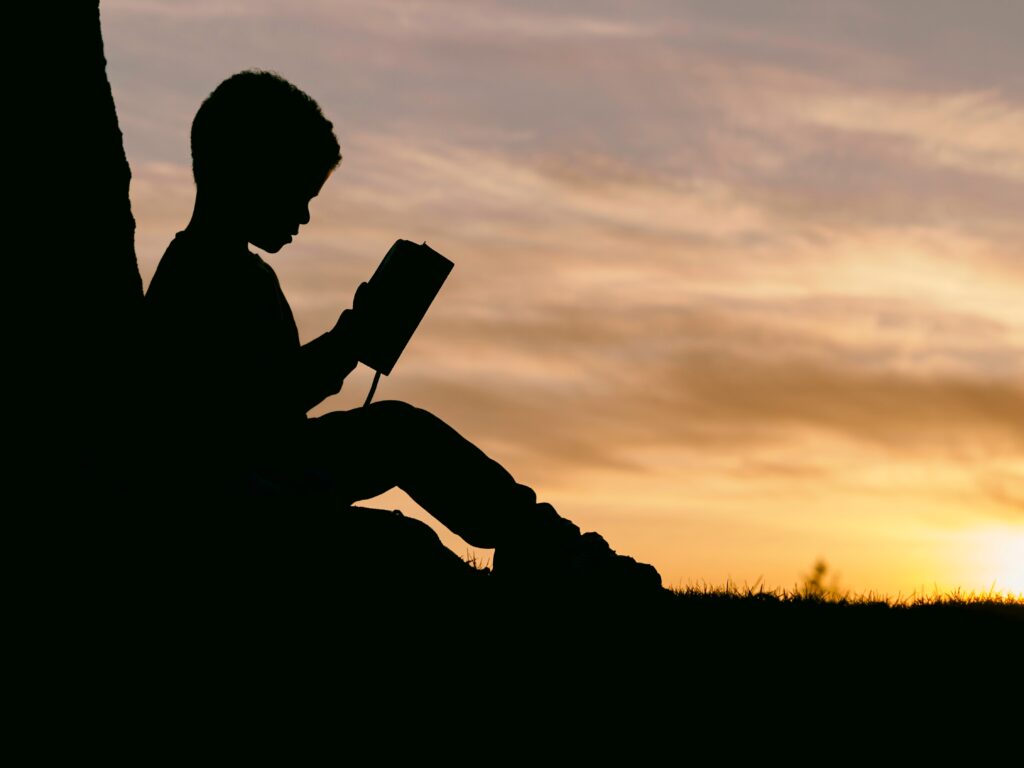
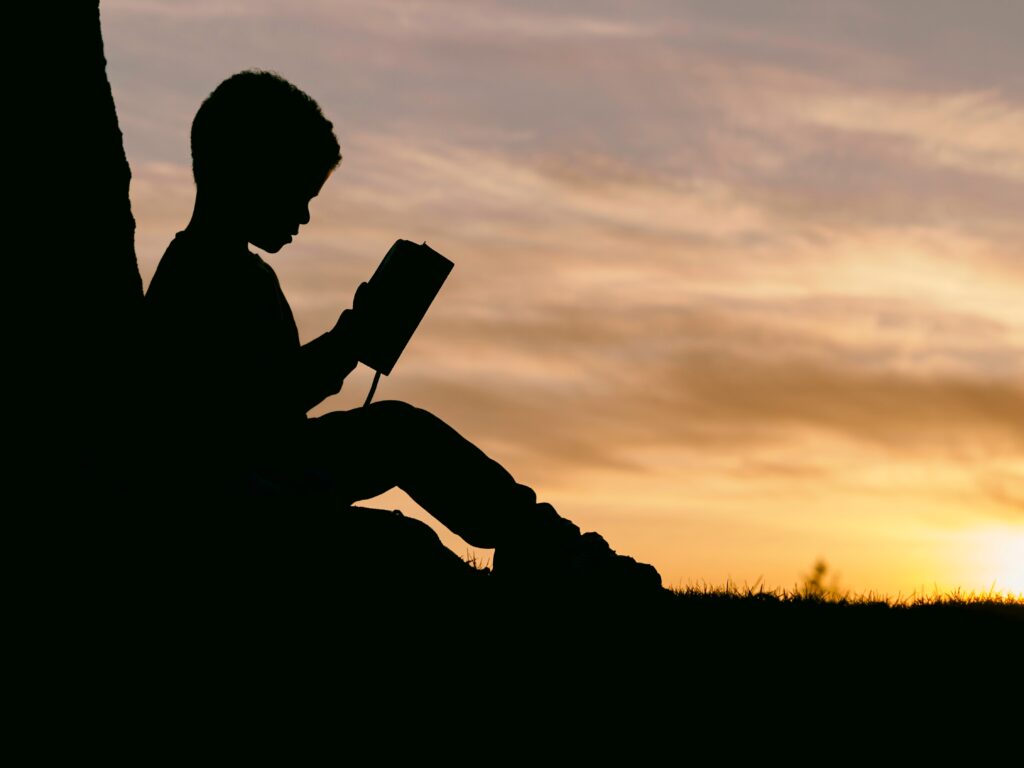
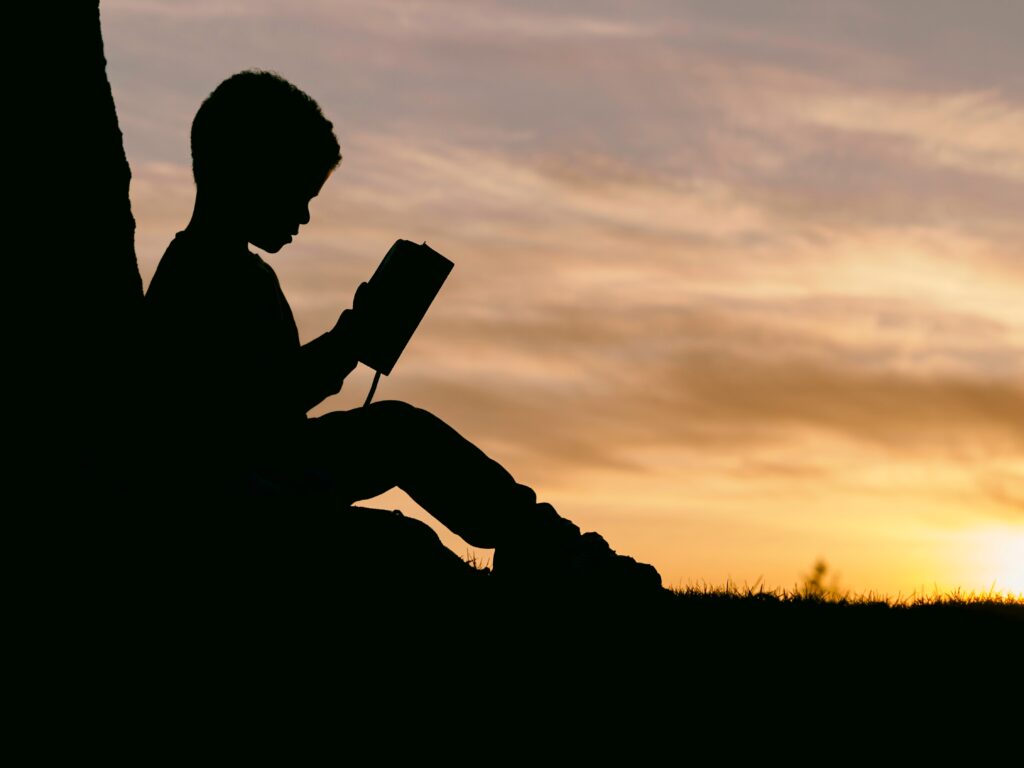
僕がこれまで論文を書いてきたことで広がった世界、得られたメリットを紹介しますね。
- キャリア:書籍執筆の機会
- 人脈:他施設のセラピスト
- スキル:論理的思考
論文を世に出せたおかげで、これまで面識のなかった人からも僕のことを認識してもらえるようになりました。
具体的には、教科書を監修しているような大御所の先生から「今度、教科書を改訂するんだけど、〇〇の部分を担当してくれない?」といったお声がけを頂いたり。
人脈という点では、論文が掲載後に、県士会から講演依頼があったり、内容に関する質問メールをもらったりと、自然と他施設のセラピストとのやりとりが増えました。
臨床の疑問を解消するために、根拠となるようなデータを探して論文を読む習慣がついたのも良かったです。
こんな感じで、論文への挑戦は大変ではありましたが、成し遂げればメリットしかありません。今では本当にやって良かったと思っています。
まとめ:言語聴覚士が論文を書くメリットは多い



この記事では「言語聴覚士が論文を書くと、どんな良いことがあるのか?」といったテーマで解説しました。
ここまでをまとめます。
- 論文を書くとキャリア・人脈・スキルが広がる
- 学歴などは関係ない。臨床しながら論文は書ける
- 論文執筆を通して臨床の質は上がる
こんな感じです。
論文を完成させるのは正直かなり大変です。
でも、成し遂げて得られるメリットは多数。ぜひ、一度は挑戦してみてほしいと思います。
学会発表は経験があっても、論文執筆まで取り組んだことのある言語聴覚士は一握り。
まずは、学会発表した内容を論文にできないか検討してみることをオススメします。
とりあえずやってみる。
僕はこれが大切だと思います。
行動にうつしていれば、不思議と助けてくれる人が出てくるものです。
実際に僕は、見切り発車が多いのですが、行動していると何故だか手を差し伸べてくれる人が現れます。感謝。
行動にうつさなければ、なにも変わりません。
ぜひ、論文を書きましょう。
それでは、今回はここまで。
何か参考になることがあれば嬉しいです。



