
フリーランスの言語聴覚士になりたい!
そのためには何をすべきなんだろう?
こんな疑問におこたえします。
- 言語聴覚士は「言語指導」「構音指導」で開業できる
- フリーランスを目指すなら小児分野を経験しよう
- 開業前に人脈・パイプを作っておくことが大切



この記事を書いている僕は、小児分野の言語聴覚士として働いています。現在はフリーランスではありませんが、過去に開業を考えたこともありました。しかし、僕は小児の嚥下領域に取り組みたい気持ちが今は強いので、クリニック勤務を続けています。このあたりの話も以下に紹介しますね。
今回は、フリーランスの言語聴覚士として働くことに興味のあるあなたに、
- 言語聴覚士がフリーランスで活躍できる領域は?
- なぜ、小児分野での開業がオススメなのか?
- フリーランスになるためにすべき行動は?
こんなことを分かりやすく解説していきます。
この記事を読めば、フリーランスの言語聴覚士として働く場合に考えておいた方が良いことが分かります。
さらに、小児分野で開業するためにすべき行動が見えてくるはずです。
それでは、さっそくお読みください。



今すぐに開業を目指しているわけではない人も、将来の自分の選択肢を広げる意味で知っておいた方が良いです!
目次
フリーランス言語聴覚士として開業したい!その理由は?



フリーランス言語聴覚士として開業したい!
そう思う理由は何でしょうか?
- 自分の理想の理念のもとに働きたい
- 分野を開拓したい
- 自分のペースで働きたい
- 収入を上げたい
などなど。理由はいろいろとあると思います。
あなたの夢をかなえるために、フリーランスとして開業するために知っておくべきことを整理しましょう。
言語聴覚士がフリーランスで活躍できる領域



言語聴覚士が専門とする言語聴覚療法には、医師の指示が必要なものと、医師の指示が不要なものがあります。
言語聴覚士がフリーランスで活躍できるのは、医師の指示が不要な「言語指導」「構音指導」の分野です。
- 医師の指示が必要:「嚥下訓練」、「聴力検査」、「補聴器装用訓練」など
- 医師の指示は不要:「言語指導」、「構音指導」など
これは、言語聴覚士法 第四十二条に、
言語聴覚士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として、医師又は歯科医師の指示の下に、嚥下訓練、人工内耳の調整その他厚生労働省令で定める行為を行うことを業とすることができる。
と明記されています。
言語聴覚士でなくても「言語指導」で開業できる
時々、言語聴覚士には開業権があるという意味を誤解している人がいますが、「言語指導」「構音指導」は言語聴覚士でなくても開業することができます。
要するに、誰でも「言語指導をします!」と言って開業できちゃうわけですね。
「言語聴覚士」と名乗って言語指導をできるのは武器!
当然ですが、「言語聴覚士」という国家資格を盾に働けるのはSTだけです。
「言語聴覚士」と名乗ってフリーランス活動できるのは、強みになります。
言語指導や構音指導を提供するサービスは、言語聴覚士が行うもの以外にも世の中には存在します。
しかし、医学をベースに根拠のある知識や指導方法に精通する言語聴覚士は、他の類似サービスのライバルに比べると信頼を得やすいことでしょう。
言語聴覚士がフリーランスとしておこなう指導等は公的医療保険適用になりません。
そのため、全額自費の自由診療のあつかいになります。
利用料金も経営者がある程度自由に決めることができます。
開業には経営・マネージメントの知識も必要
フリーランスで開業となると、言語聴覚士としての専門知識や技術のみでなく、
人材管理や運営方法、マネージメントなどの勉強も必要になります。
ただし、すべて自分ひとりでやる必要はありません。
人材管理やマネージメントが得意な人と組んだり、外注して経営するのも一つの方法です。
言語聴覚士がフリーランスで働けない領域
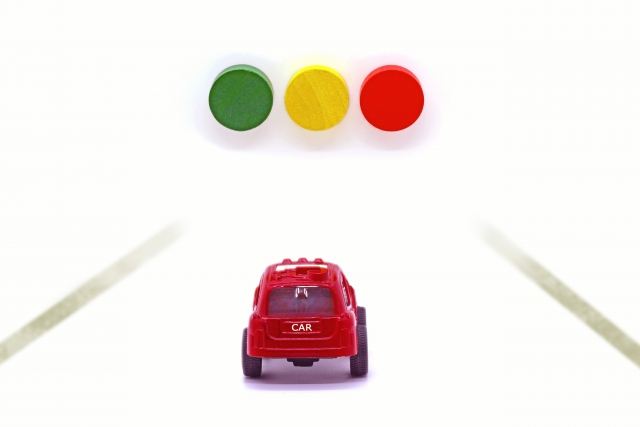
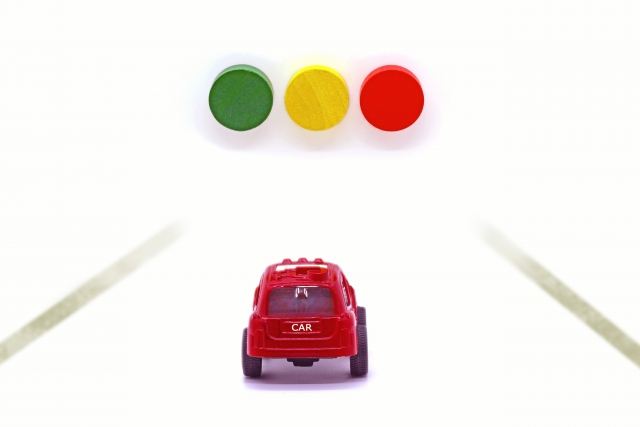
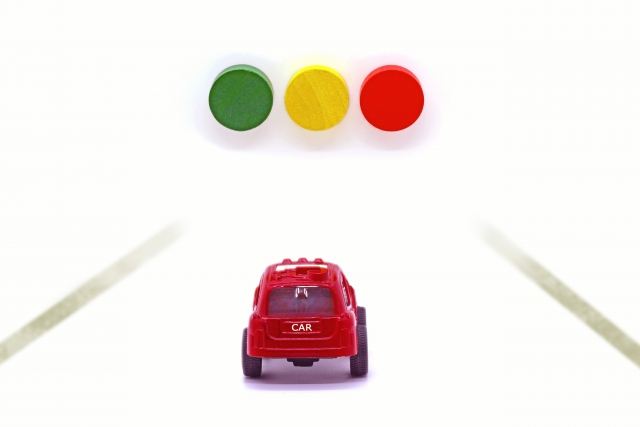
「嚥下訓練」「聴力検査」「補聴器装用訓練」など医学管理重要な分野の指導・訓練は医師の指示のもと行うことが法律で規定されています。
すなわち、これらは言語聴覚士が単独で実施することができません。
- 医師の指示が必要:「嚥下訓練」、「聴力検査」、「補聴器装用訓練」など
- 医師の指示は不要:「言語指導」、「構音指導」など
嚥下訓練などを医師の指示なしにやっちゃダメ!絶対!
時々、「言語聴覚士がオンラインで嚥下訓練を行います」といったサービスを目にしますが、
嚥下や聴力の分野でフリーランスを考えている人は、法律関係を慎重に検討した方がよいでしょう。
余談:僕がフリーランスを目指すのをやめた理由(体験談)
冒頭でもお伝えしたように、僕も開業を目指そうとしたことがありました。しかし、上記のような法律を調べていく中で、自分がやりたいことはフリーランスではないことに気づきました。



僕の場合は、重症心身障害児者の嚥下障害の臨床を今後も一生懸命に取り組みたいと思っています。
でも、フリーランスで開業となってしまうと、嚥下の臨床を行うことは難しくなってしまいます。
そのため、今は医療機関に所属して働いていこうと判断しました。
とはいえ、将来的にフリーランスの選択肢は作っておきたいですし、世の中の状況も変わるかもしれません。
もしかしたら、嚥下に関しても、訪問看護ステーションのように提携医療機関の医師の指示で言語聴覚士が担当できる日が来るかもしれないですね。
臨床以外で言語聴覚士がフリーランスとして活躍する道



言語聴覚士としてセミナー主催会社を立ち上げるといった方法もあります。
つまり、言語聴覚士を対象としたセミナーや研修会を開催し、言語聴覚士を育てることで間接的に対象者の役に立つということです。
自分自身で講師をおこなう場合もありますが、ある程度の認知度のある講師を招いてセミナーを行った方が良いかもしれません。
そのため、人脈がとても大切になります。
一般企業に近く、集客・マネージメントなど言語聴覚療法以外にも知るべきことがたくさんありますが、選択肢の1つとして知っておくとよいでしょう。
フリーランス言語聴覚士の開業の仕方



現在、フリーランス言語聴覚士は以下の場所・領域で活躍していることが多いです。
- 自身で相談室・指導室の開室
- 児童発達支援事業
- 放課後等デイサービスの事業所
- 訪問看護・訪問リハのステーション
- 言語聴覚士へのコンサルテーション
言語聴覚士はフリーランスでなくても、医療、教育、福祉、行政、介護など幅広い分野で活躍しています。
また、言語聴覚士になるために他職種からキャリアチェンジを経験していたり、ダブルライセンスを持っていたりと経歴に魅力をもつ人も多くいます。
こういった点でも、他の医療技術職よりもフリーランスとして力を発揮する人が多いのが納得できます。
フリーランスになるためには、ある程度経験してからがおすすめ
もちろん、新卒ですぐにフリーランスというのは難しい場合がほとんどです。
知識やスキルを蓄え、人脈などのネットワークを広げるために臨床経験を積むことがおすすめです。
将来にフリーランスで働く言語聴覚士を目指したい人は、そのために必要な経験をコツコツと着実に積み上げていきましょう!
言語聴覚士がフリーランスになるなら小児分野がおすすめ



現在、フリーランスで働いている言語聴覚士が一番多いのは、小児分野です。
「ことばの教室」や「発達相談・支援室」、最近では「オンライン療育」といった業態で開業している言語聴覚士もいます。
フリーランスで働くなら小児分野が狙い目!
上記の子どもたちを評価し、必要な言語・コミュニケーション指導および保護者への助言を行います。
フリーランスの言語聴覚士としてサービス提供が許されているのは「言語指導」「構音指導」です。
これらの子どもたちは言語や構音に支援の必要性が高い場合が多いですよね。
小児分野は需要が高い!
さらに、療育センターなどは半年以上の待機、児童発達支援では定員いっぱいで受付停止となっている地域も多くあります。
小児の言語聴覚士の需要は高く、自由診療でお金を払ってでも指導・助言を受けたいという人はたくさんいます。
実際に、1回1時間程度のセッションが7,000円~10,000円とやや高額に設定されていても利用者はきます。
需要の高さに比べると供給は全然といっていいほど追いついておらず、ビジネスとしても新規参入の余地は十分にある領域だと思います。
言語聴覚士によることばの支援を受けたいという保護者の希望は間違いなく多いです。
そのような親子を支える小児分野の言語聴覚士は、間違いなく魅力・やりがいのある仕事です!
フリーランス言語聴覚士として開業する前に小児分野は経験しよう



言語聴覚士として小児分野で開業する前に、一度は小児分野に就職して経験を積むことをおすすめします。
臨床に出て、知識やスキルを高めることは当たり前のことです。
それに加えて子どもを支援するための輪を広げておくことが大切です。
人脈・パイプはフリーランスになった時の武器となる!
実際に医療・福祉・教育の分野でどのような働き方・役割を担っているかを肌感覚として持っているかどうかは重要だと思います。
そして、これらの領域で働いた経験があれば、その領域でのパイプができているかと思います。
そのパイプを活かして、診断や投薬が必要なお子さんには医療を、福祉サービスの利用が必要な場合には行政や事業所に、適切につないであげることができるかと思います。
このように自分のところだけで抱えずに、必要な時には必要な場所につなげるコーディネート力があると、保護者からはより一層信頼されるはずです。
小児では就学に関する相談も多い
就学先の検討や就学後の学校とのやりとりも言語聴覚士が力になれる部分です。
特に、言語聴覚士は個室で親子と関わるといった性質もあってか、保護者から深い部分の悩みの相談を持ち掛けていただくことも少なくありません。
他の専門職・関連職種とのパイプを作って、フリーランスとなってからも対象のお子さんをしっかりサポートできるような体制を整えておきましょう。
そのためには、複数個所での勤務経験が役に立つ場合も少なくありません。
医療と福祉の両方で働いたことのある言語聴覚士など、言語聴覚士の職域の広さを活かしたキャリア形成をしていけると、将来のフリーランスにつながるかもしれません。


フリーランスで働く言語聴覚士の体験談



もともと小児分野で働いていましたが、就学後の療育を引き受けてくれる場所がなかったため、独立・開業してフリーランスとなりました。就学後の療育先を探している人は多く、すぐに想定していた定員は埋まってしまいました。最初は利用者が来てくれるのか心配しましたが、ニーズの高さゆえにそのような心配は不要でした。
自分のペースで働くことを夢みて、フリーランスを志すようになりました。最初の就職先は成人分野でしたが、フリーランスで働くなら小児が圧倒的に有利だと感じたため、働いて3年目に小児分野に転職しました。そこで5年間修業して、自分の地元で開業しています。アパートの一室で開業できるので、最低限の初期投資で始められたのも良かったです。
まとめ:フリーランス言語聴覚士【夢への一歩を踏み出そう】



フリーランスとして働く言語聴覚士に近づくためには、小児分野での複数の領域にまたがった臨床経験があると良いです。
言語聴覚士が専門とする「言葉」の問題は、日常のコミュニケーションや生活と関連が強く、リハビリのニーズが強い分野です。
フリーランスを目指すなら小児分野がオススメ!
特に小児分野の言語聴覚士の需要は高い一方で、サービスの供給が間に合っていない状況のため、
現時点では言語聴覚士は「引く手あまた」という状態です。
フリーランスで働くことを考えている人は、早い段階で小児分野に就職して経験を積み上げておくことをおすすめします。
今は小児分野が転職しやすい!
少し前までは「小児分野は就職先が少ない」と言われていました。
でも、ここ数年では児童発達支援の広がりにより、小児の言語聴覚士の働き口がかなり広がっています。
たとえば、転職サイトをのぞいてみてください。
小児の求人は比較的に容易に見つけられると思います。
今すぐにフリーランスを考えていないとしても、
将来のあなたの可能性を広げておくために、小児分野を経験してみてはいかがでしょうか?
まずは転職サイトに登録しよう!
フリーランスを目指すなら、複数の職場経験があることで知識も人脈も広げられます。
今すぐに転職しないとしても、転職サイトに登録して情報収集をしておくことが大切です。
転職サイトは相談だけで登録することも可能です。詳しくは【転職エージェントは相談だけでもOK?相談のコツとおすすめエージェントを紹介】の記事でも解説しているので、参考にしてみてください。
初めての転職の場合には、何から始めて良いのか分からず途方に暮れる人も多いです。
以下の転職サイトでは、転職活動の段取りや、履歴書の書き方・面接対策までアドバイスをもらえます。
これらが全て無料で利用できるのですから、利用しないなんて損ですよね。
当ブログでは、小児分野の言語聴覚士として働きたい人に向けて、様々な情報を発信しています。
以下のリンクに記事をまとめてありますので、ぜひ、ご覧ください!


