
「小学校に向けて勉強の習慣をつけたい。でも、嫌がって全然勉強してくれない。なんでこんなに嫌がるんだろう?今すぐできる対策があるなら知りたいな」
こういった悩みにこたえます。
- 年長で大切なのは「学ぶ楽しさ」
- 勉強が嫌いな3つの原因
- 勉強が好きになるための3つの工夫



小学校に入学する前から勉強が嫌いだなんて、ちょっと心配になってしまいますよね。
でも、無理やり勉強させようとすると、さらに勉強嫌いになってしまって小学生になってからが大変になってしまうかも…。
就学前に大切なのは『学ぶ楽しさ』を育むこと。
年長さんの頃から勉強を嫌がるなんて、なにか理由があるはず!原因を理解して対応しましょう。
この記事では、勉強を嫌がる原因を3つ解説し、それぞれの原因への対策を紹介します。
それでは、さっそくお読みください。
目次
年長さんが勉強を嫌いになる3つの原因



「なんでこんなに勉強が嫌いなんだろう?小学校に上がってから大丈夫かな……」
と焦ってしまいますよね。
まずは、お子さんが勉強を嫌がっている原因を考えてみましょう。
①:親から言われすぎた
②:他にやりたいことがある
③:勉強の内容が難しすぎる
順番に解説します。
原因①:親から言われすぎて嫌になった
あなたも小さい頃に「早く宿題やりなさい!」といわれて、余計にやる気が失せてしまった経験がありませんか?
実は、「〇〇しなさい」と高圧的にいわれると、余計に「〇〇するもんか」と抵抗したくなってしまうことが心理学で証明されています。
要するに、「勉強しなさい」と子どもに命令するように言うことは、子どものやる気を知らぬ間に奪ってしまいます。
また、ほかの子と比べられることでやる気をなくしてしまう子もいます。
「〇〇くんはもうお名前かけるよ」など、お友達や兄弟と比べることは絶対にやめましょう。
比べるべきは過去の我が子です。
お子さん自身の進歩を一緒に喜んであげましょう。
原因②:他にもっとやりたいことがある
年長さんにとって、
「勉強は小学生になったらやるもの」
「他に楽しいことがあるから、今はやらない」
となっているのかも。
例えば、家でゲームをしたり、テレビをみたり、おもちゃで遊んだり。
お子さんには勉強の他に、もっとやりたいことがある場合も多いです。
この状態で勉強をさせようとしても、なかなかうまくいかないですよね。
少し考え方を変えて、お子さんが好きな活動を活かした学習方法がないか考えてみましょう。
例えば、ゲームやテレビが好きな子なら、タブレット学習が向いているかもしれません。
おもちゃが好きな子だったら、知育玩具やプログラミング学習なども良いかも。
お子さんが夢中になれる学習方法を見つけてあげることも、就学後の力につながります。
原因③:本人のレベルと勉強の内容が合っていない
今やらせようとしている教材が、子どもにとっては少しレベルが高くて難しく感じているのかもしれません。
または、得意な分野と苦手な分野の能力の差が大きくて、「年長用」の教材を用意しても簡単すぎたり、難しすぎたりしているのかも。
子どもの知的好奇心を高めるには、子どもの発達の状態に合わせた教材や関わりが必要。
年齢や学年にとらわれすぎず、お子さんの能力に合わせた教材を探してみましょう。
年長さんの勉強嫌いに今すぐできる3つの対策



今すぐできる3つの対策は以下のとおり。
- 子どもの発達の状態に合わせた教材を工夫する
- 子どもがすでにできていることに目を向ける
- 子どもの「好きなこと」を活かす
対策①:子どもの発達の状態に合わせた教材を工夫する
子どもたちは素直。
むずかしい、できない、と感じると
スーッといなくなってしまいますよね。
子どもたちの発達のレベルに合わせた教材を用意することが大切です。
市販の「年長さん用」にこだわる必要はありません。
子どもが楽しめるレベルを探してみましょう。
お子さんによっては、ひらがなは得意だけど、数は苦手など内容によって能力のデコボコがあるかも。
そのため、ひらがなは年長さん用だけど、数は年中さん用など、使い分けるのも手です。
以下で紹介するような難易度や子どもの興味を活かす工夫をしてみましょう。
》【厳選】発達障害をもつ幼児におすすめの通信教材【各社の比較:ベスト3】
対策②:子どもがすでにできていることに目を向ける
年長さんの時期には「学ぶ楽しさ」を育てることが大切。
まずは、机に向かうと良いことがあるという経験を積みましょう。
そのために、まずは子どもがすでにできるところから。
「できた!」→褒められた!→もっとやりたい!
このサイクルを回せるようになりましょう。
子どもの「好きなこと」を活かす
なかなか気持ちが勉強に向かない…
このような場合には、子どもの「好きなこと」を活かせると良いでしょう。
なにも机に向かって、文字や計算を繰り返すことだけが勉強ではありません。
たとえば、今話題のプログラミング学習。
パソコンやタブレットが好きな子なら夢中になれるかも。
プログラミングの中では論理的な思考が身に付きます。
小学校での必修化も始まるため初めておいて損のない科目です。
》【決定】発達障害をもつ子におすすめのプログラミング教室3社【目的別に紹介】
勉強嫌いな年長さんに小学校までに育みたい力
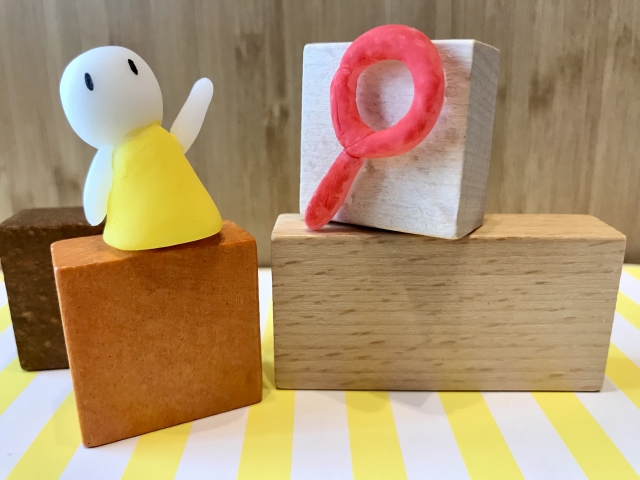
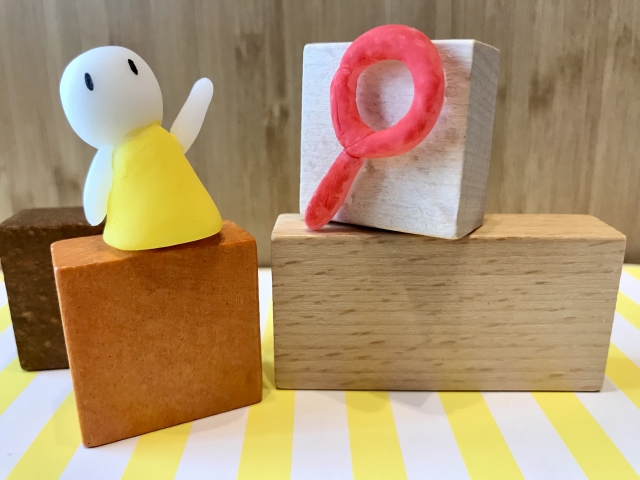
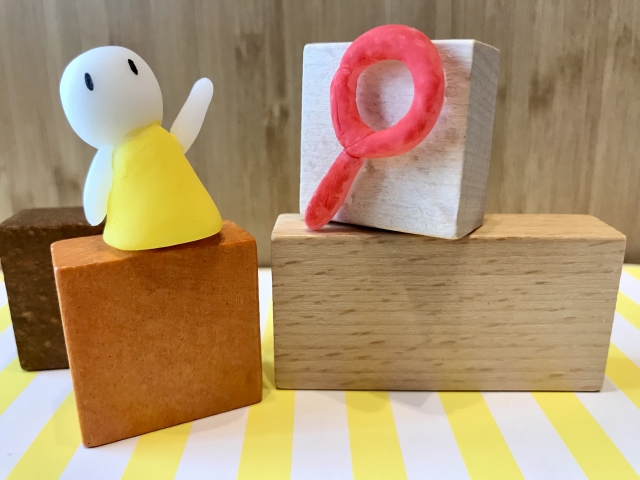
「もうすぐ小学校にあがるのに・・・」
と焦ってしまう気持ちも分かります。
では、小学校に上がるまでに、何をどこまで理解している必要があるのでしょうか?
一番大切なのは「学ぶ楽しさ」
「学ぶ楽しさ」は、年長さんの時期に最も育てたいものです。
学ぶことが楽しいと感じられれば自然と机に向かいますよね。
学習の達成感と充足感は「学ぶ楽しさ」を育てます。
要するに、お子さんに合った教材で「分かる」経験の積み重ねと褒められた経験が「学ぶ楽しさ」を育てるのです。
ひらがなは8割くらい読める
小学校入学の時点で、ひらがな清音の大部分は読めるようになっている子が多いと研究結果でも示されています。
しかし、中にはひらがなが全く読めないという子もいます。
年長さんの時期に大切なのは、ひらがな習得の土台を固めておくこと。
ひらがな習得の土台については、以下の記事で詳しく解説しています。
数は「合わせる」「減らす」などの操作
小学校入学の時点で足し算や引き算を理解している必要はありません。
年長さんの時期には、「合わせる」「減らす」などの数の操作を、生活の中でたくさん経験しておくことが必要。
数の操作の経験があれば、入学後にそれを数式に当てはめるだけです。
年長さんの時期に大切なのは、数概念をしっかりと固めておくこと。
数概念の土台については、以下の記事で詳しく解説しています。
>>かぞえるだけが数概念じゃない?数概念の4つのポイントを解説
まとめ:勉強嫌いな年長さんには「学ぶ楽しさ」を育てよう!
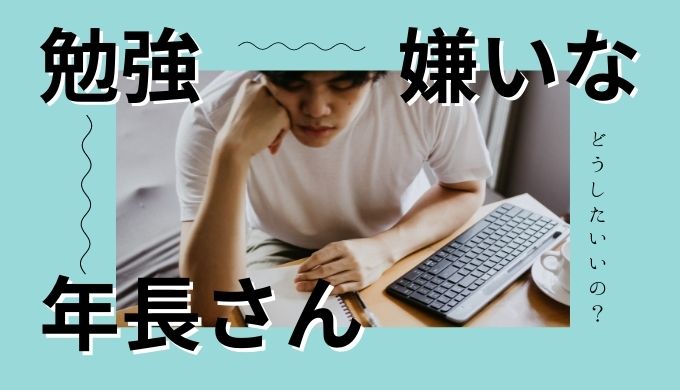
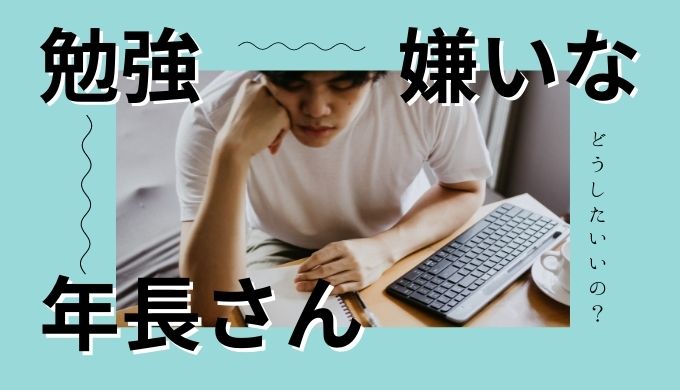
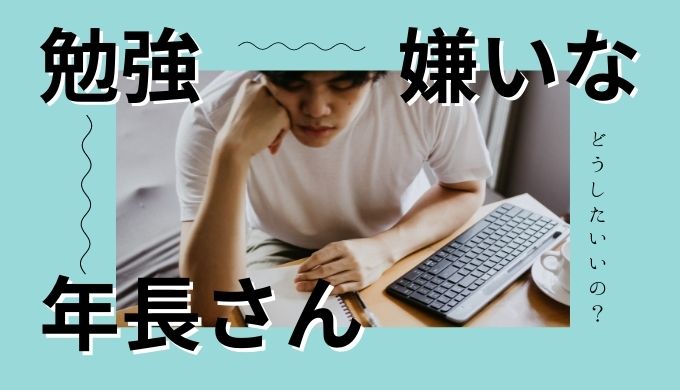
いかがでしたか?
この記事では「年長さんの勉強嫌い」について、3つの原因と対策を解説しました!
最後に内容をまとめます。
- 親から言われすぎ→既にできていることを認める
- 他にやりたいことあり→好きなことを活かす
- 内容が難しい→子どもの発達に教材を合わせる
この3つを理解していれば、
子どもに怒ってしまうことは減って
建設的に子どもの学習のサポートができるはずです。
「子どもに合った教材を探したい」
という方は、お子さんの興味に合わせて以下の教材を検討してみてはいかがでしょうか?
無料体験や資料を請求して、お子さんに合うかどうかを見極めましょう!
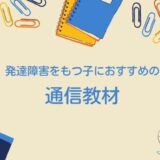
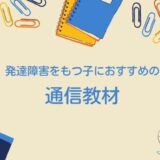
- 【天神:幼児版】:子どもの知っていること7割、知らないことを3割で教材がつくられているそうです。楽しみながら机に向かえる子が多い!
- 【LITALICOワンダー】:子どもとの関わりに慣れている講師陣が多いプログラミングスクールはここ!
- 【読むトレGO! for 任天堂スイッチ】:ゲームで楽しく文字学習。これなら間違いない!


