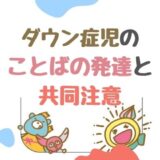ダウン症のお子さんをもつ親「うちの子、発音が不明瞭で聞き取りづらいけど、どうにかならないだろうか?親でもできる具体的な方法があるなら知りたいな」
このような疑問にこたえます。
- ダウン症をもつ子の発音不明瞭の原因とは?
- 発音を育てるために、できること
- 舌の動きと音の認識の発達が発音を育てる



この記事を書いている僕は、言語聴覚士としてダウン症をもつ子の療育を担当して15年ほど。その経験と知識から解説していきます。
ダウン症をもつ子の発音の不明瞭さは、多くの親御さんが心配されています。
ある研究では、ダウン症児の親の90%以上が、子どもの発音を心配していたと報告されるほど(Kumin, 1994)。
発音が不明瞭となりやすい原因は何か?どのように関わることで発音を育てられるのか?
こういったテーマで解説していきます。
目次
なぜ、ダウン症児は発音が不明瞭となりやすいのか?



結論からいうと、以下の問題を併せ持ちやすいからです。
- 聴力障害
- 顔のつくりの違い
- 舌運動の未熟さ
- 認知・言語発達の遅れ
順番に解説していきますね。
原因①:聴力障害
ダウン症のお子さんでは聴力に障害がある場合が少なくありません。
正しい発音の獲得には、しっかり聴こえていることが重要な役割を果たします。
それを裏付けるように、ダウン症のお子さんの聴力低下と発音の不明瞭さの間には関連性があることが研究によっても明らかにされています(Chapman et al., 2000)。
要するに、『耳の聴こえにくいと、正しく発音を聞きとれないため、自身も正しい発音が身につけられない』ということになります。
聴こえにくさがあるのではないかと気になる場合には、耳鼻科を受診して相談してみましょう。


原因②:顔のつくりの違い
ダウン症をもつ子の中には、定型発達の子とは顔のつくりが異なる場合が多く、形態の違いから発音が育ちにくいという面もあります。
具体的には、顔面の真ん中あたりが低形成であり、口の中の容積が小さいお子さんが多いです。
ダウン症のお子さんは舌が大きいと言われることもありますが、最近の研究では、舌の筋緊張が低く、口の中が狭いため、相対的に舌が大きく見えているだけである場合が多いといわれています。
このような顔のつくりの違いにより、音声の共鳴(声が体の中でひびく感じ)が定型発達児と異なるため、発音の明瞭度が低下することがあるようです。
お子さんによっては、口の中の矯正が必要な場合もありますので、必要に応じて歯科にご相談されると良いかもしれません。
原因③:舌の運動の未熟さ
ダウン症をもつ子の多くは、舌の運動がゆっくりと育ちます。
発音=舌などの口腔器官を動かして音を作る
簡単に言うとこのような特徴があるので、舌運動の育ちにゆるやかさは発音にも影響がでてきます。
例えば、「た」を発音する時には、舌の先を前歯の裏側につけて発音しますよね。しかも、舌運動にかなりのスピードと正確性が求められます。
このような発音に必要な舌の動きの基礎は、離乳食を食べる時期にも発達します。詳しくは以下の記事で紹介していますので、お読みください。


原因④:認知・言語発達の遅れ
ダウン症をもつ子では、中等度から重度の知的障害があることが多いといわれています。そして、以下のような特性を持ちやすいことが知られています。
- ことばで理解するよりも見て理解する方が得意であり、ことばの理解力が表現力よりも優れている場合が多い(Næss et al., 2011)
- 聞いた情報を覚えること(ワーキングメモリー)や、文の理解、音韻認識(単語の音を認識・操作する力)の弱さが目立つ(Chapman, 2006)
- 特に、聞いた音を正確に把握して、記憶にとどめておくことが苦手である可能性がある(Vicari et al., 2004)
これらの研究結果を簡単にまとめると、「聞いた単語の音を正確に把握することが苦手なため、単語の音のイメージが曖昧なまま覚えている」という可能性があると考えられます。



たとえば、覚えている単語でも『メガネ』のことを「めがめ?」「ねがめ?」「げなめ?」と音を曖昧に覚えている場合があります。
発音の明瞭さに、どのように対応すべきか?



結論からいうと、『聴力』『口の中の構造』を確かめた上で、『発音の土台となる力をコツコツと育む』ということが大切。
聴力の確認
正しい発音を獲得するためには、聴力が重要な役割をはたします。
そのため、発音の不明瞭さがある場合には、一度、耳鼻科で聴力検査を受けることをおすすめします。
仮に、聴力に問題がある場合には、補聴器などを検討することで、聴力を保障してから発音改善に向けた次のステップに進むことになります。
おくちの中の構造を確認
発音の多くは、口の中で音をつくります。
そのため、舌が自由に動けるようなスペースを確保することが大切です。
ダウン症をもつ子でも、特に矯正治療をしなくても済むお子さんが多いですが、歯科検診に行ったついでなどに、発音の獲得に影響を与えるような歯並びや顎の特徴などがないか聞いてみると良いと思います。
発音の土台となる力を育てる
発音の土台となる力として、以下の3つを丁寧に育てていきましょう。
- 全体的なことばの発達
- 舌やくちびるの動き
- 音を認識する力
順番に解説します。
発音が明瞭になるためには、ことばの発達が一定の水準まで育つことも大切です。
実は、定型発達の子でも4歳になるまでは発音の個人差はかなり大きい。大人のように話す子もいれば、まだまだ赤ちゃんことばという子までいます。
しかし、言語発達が4歳代を超える頃には、多くの子で自然と正しい発音を獲得していきます。
ダウン症をもつ子でも同様、ことばの発達が4歳代を超える頃になると発音がしっかりしてくる場合が多いです。
- 単語を1音ずつ手を叩いて言える(例:「た・い・こ」)
- じゃんけんグリコが楽しめる
- 「しりとり」のルールが分かり始める
このような姿がみられはじめたら、発音を獲得する土台が整ってきたと思ってよいかもしれません。
繰り返しになりますが、発音がしっかりするためには舌やくちびるの運動が育つ必要があります。
舌やくちびるの動きは、毎日の食事の中でも育ちます。食べる機能と舌運動の関連については以下の記事で詳しく解説していますので、お読みください。
》ダウン症児の離乳食の進め方の目安
食事の他にも、口元をつかって遊ぶ経験は小さい頃からたくさんしていけると良いと思います。例えば、シャボン玉や巻き笛、吹き矢、紙風船など。
くちびるをすぼませて吹く経験は、くちびるを閉じる筋力の強化にもなります。
単語の中の音の認識を育てていくことは、発音に良い影響をあたえます。
この音の認識ですが、ダウン症をもつ子の多くで苦手さがあると言われていますので、丁寧に・ゆっくりと育てていきたいですね。
音の認識を育てる関わりとして、以下の順番で取り組まれると良いかも。
- 擬音語・擬態語を使った関わり
- 韻を踏むような歌遊び
- 単語を音に区切る遊び(じゃんけんグリコ等)
- 単語から音を抜き出す遊び(しりとり等)
擬音語や擬態語は、「ワンワン」「ジュージュー」などと音が繰り返されている語が多いので、子どもにとって音を認識しやすいといえます。
「おもちゃのチャチャチャ」「だいこんはコンコンコン」などの歌遊びも音の認識を助けてくれるのでオススメです。
グーで勝ったら「ぐ・り・こ」と3歩進む『じゃんけんグリコ』、単語の一部の音を取り出す『しりとり』のような音遊びができるようになれば、ひらがなの習得も進むかもしれません。
ひらがなが読めるようになると、音が耳からだけでなく、目からも認識できるようになるため、発音がしっかりしてくる子も多いです。
まとめ:発音を育てるために、できること
-520x300.png)
-520x300.png)
-520x300.png)
ダウン症のお子さんたちの発音の改善は長期にわたるという論文があります(Wild et al., 2018)。この論文では、16歳くらいまで改善が認められたと報告していますので、ゆっくりと時間をかけながら気長に育てていきたいものです。
最後に、ダウン症をもつ子の発音を育てるために、この記事で紹介したことをまとめます。
- 聴力障害→耳鼻科で確認
- 顔のつくりの違い→歯科で矯正の必要性などを確認
- 認知・言語発達の遅れ→特に音の認識を育てよう
- 舌運動の未熟さ→食べる機能や舌の運動を育てよう
こんな感じです。
少し内容が専門的で分かりにくいところがあったかもしれません。ご質問などあれば、気軽にお問い合わせからご連絡ください。
それでは、今回はここまで。

.png)