
うちの子、まだことばが出ないけど、どんな関わりをしてあげたらいいんだろう?
お子さんのことばが出る前の小さい時期、療育にかかっていても理学療法(PT)が中心だったり、言語聴覚療法(ST)でも摂食が中心だったりと、ことばに関する療育って始まるのが遅い場合が多いですよね
本当は、気になった時に、いつでもアドバイスが受けられるといいな、と思うのですが、それぞれの療育センターやクリニックの事情もあるのかもしれません
せめてアドバイスだけでも届けられたら・・・と感じる今日この頃です
そこで、今回は、ご家庭で簡単にできることばを育てる関わりの一つを紹介しようと思います
前半は、研究結果を紹介しながらなので少し難しく感じる部分もあるかもしれませんが、できるだけ分かりやすく解説しようと思います
後半には、日常の中で気を付けたいポイントを分かりやすくまとめました



ぜひ、最後までお読みいただき、日常のお世話の中に取り入れてみてください



目次
ダウン症児の多くは、生後9~14か月頃に座位を獲得し、12~18ヶ月頃にはいはいでの移動を開始します
そして、多くの場合で歩行を開始するのは24ヶ月以降になります
音声の始まりである喃語は、個人差が大きいものの15ヶ月くらいに出てくることが多いようです
要するに、ダウン症児は音声が出始める頃に座位や四つ這いといった運動機能を獲得している場合が多いと考えられます
運動発達に関しては、座位の獲得時期が早いほど、歩いたり、走ったり、ジャンプできるようになったりといった、全身の運動の発達が早い場合が多いとする報告があります(Locatelli et al., 2021)
しかしながら、座位の獲得時期に関しては、学齢期以降の運動スキルを予測するものではないようです(Locatelli et al., 2021)
ということは、将来の運動スキルが乳児期に決まるものでもないので、気長に成長を待っていて良いのではないかと思います
ただし、座位ができるようになる時期と言語発達との関連は近年注目されてきています
定型発達の子どもの場合、座位は喃語の開始に関係しています(Iverson et al., 2010)
これは、座位では胸郭が重力で下がることも関係して呼吸が深くなり、同じく重力の影響を受けて舌が口腔内で前方に位置するようになるため、喃語を産生しやすい条件がととのうためと考えられています
座位が可能となることで、子どもは両手を自由に使って周囲の物を探索することができるようになります
これにより、親と会話をする機会が増え、言語・コミュニケーションの発達に重要な共同注意場面が増加します。
この場合の共同注意とは、親と子が同じ対象に注意を向けている状態をさします。
共同注意場面では、子どもが興味を示している物へ親の注意を向け、親が子どもが興味を示している物の名前を言うことにより、ことばを学習する機会が提供されます(Libertus et al., 2016)
要するに、座位の獲得は、親とのことばを用いたやりとりの機会を増やすきっかけとなります
この時期に、子どもの興味の先をしっかりと大人が把握して、関わりを持っていくことがことばの学習には重要といえるでしょう
それを示すように、親子の共同注意を多く経験した児ほど、その後の理解語彙が多かったとする研究結果は多くあります(例えばZampini et al., 2015)
しかも、ダウン症児は他の発達障害に比べて、認知や言語発達に比べて共同注意が相対的に強みである可能性が指摘されています(Hahn et al., 2018)
たしかに、ダウン症のお子さんは人懐こく、自分の持っているものを見せてくれたり、逆に相手が見ているものに視線をうつしたり、といったことを自然とできる場合が多いように思います
それを裏付ける研究結果として、ダウン症児は「対象物を見てから、親を見て、また対象物を見る」といった視線の使い方(TEG)は、他の発達障害のお子さんよりも頻繁に行うことが示されています(Hahn et al., 2019)
この視線の往来(TEG)は、たとえば子どもが飲み物を要求するために、親を見てからコップを見て、また親に視線を戻したりする姿として日常ではみられます
すなわち、共同注意を自分から成立させるための視線の使い方をしているわけですね
ダウン症児では、この視線の往来(TEG)をよく経験した児ほど、理解言語が良く育ち、その後にことばでの表現も良く育っていたそうです(Hahn et al., 2019)
以上をまとめると
- 座位を獲得する頃には共同注意が成立しやすい条件がととのう
- ダウン症児は自分から視線を用いて親と共同注意を成立させる頻度が高い
- 共同注意の経験は、ことばの発達に良い影響を与える
となります
これらの研究結果を踏まえると、ダウン症児の早期の言語獲得に向けては、彼らの強みでもある共同注意スキルをうまく引き出し、しっかり活用させてあげることが重要と言えると思います
では、これらの研究結果を踏まえて、ことばが出る前のダウン症のお子さんへは、どのような関わりを日常の中に加えると良いのでしょうか?
ポイントは、
- 向かい合って遊ぶ
- 少し大げさにリアクションをする
- お子さんが興味を持って見ている対象物の名前を言って聞かせる
となるかと思います
なんだか研究結果をならべて難しいことを言ってきたわりには、関わりのポイントが当たり前に感じた方も多いかもしれません
でも、この当たり前の関わりがしっかりことばを育ててくれることが証明されてきていることが大切で、自信を持ってこれまでどおりに遊んであげてください
ポイントの中で、「あまりやってなかったな」と思うものがあった方も大丈夫です
今から意識するだけでもお子さんは成長してくれます
それぞれのポイントについて、少し補足します
自然と相手の顔に注意が向きやすいような環境を設定するため、向かい合ってあそぶ時間を大切にしてあげてください
おすわりができるようになっていれば床でも良いですが、まだ倒れちゃいそうで不安な時には、座位を保ちやすいような椅子(バンボなど)を使うのも良いでしょう
ダウン症のお子さんでは、相手の視線や表情、ジェスチャーなどを見ることが得意な子が多いです
でも、まだ小さい頃には、これらの力が十分ではありません
大人が少し大げさにビックリした顔をしたり、対象物を見る時に視線だけではなく顔ごと対象物の方に向けたり、身振り・手振りを交えてコミュニケーションをとってあげることで、子どもたちは相手の出したメッセージに気づきやすくなります
子どもは、共同注意の場面で言われたことばをより効率的に学習します
お子さんが差し出してくれたものについて、「コップ、あったね」と声かけをする
お子さんが手の伸ばした先にあるものについて、「くまさん、ほしいね」と声かけをする
要するに、子どもが感じていそうな気持ちを代弁するように、その場でナレーションを入れていくようなイメージです
ダウン症のお子さんの初期言語発達に共同注意がいかに大切かを解説しました
・座位の獲得➔共同注意が成立しやすくなる:この時期に向かい合って遊ぶ経験が大事!
・ダウン症児は共同注意を成立させようとするポテンシャルが高い子が多い
・少し大げさにリアクションしながら、お子さんの興味・視線にそった声かけをしよう!
研究結果を引用しながらの解説だったため、少し難しく感じられた方もいるかもしれませんが、大事なポイントは実践しやすいものかと思います
ポイントを意識するだけで、少し自信をもって関われることが増えるかもしれません



できるところから、少しずつ実践してみていただけたらと思います
日常の中で具体的に使用できるおススメの玩具などはこちらの記事でご確認ください。

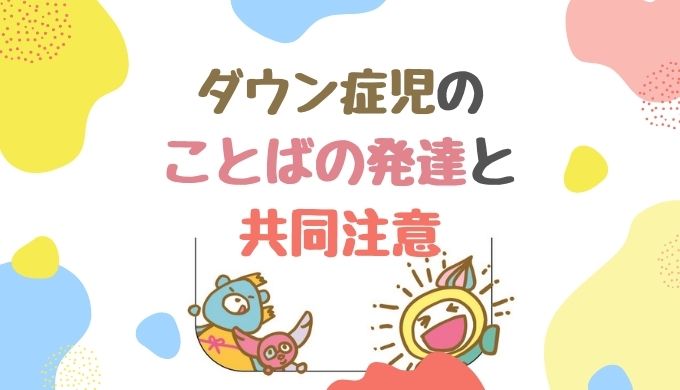
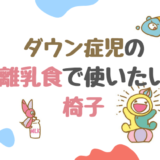
-160x160.png)