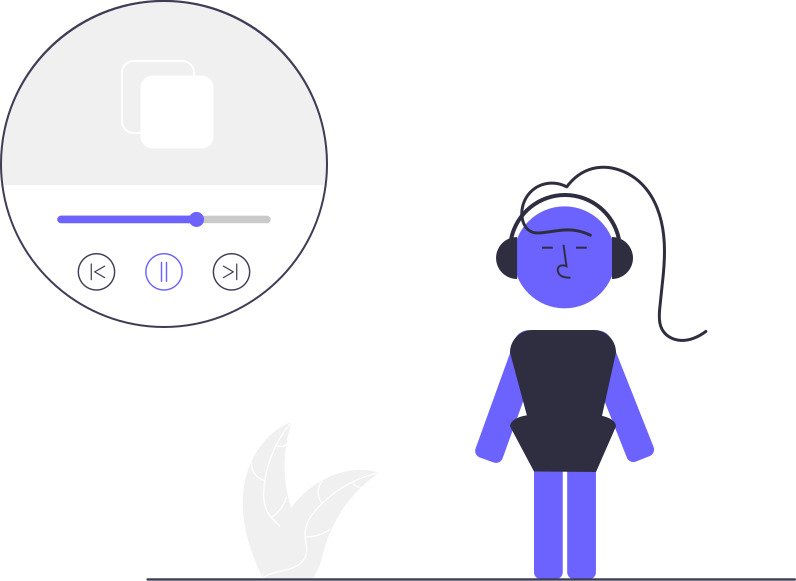うちの子、ことばがなかなか出てこなくて心配。耳のきこえがことばの発達に大切って聞くけど、もしかして聴力に問題があるのかな?ことばの発達と聴力の関係とか、聴力の調べ方とかを知りたいな。
こういった疑問にこたえます。
- ことばの発達に聴力は重要な役割をはたしている
- 中耳炎などの病気で聴力が低下することもある
- 聴力検査にはいろいろな種類がある



この記事を書いている僕は、言語聴覚士という立場で、ことばの発達がゆっくりな子たちの支援をしています。
子どものことばがなかなか出てこないと心配になりますよね。
ことばの発達が心配な時、耳がちゃんと聞こえているかを確認しておくことは大切です。
なぜなら、聴力の問題がある場合には、早期に発見して支援を開始することがことばの発達に良い影響を与えるからです。
実際に、ことばの発達を心配して医療機関に相談に来た子の一定数で、耳のきこえに問題が見つかります。
この記事では、ことばの発達と聴力の関係を解説したうえで、日常のどのような行動から聴力の問題を疑い、どのように聴力を調べていくのかをお伝えします。
読み終えたとき、少しでも子どもの聴力が心配であれば、耳鼻科に相談をしてみてください。
目次
なぜ、言葉の発達に聴力が大切なのか?
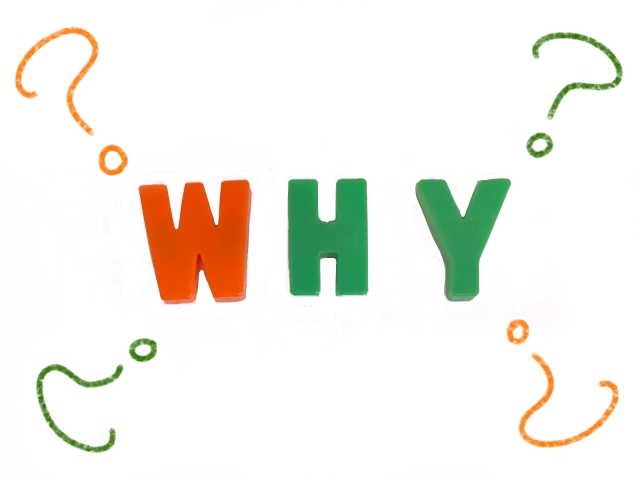
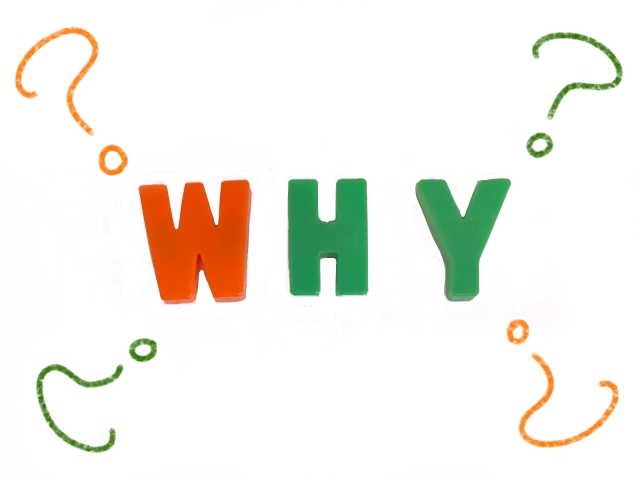
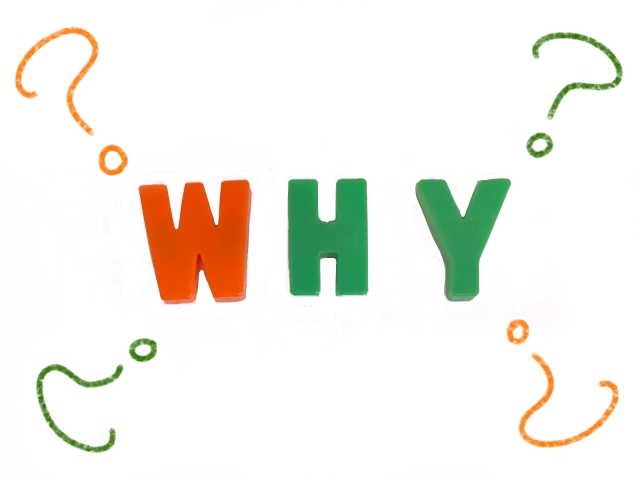
ことばの発達には聴力が重要な役割をはたしています。
なぜなら、初期のことばの発達では、大人が言ったことばを”聞いて”、子どもたちはことばを覚えるからです。
たとえば、聴力に問題があって聞こえにくい子では、生活の中で大人が言ってることば上手く脳にインプットされず、ことばを理解する力が育ちにくくなってしまいます。
ことばを話すためには、ことばを理解する力が育つことが必須なので、なかなか話せるようにならないといった状態になってしまいます。
>>【ことばの発達の3側面:ことばが話せる前に理解できるようになる】を読む
そのため、聴力に問題が疑われる場合には、できるだけ早く聴力検査をするなどして発見し、支援を開始する必要があります。
これは、子どもたちがことばを学ぶ時期に、可能な限り学びやすい状況を作ってあげるためです。
具体的には、補聴器や人工内耳といった聴力を補う手段を用いて聞こえを改善させたり、手話や口話といった方法でコミュニケーションを経験させたりします。
要するに、ことばの情報をあらゆる手段で子どもにインプットさせていくイメージですね。
ことばの発達を考える時には、まずは聴力の問題の有無を調べて、もしも聞こえにくさがあるようならまずは聴力に関する手立てをしていくことが重要になります。
産まれた時の聴力検査でOKだったから大丈夫?






たしか、産まれた病院で聴力検査をして問題なしって言われたような。この時点で問題がなければ聴力って大丈夫なんじゃないの?
産科によっては、新生児聴覚スクリーニング検査を産まれてすぐに実施している場合があります。日本では諸外国に比べるとかなり普及しており、聴力障害の早期発見・早期支援につながっています。
しかし、以下の2つの理由で、産まれたばかりの聴力検査で問題なしとなっていても、聴力障害が見つかることがあります。
- 新生児聴覚スクリーニング検査で100%問題を発見できるわけではない
- 成長の過程で聴力の低下が起きる場合がある
新生児聴力スクリーニング検査の精度は完璧ではない
残念ながら、新生児聴力スクリーニング検査で全ての聴力障害を発見できるわけではありません。
これはどのような検査にも言えますが、100%の制度で異常をみつけることは難しいのです。
そのため、成長の過程で聴力が心配になった場合には、再度聴力検査を受ける必要があります。
成長の過程で聴力の低下が起きる場合がある
新生児聴覚スクリーニング検査で異常がなかったとしても、その後の成長の過程で聴力障害が生じることがあります。
例えば、中耳炎にかかると耳の中に水がたまって一時的に聞き取りにくい状態になったり、中耳炎を繰り返すことで聴力が低下してしまったりすることがあります。
子どもが小さいうちは中耳炎などを繰り返すことは仕方ないですが、耳の病気にかかりやすい子では、こまめに耳鼻科に受診して様子をみていけると良いでしょう。
聴力障害が疑われる行動とは?
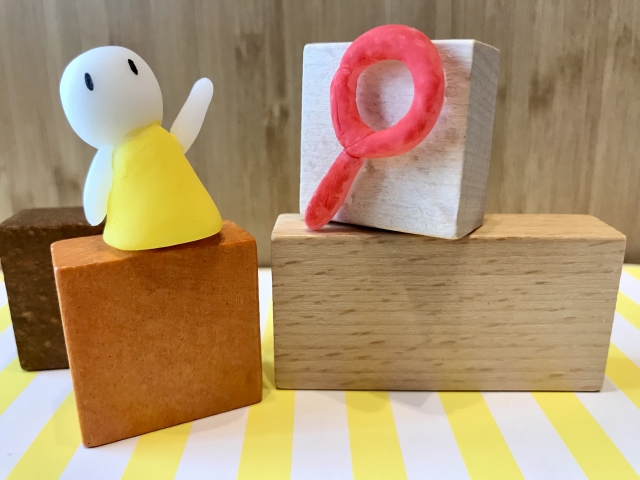
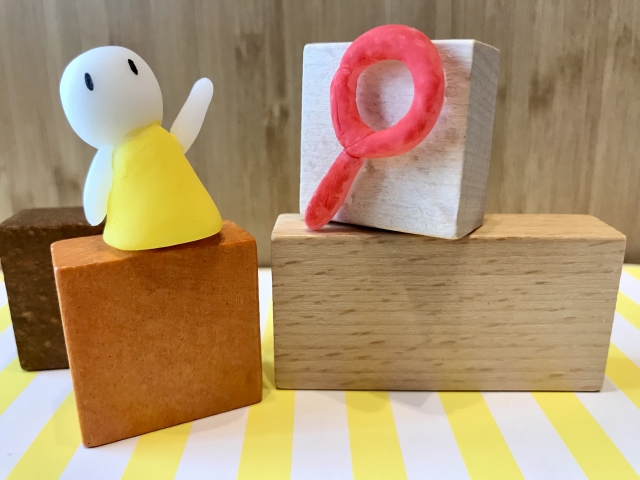
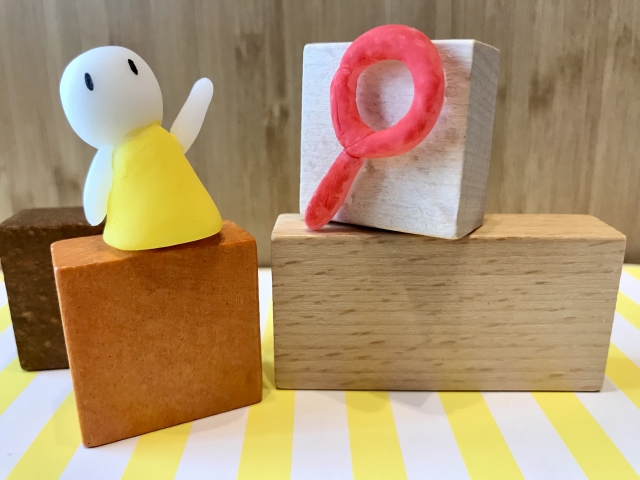
日常の中で、以下のような行動がきっかけで聴力障害に気づける場合があります。
- 声かけに振り向かない
- ささやき声に反応しない
- テレビの音を大きくしたがる
これらは代表的な聴力障害を疑う行動ではありますが、日常生活の中では目に見える情報で判断して行動できてしまうことも多く、発見は容易ではありません。
日本耳鼻咽喉科学会のホームページに、家庭で出来る耳のきこえと言葉の発達のチェック表や1歳6ヶ月児健診や3歳児健診での聞こえの確認に関する資料も掲載されています。
一度、確認してみてください。
聴力検査はいつからできるの?



産まれてすぐの赤ちゃんから実施できる検査があります。
それぞれのお子さんの発達の状態に合わせて、検査を選択して聴力を調べます。
かかりつけの耳鼻科で検査が難しくても、主治医に相談することでお子さんに合った検査が実施できる病院を紹介してもらえると思います。
お子さんに眠って頂き、頭に電極を貼った状態で音を聞かせて、脳波から聴力の状態を評価する検査です。
お子さんは寝ているだけなので、0歳から実施できます。
お子さんの左右のどちらかから音を鳴らし、音が鳴った方から映像が出てくるような仕掛けで聴力を評価します。
検査は音を出した後に、お子さんが映像を探すかどうかといった行動をもとに聴力を評価します。
ヘッドホンをつけ音が出ている時だけボタンを押すといった検査です。
大人がやる検査に似ていますが、音が鳴っている時にボタンを押すと電車が動くなどの遊びの要素が入っています。
これらの検査からお子さんが実施できそうなもの選び、必要に応じて組み合わせて聴力を評価します。
まとめ:言葉の発達が気になる子は聴力を確認しよう



ここまでをまとめます。
- 聴力はことばの発達に重要な役割をはたしている
- 産まれた時の聴力検査で問題がなくても、その後の成長で聴力に不安があるなら検査をするべき
- どの年齢でも聴力検査は実施できる
- ことばの発達が心配な場合には、聴力も確認しておこう
聴力に問題がある場合には、ことばの発達が遅れたり、発音が不明瞭なまま育ちにくかったりと言語発達に影響が出てきます。
ことばの発達を促すための支援を考える上でも、聴力の問題の有無によって支援方針が変わります。
そのため、ことばの発達に心配がある場合には、一度、聴力検査を実施して確認しておくことが必要です。
聴力検査は耳鼻科でとることができます。ただし、子どもが小さく、特殊な聴力検査の機器が必要な場合には大学病院や療育センターなどの専門的な医療機関に行く必要があるかもしれません。
まずは、かかりつけの耳鼻科や小児科で相談してみましょう。必要であれば、適した病院を紹介してくれるはずです。
当サイトでは【言葉の発達に大切なこと | ゆっくり?遅れてる?言語聴覚士が完全解説!】の記事に、ことばの発達に関する記事をまとめて紹介しています。
ことばの発達の順番に記事を並べていますので、お子さんの発達の状態に合わせてお読みいただけます。
\クリックして記事へ移動!/