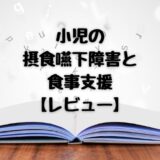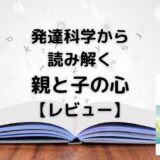先日、このようなツイートをしました。
スモールステップは使いたい子が使えばいい。使う必要のない子は1段飛ばしでも2段飛ばしでのぼってもいい。使いたいと思う子のために用意しておくステップで、だれも使わないならそれでいい。でも、登れない子を出してはいけない。
— ゆう@ことばと摂食の発達・療育・リハビリ (@hagukumichild) August 7, 2021
といった説明が僕にはしっくりきています。
障害をもつ子たちは、能力の凸凹(デコボコ)や偏りがあったり、発達がゆっくりであったりするために、日常の生活の中で支援を必要とする場合があります。
支援を検討する上で、目標までの道のりを細かいステップに分け、少しずつ登っていけるように配慮するスモールステップといった考え方があります。
スモールステップを組むことで、子どもたちは達成感をかんじながら、自信を育んでいくことができます。
スモールステップはとても有効ですが、集団生活の中で支援として組み込もうとすると、以下のような懸念をお聞きすることがあります。
子どもにスモールステップを組んでほしいことを伝えると、一人の子だけに特別な対応はできない。他の子が「ずるい」と感じてしまう。と言われることがあります。しかし、子どもたちは支援を「ずるい」とは思わないことが多いです。「ずるい」と思う子がいるなら、その子にも支援を与えれば良いと思う
— ゆう@ことばと摂食の発達・療育・リハビリ (@hagukumichild) August 7, 2021
本記事では、スモールステップの効果やメリット、支援する上での懸念への回答について解説しようと思います。
目次
発達障害児へのスモールステップとは?

スモールステップとは、目標に到達するまでのステップを、対象のお子さんが一つ一つ達成しやすいような細かいステップに分けて、少しずつ・確実に登っていけるような配慮のことをいいます。
たとえば、「ズボンを自分ではけるようになる」といった目標があったとすると、最初は「大人が足をとおしてあげて、子どもはズボンをあげるのみ」という段階から始めます。
これができるようになったら、「大人が片足だけとおしてあげて、子どもはもう片方を自分でとおしてズボンをあげる」。
さらに、これができるようになったら「大人がはきやすい向きにして子どもの目の前にズボンを置き、子どもが自分ではく」といったようにいくつかのステップに分けて目標とした行動に近づけていきます。
発達障害児へのスモールステップの効果・メリット



スモールステップには、以下のような効果・メリットがあります。
- 子どもが達成感をもって取り組みやすい
- 子どもを褒めるポイントが明確
- 子どものつまづきポイントが分かりやすく、次の支援につながりやすい
スモールステップに課題を設定することで、お子さんは1つずつ確実に課題を達成していくことができます。
「できた」の積み重ねはお子さんのやる気・モチベーションを高めます。
やる気とモチベーションが高まるから、次の段階のステップにも挑戦しようといった意欲が湧いてきます。
お子さんが確実にできる難易度のステップから始めて、少しずつレベルアップし、7~8割できるところを見つけたら、その段階を繰り返して9~10割できるようになってから次の段階にうつるとうまくいく場合が多いです。
ポイントは、「できた」を繰り返し経験させてあげることです!
スモールステップをどのように組んでいくかを考える段階で、すでにお子さんの「褒めるポイント」は決まっています。
たとえば、先ほどの「ズボンをはく」といった目標では、 「大人が足をとおしてあげて、子どもはズボンをあげるのみ」 の段階では、子どもがズボンをあげた瞬間が褒めるポイントです。
また、 「大人が片足だけとおしてあげて、子どもはもう片方を自分でとおしてズボンをあげる」の段階では、子どもが片足をズボンにとおした瞬間が褒めるポイントです。
褒めるポイントが明確なので、大人側は褒めやすく、お子さんと良好な関係の中で目標に向かった練習を続けることができます。
たくさん褒めて、楽しく穏やかな雰囲気のなか、ステップをのぼっていきましょう!
仮に、事前に考えていたステップが高すぎて、お子さんがうまく登れなったときには、さらに細かいステップに分けてあげる必要があります。
そのステップを考える時に、子どものつまづきポイントが見えやすいので、次の支援につなげやすいこともスモールステップのメリットです。
たとえば、「子どもが片方の足をズボンに入れられない」といった原因をみてみたところ、すでに足が入っている側にもう片方の足も入れようとしていたとします。
その場合には、長ズボンはやめて、パンツや短パンにしてあげると、どっちの穴に足が入っているのかが見て分かりやすいため、うまく行く場合が多いです。
この段階を経て、再度、長ズボンに挑戦するといったスモールステップの再考をしても良いとかと思います。
発達障害児へのスモールステップの支援を行う上での懸念への対処



お子さんと1対1で関われる場面では、スモールステップを行う懸念は少ないかと思います。
懸念が出てくるのは、集団生活の中で、他のお子さんとの兼ね合いを心配される場合が多いのではないでしょうか?
具体的には、以下のようなご相談をよくいただきます。



この子にだけ、特別に簡単なステップを用意すると、他の子と比べて「自分だけ簡単なものになっている」とショックを受けないかしら?



他の子が、この子に用意したスモールステップを見て「ずるい」と言わないだろうか?
自分だけ簡単な内容でショックを受けないか?
子どもたちは、「明らかにできない課題」をやるよりも、「できそうな課題」をやることを好む場合が多いです。
ただし、お子さんにとって明らかに簡単すぎる課題では、モチベーションも上がらず、他の子との違いにショックをうけやすくなるかもしれません。
大切なのは、子どもたちの集団の意識として、「一人ひとりの得意・不得意は様々」「自分で決めた目標に向かって頑張ることはかっこいいこと」といったことを常日頃から伝えていくことだと思います。
しかし、年齢が上がってくると、たしかに他の子と比べて自分だけ簡単な課題は嫌だという場合もあるかと思います。
そういった場合には、いくつか支援方法(スモールステップ)を提示して、本人に選んでもらったらよいと思います。
年齢が上がってきたお子さんには、支援を選ぶ経験をさせてあげることも大切なことかと思います。
他の子が「ずるい」と言わないか?
本記事の冒頭のツイートでも示しましたが、スモールステップに対して子どもたちが「ずるい」ということは案外すくないように思っています。
おそらく、子どもたちは自分にとって簡単すぎる課題ではおもしろさを感じにくいため、用意したスモールステップを使ったとしても数回やって終わりにするのではないでしょうか。
また、どの子にも得意・不得意はありますので、やろうとしている課題でスモールステップを必要としている子が対象のお子さんの他にもいたのであれば、スモールステップを使わせてあげたらよいと思います。
大切なのは、スモールステップを使うか・使わないかではなく、子どもたちが意欲的に、達成感を持ちながら課題に取り組み、その過程の中で自信を育むことのはずです。
「ずるい」という子がいたら、スモールステップを使わせてあげたらいいと思います。
まとめ:積極的に集団生活にもスモールステップを組み込もう!



スモールステップについて、本記事では解説しました。
- 子どもが達成感をもって取り組みやすい
- 子どもを褒めるポイントが明確
- 子どものつまづきポイントが分かりやすく、次の支援につながりやすい
上記のような効果やメリットがスモールステップにはあります。
そして、 子どもたちの集団の意識として、「一人ひとりの得意・不得意は様々」「自分で決めた目標に向かって頑張ることはかっこいいこと」といったことを常日頃から伝えていくことが支援を成功させる上で大切なことだと思います。
時々、スモールステップを使うことが目標になってしまっている方がいますが、 大切なのは、子どもたちが意欲的に、達成感を持ちながら課題に取り組み、その過程の中で自信を育むことのはずです。
スモールステップは、障害がある子にも、障害がない子にも、達成感を与えて自信を育むきっかけを与えてくれるすてきな考え方のひとつだと思います。