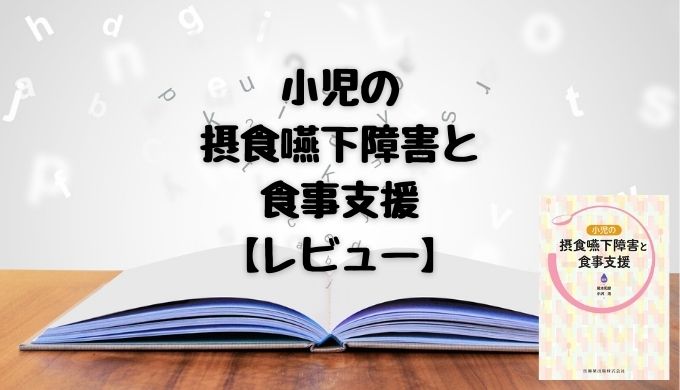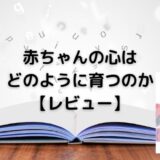「小児の摂食嚥下障害と食事支援」という障害をもつお子さんの摂食嚥下障害とその支援に関する書籍が2019年に医歯薬出版より出版されました。
この書籍は、著者の尾本和彦先生が2005年に出版した「障害児者の摂食・嚥下・呼吸 リハビリテーション その基礎と実践」の内容を、より分かりやすい表現で内容をアップデートした書籍と言えるかと思います。

実は、僕はこの「 障害児者の摂食・嚥下・呼吸 リハビリテーション その基礎と実践」を読みまくってボロボロになってしまったため現在は2冊目を使っています。
執筆されていた先生も一新し、障害児医療・療育の現場で働く医師や言語聴覚士、理学療法士の先生が原稿を書いています。
本記事では、実際に読んだ感想をレビューします。
目次
「小児の摂食嚥下障害と食事支援」レビュー
この書籍は、「基礎編」と「実践編」分かれ、以下のような構成になっています。
基礎編
1 摂食嚥下リハビリテーション概要
2 障害児(者)の医学的背景
3 誤嚥と誤嚥性肺炎
4 気管切開、喉頭気管分離等
5 食べる機能の発達と障害
6 摂食機能の評価と診断
7 姿勢運動と食べる機能の発達
実践編
1 摂食嚥下姿勢の工夫
2 食事支援の実際
3 経管栄養法
4 進行性疾患への対応
5 心理行動的問題への対応
6 症例



さっそく、基礎編と実践編に分けて感想を書いていきます。
基礎編を読んだ感想
2005年に発売された「障害児者の摂食・嚥下・呼吸 リハビリテーション その基礎と実践」に比べると、引用されている文献数が少なく、最新の文献紹介が少ないように感じました。
「障害児者の摂食・嚥下・呼吸 リハビリテーション その基礎と実践」が発売された当初は、小児の摂食嚥下障害に関する書籍がほとんどなく、専門的に詳細まで記載された「専門家向け」の書籍は貴重でした。
そして、 「障害児者の摂食・嚥下・呼吸 リハビリテーション その基礎と実践」 は内容が濃く、小児の摂食嚥下障害を専門とする医師や言語聴覚士でも内容を理解するには何度も読み返す必要があるものでした。
一方で、最近では小児の摂食嚥下障害に関わる人・職種が増えてきました。
小児の摂食嚥下障害に関する書籍も増え、この分野も学びやすい時代になったと思います。
そのため、より分かりやすくポイントを絞った書籍で、専門家だけではなく、さらに幅広い職種に理解を広げるステージ(実際に介護する人たちへの知識の啓蒙)に入ったようにも感じます。
そういった意図もあるのか今回の「小児の摂食嚥下障害と食事支援」では、実際に障害をもった子の摂食嚥下支援を行う職種の人が知っておくべき必須知識に内容がまとまった印象でした。
上記で記載したように、幅広い職種の人に小児の摂食嚥下支援の基礎を知ってほしいといった意図があるのか、医学的背景や誤嚥、気管切開といった医学的な内容が非常に分かりやすくまとめられています。
おそらく、医学的な知識がそれほど多くない介護や保育の現場にいる方にも理解しやすいのではないかと思います。
その一方で、少し突っ込んだ内容の記載もあり、摂食嚥下機能の評価と診断のパートでは、重症心身障害児者の嚥下造影検査(VF)の結果を二次的に解析した著者らの研究が紹介されていました。
重症心身障害児者の口腔機能に関する内容や、咽頭期嚥下でも誤嚥の有無を話題にしたものはこれまで多かったですが、咽頭期嚥下の特徴(なぜ誤嚥するのか?)に迫った記載をしているのは、おそらく本書が初めてではないかと思います。
ここで紹介されている研究を発展させたものが、「Hyoid bone movement during swallowing and mechanism of pharyngeal residue in patients with profound intellectual and multiple disabilities (Nakamura et al., 2021)」として、2021年に海外誌に掲載されていました(本書出版時にはまだ掲載されていなかったようで、書籍には文献は載っていません)。
さらに、理学療法士が姿勢・運動発達と摂食機能の関連を分かりやすく記載されていた部分も興味深く読みました。
やはり、実際に臨床にあたっているリハビリ・スタッフが記載している内容は親近感も湧きますし、納得の内容でした。
実践編を読んだ感想
執筆陣に栄養士さんが入っていなかったということもあるかと思いますが、たとえばペースト食の作り方などの日常的に提供する食事の作り方の解説があるとうれしかったです。
レシピについては、監修者の小沢先生が別の書籍として編集している「おかあさんのレシピから学ぶ 医療的ケア児のミキサー食」が参考になりました。
また、主に発達障害児を対象とした話題になるが、臨床場面で偏食に関する相談も増えてきているため、もう少し話題をふくらませてもらえるとうれしかったです。
偏食に関しては、2019年に中央法規から出版された「発達障害児の偏食改善マニュアル」が参考になりました。
なお、当ブログでも偏食に関する記事を作成していますので、併せてお読みいただけると幸いです。


基本的には2005年出版の「障害児者の摂食・嚥下・呼吸 リハビリテーション その基礎と実践」の内容を踏襲しつつ、著者の実際の臨床経験から得られた指導方法に関する示唆が勉強になりました。
また、これまで言われてきた指導方法に関して、根本的な考え方を変更しようとする想いも感じ取れました。
たとえば、これまで口腔機能の発達は「口唇閉鎖・成人嚥下」「押しつぶし」「咀嚼」の順番を基本としてそれぞれのケースに合わせて指導を行うことが多かったですが、本書では「押しつぶし」の練習に時間を割くことを否定し、「咀嚼」への移行のための練習を行うべきとしています。
たしかに、海外の文献を調べてみても「押しつぶし」に着目した研究はなく、ほとんどが「咀嚼の発達」を話題にしているようでした。
しかし、個人的には「押しつぶし」には咽頭期嚥下のパワーを上げるといった意味合いもあるように思っていますが、ここで議論するのは控えたいと思います。
ぜひ、あなたも本書を手に取って内容を確認してみてください。そして、機会があれば「押しつぶし」の練習の必要性について、議論できればうれしいです。
さらに、近年は子どもの窒息事故などの痛ましいニュースも少なくありません。
障害をもった子どもたちは、摂食嚥下機能の発達が未熟な場合が多いため、窒息事故のリスクもどうしても上がってしまいます。
本書では、万が一の窒息事故に備えて、窒息が起きた時の対応方法を記載していました。
実際に障害をもつ子の食事の介助にあたる人たちには、窒息事故の対応は知っておくべきだと思います。
まとめ:「小児の摂食嚥下障害と食事支援」の書評・感想
本記事では、尾本和彦先生・小沢浩先生の「小児の摂食嚥下障害と食事支援」を読んだ感想を書きました。
この書籍は、子どもの摂食嚥下の発達を支援する立場の方に、ぜひ読んでほしい本だと感じました。
摂食嚥下に関する書籍を初めて読む方にも分かりやすくまとまっていると思います。
長年の間、障害をもつ子どもたちの摂食嚥下の診療をしてきた先生だからこその、非常に臨床的・実践的な内容になっていると思います。
実際に今、障害をもつ子どもたちの摂食嚥下の支援を行っている人にも、日々の臨床を振り返ったり、大切なポイントを整理したりするための書籍として役立つと思います。
また、これまでに言われてきた内容から一歩進んだ内容や今後議論が必要な指導方法まで記載されています。
個人的には、少し攻めた内容の記載もあり、好きな本の一つです。
価格は4,800円+税です。
本当に、買ってよかったと思いますし、読んだその日に内容について同僚と語りたい本でした。