
1年目の言語聴覚士「臨床スキルってどうやって上げたらいいのかな?できるだけ早く力をつけたい。」
こういったテーマで記事を書いてみます。
- 言語聴覚士が臨床スキルを上げる最速の方法=真似
- 誰から真似をするのか?も大切
- 真似を通して「本質」を理解することが重要



この記事を書いている僕は、言語聴覚士として働いて15年ほど。
先日、「どうやって臨床の勉強をしたらいいですか?」と他施設のSTさんから相談がありました。
そこで、今回はこの相談に答えたことや新人教育などで僕が後輩に伝えていることを記事にしてみようかと思います。
ひと昔前までは「自分で考えないとダメ!」なんて意味不明なスパルタ教育も流行っていました。これはひどいですよね。
「真似して」「教えてもらって」少しずつ自分の中に根付かせていく。これが臨床スキルの向上には必須だと思っています。
目次
言語聴覚士が臨床スキルを上げる最速の方法=「真似」です



臨床スキルを上げたいなら「真似」をしましょう。
「真似」が大切な理由
効果的なセラピーを、そのまま取り込むことができるからです。
先輩が年月をかけて学び、鍛えてきた臨床スキル。これをサクッと真似して対象者に提供してみましょう。
「でも、リハビリは個別性が高い。なんでもかんでも真似してやるだけじゃダメでしょ」
こんな声が聞こえてきそうですね。ちなみに、僕もそう思います。
真似をすると自分に足りないものが見えてくる
最初は自分の中に手札がない状態。だから、先輩の真似をするのが最善のセラピーになる場合も多いと思います。
でも、実際に真似してやってみると、先輩のように上手くいかない。なぜか?
※対象者が違えば、提供するセラピーも違う
これは当たり前。でも、先輩のセラピーを見て「この臨床は〇〇さんにも当てはめられそう!」と思って真似したんですよね?
対象者の特性の違いもあるかもですが、以下の理由が多い気がします。
※表面上の手続きだけ真似していないか?
実は、これがすごく大切な視点。使用する教材だけ真似しても何の意味もありません。
例えば、以下のような視点で観察して、真似してみましょう。
- どんな声かけをしていたか?
- 声かけのタイミングは?
- STは何を見ていたか?
など。つまり、コミュニケーションの取り方、関わりのタイミングなどの非言語的な側面まで真似できていないから上手くいかないのかも。
「でも、そんなに完全にコピーできないよ」って思いますよね。
僕も当初はそう思いました。
真似するべきは、少し先を行く人です
いきなり一流のセラピーを真似したらOKという訳でもないです。ポイントは「自分よりも少し先を行く人」だと思います。
一流STのセラピーでは自分に足りない部分が満載。これは当たり前ですね。そのため、真似しきれないという事態に陥りやすくなります。
例えば、以下のような感じが良いかと。
- あなたが1年目→3~5年目くらいの先輩の真似をする
- あなたが5年目→8~10年目くらいの先輩の真似をする
とはいえ、年数が上なら誰でも良いわけではないですよ。自分が信頼・尊敬できる人を選びましょう。
では、ここまで読んでくれた人に質問です。
※「あなたの一歩先の人は誰ですか?」
この答えがパッと思い浮かばないなら、今の働き方を考え直した方が良いかもです。
仮に一人職場で先輩がいないといった事情があったとしても、県士会などでつながりをつくる努力をしてみるべきです。つながりがあるなら、他施設のSTの臨床を見学させてもらえるように、職場長に交渉してみるのも良いと思います。
全部ムリ!って感じなら、そもそも職場を変えた方が自分の成長につながるかもしれないですね。まずは目指すべき人(=追い越す目標)を明確にしましょう。
》転職を考えるなら、まずは転職サイトを選びましょう【選び方&最大活用のコツ】
臨床スキルを上げるために真似する時に、考えるべきこと
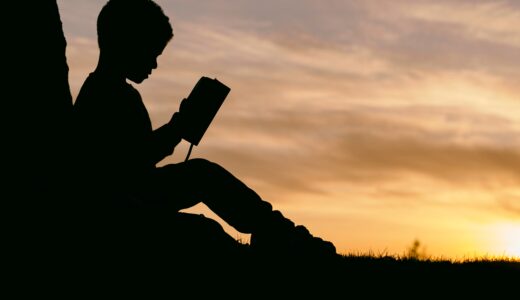
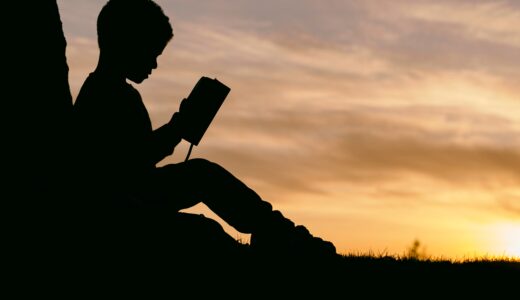
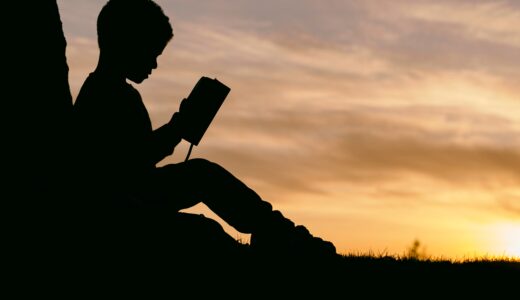
結論、「本質」を理解しよう。
臨床スキルには「本質」が隠れている
繰り返しになりますが、臨床で使っている教材などの表面的な部分に隠されている「本質」を見抜いて、真似するようにしましょう。
- セラピーの目的は何か?
- 大切にしているセラピー感は何か?
- そのセラピーで成功(失敗)したことは?
例えば、こういったことを考えながら見学して、見学後に質問することで答えあわせすると良いと思います。
たぶん、セラピストごとに大切にしている考え方や得意なセラピーがあるかと思うので、ひとまず真似してみて、自分に合わないと思ったら真似する相手を変えてみるのも良いかも。
でも、基本的な「本質」はそんなに変わらないと思います。
「本質」が分かれば、自分でも臨床スキルを高められる
「じゃあ、その本質って何だよ?」って言いたくなりますよね。
ただ、こればかりは抽象度と個別性が高い。
「同じ対象者を複数のセラピストが見たとしても、大体同じようなねらいのセラピーになる部分」があるということかな?と思います。
簡単に言うと、「この人のココは絶対におさえるべき」ってところ。
たぶん、これさえつかめるようになれば、あとは自分流にもセラピーをアレンジできるようになると思うんですよね。
- ステップ①:一歩先の人を真似する
- ステップ②:表面上はそれなりに出来るようになる
- ステップ③:自分のセラピーの目的が明確になる
ただ見学してもあまり意味がなくて、見た内容を真似してみることが大事。そのつもりで見学することで「自分ゴト」になります。
「自分ゴト」になることで、必死に「本質」を知ろうと努力できるわけですね。
真似しても、成長を感じられなかった場合の対処方法
「でもさ、真似しても成長を感じられなかったらどうするのよ?」という疑問が出てきますよね。
※その答え→「大丈夫!」、です。
「見学→真似→考える」これを一通りやってみて、何も得るものがなかったということはないと思います。自分が気づいていないだけ。
仮に、すぐに成果が出ていないように感じても、その経験は脳裏に焼き付いているはず。ふとしたきっかけで役に立つものです。
自信が持てないなら、先輩に自分のセラピーを定期的に見てもらいましょう。
どこが成長したのか、フィードバックをもらえる先輩がいいですね。
まとめ:臨床スキルを真似ながら本質を学ぶ=最速の学習方法



今回は、「言語聴覚士が臨床スキルを上げる最速の方法」をテーマに書いてみました。
ここまでをまとめます。
- まずは臨床を「真似」してみよう
- その中で自分に足りないものを考える
- 「本質」を真似できれば、あとは自分で広げられる
こんな感じ。「最速」ってタイトルだけど、すぐに身につきそうにないな…って思うかもしれませんが、しょうがない。
時間をかけて、ゆっくりと成長するからこそ、自分の中に根付くものだと思います。
逆に、そんなにサクッと身につくなら、誰だって苦労しないですよね。
ただ、自分一人で独学していたのでは、臨床スキルって伸び悩むと思います。
言語聴覚士って個室にこもってセラピーをすることが多いので、先輩のセラピーをチラ見することが難しいんですよね。
ちゃんとお願いして、同席させてもらう。
「いや、自分でも学べるし、他人の真似なんて必要ない」と考える人は、その思考はちょっと危ないと思います。我々は、対象者のために『間違ったセラピー』だけは避けないといけません。
変なプライドは捨てて、成長のために頭を下げて(下げなくてもいいケド)、真似から始めてみましょう。
最初は独自性は必要なし。
自己流の方法でスキルを高めるのは、基礎がしっかり固まった後で遅くありません。
信頼+尊敬できる人に出会えるかが肝
というわけで、今回は終わりにします。
最後に、自身の成長のためには、自分が信頼できて、尊敬できる人に出会えるかどうかが肝だとも感じます。
僕の場合には、幸いにも職場で尊敬できる先輩方に出会えました。
友人は一人職場ですが、県士会でメンターに出会えたようです。
※あなたが尊敬できる人は誰でしょうか?
こういった出会いは積極的に求めた方が、職業人生は楽しくなるかもですね。



