
言語聴覚士として働いている人「臨床のスキルを上げるために、勉強して知識を増やしたいな。やっぱり、しっかり学ぶためにはセミナーとかに参加した方がいいのかな?効率のいい学び方があるなら知りたいな。」
こんな疑問にこたえます。
- 臨床で必要な知識は独学で学べる
- 症例報告をまとめることが最強の勉強方法
- 論文を書いてアウトプットすることで業績となる
- 筆頭著者での学術論文10本以上(内、2本は英論文)
- 全国規模の学術集会でのシンポジスト
- 書籍の分担執筆5冊



僕は15年くらい小児分野の言語聴覚士として働きながら、上記の実績をあげてきました。
国家資格をとるために養成校で学んだ後、就職して数年は外部のセミナーなどにも参加しましたが、5年目以降は基本的には独学で知識を積み上げています。
最近では、大学院に行って学位をとろうかな?と思うことはありますが、日々の勉強のメインはやり独学でいいかなと思っています。
この記事では、僕が実践している独学の方法・マインドをご紹介します。
目次
臨床スキルを上げたいなら、独学したらOK【症例報告をまとめよう】



「何かを学ぶ=学びに行く」と考えがちですよね。僕も最初はそうでした。
独学は効率的に必要な知識を学べる
もちろん、大学院や外部のセミナーなど、お金を払えば学習の機会を得ることはできます。でも、ぶっちゃけ独学でも同様の内容は学べます。
今ではインターネットを利用して世界中の情報が手に入ります。
日本にも良書がたくさんあるので、あなたが学びたい内容の書籍を買えばOKです。変なセミナーで根拠のない情報を叩きこまれるよりよっぽどマシです。
教科書レベルの書籍で調べて、足りない部分は最近の論文にあたってみる、このくらいのことであれば独学でも十分に学べますよね。
教科書で確かな知見を広く→論文で最近の流れを深く
この順番で学べると良いと思います。
体系的に学びたいなら学校もアリ!
とはいえ、大学院などの学校にいって体系的に学ぶのもアリだと思います。
「独学が良いんじゃなかったのかよ!」と怒られそうですが、コスパを考えると独学が良いと僕は思います。
ただ、ここは考え方次第なので、経済的な余裕がある人で、学校で体系的に学びたいという人であれば、『行けばいい』と思うのです。
「受け身の学習」は義務教育まで
「学校にさえ行けば、知識が身についてキャリアアップにつながるぞ!」というのは大きな誤解です。
学校に行ったって、あなたが学ぶ意欲がなかったら何も学べないのは当たり前ですよね。
せっかく大金を払って学びに行くのですから、能動的な学びをするべきです。
そうなると、結局は教科書を読んで、深めるところは論文にあたって・・・といった学び方になるので、独学と大差はないように感じませんか?
あくまで僕の考えですが、下記のとおりです。
まずは独学してみて、どうにも自分だけで学べない壁にぶち当たったら学校を検討
だって、学び方さえ知っていれば、独学でちゃんとした知識が学べてしまうのですから。
ただ、僕も自分一人で独学していたのではこのように思えなかったと思います。
僕の場合には、大学院の博士課程まで修了し、研究者として働いている友人がいました。
その友人から、論文検索の仕方や論文の読み方、まとめ方、研究計画の立案の仕方などを学ぶことができたのが大きかったですね。
ここを学ぶために大学院に行くのであれば、その後の独学がスムーズになるので、マジでオススメです。
僕を含めて、大学院の修士課程って、学部の時のように専門領域の講義を聞いて学ぶかと思っている人も多いかと思います。でも、これだけだったら正直、独学で良いのではないかと思います。
論文を使った学び方、研究のやり方を学べると、それ以降の財産になっていくこと間違いなしです!
こんな本もオススメです。
めっちゃ分厚くてびっくりすると思いますが、中身はかなり読みやすいです。
療法士向けのセミナーはピンキリ
外部のセミナーに関しては、正直ピンキリだと思っています。
貴重な時間やお金を使うのですから、有意義なものに投資したいですよね。
おすすめは、セミナー参加前に、講師の業績を調べておくこと。講師が何者なのかを知った上で、話を聞きに行きましょう。
その点では、一流講師の話がオンラインで時間を選ばずに聞ける『リハノメ』は、あなたが学びたいテーマの動画があるのであれば利用する価値が高いでしょう。
》リハノメを実際に利用した『感想&注意点』
くれぐれもよく分からないセミナーに大金を注ぎ込むのはやめましょうね。
学んだ知識は使わないと定着しない【臨床せよ】



知識ばかり詰めこんでも、知識を使った実践をしないと定着しません。
というか、あなたが臨床家なら、なんのために学んでいるのか分からなくなってしまいます。
臨床スキル=知識×経験
いくら教科書や論文を読んで知識を増やしたとしても、あくまでそれは机上の空論。
僕ら臨床家は、この知識を対象者に還元することで経験を積むことが重要です。
大切なことは、「臨床で使える知識を獲得し、その知識を臨床で使う経験を積み重ねることで、スキルとして定着させていく」ということです。
- 学んだ知識で、リハビリを提供する
- 学んだ知識で、家族に助言する
- 学んだ知識で、新規分野に挑戦する
こういった感じです。当たり前といえば当たり前ですね。
学んだだけの知識は時間とともに忘れてしまうことも多いですが、臨床の経験の中で深められた知識は、あなたの「スキル」となって定着していきます。
新しい分野を学びたいなら就職も良い
たとえば、あなたが成人分野で働いていて、小児分野についても学びたいと考えていたとします。
それなら、小児分野に転職しちゃって、働きながら学んでしまうのが実は効率的。
幸いなことに、小児分野は人材不足なので、未経験でも就職がしやすい状況が続いていますので。
経験を価値あるものにする方法は症例報告
学んだ知識を臨床で使用することで、スキルはUPしていきます。
さらに、あなたが担当した対象者の方を症例報告としてまとめてみましょう。
最初は職場内のケース・スタディなどでも構いません。文章で全体像をまとめるようにしてみてください。
症例報告としてまとめることで、「知識×経験」が症例報告書という形になります。
この『形』を作ることが非常に大切です。
症例報告こそ最強の勉強方法
症例報告書を書いたことがある人なら分かると思いますが、ものすごく勉強になります。
そして、あなたに不足している知識を明確化し、勉強の焦点を定める上でも有用です。
例えば、ひとりの対象者の症例報告書を書く場合に、以下のような項目を把握する必要があります。
- 既往歴
- 生活歴
- 家族歴
- 診断名
- 各種の検査結果
- 行動観察
などなど。まだまだあるかと思います。
これらを総合的に解釈して、全体像としてまとめ上げる必要があるのです。最初はメチャメチャ大変です。
この作業をしている中で、「この診断名ってどんな特徴があるんだっけ?」「家族の中のキーパーソンって誰だっけ?」など疑問が出てくると思います。
少しでも疑問に思うところが出てきたら、そこを深堀りして調査しましょう。症例報告書を書いているようで、実際には、目の前の対象者のことを深く知ろうとしていることに気づけるかと思います。
これをすることで、症例報告書としてまとめた対象者のことはよく把握できるようになりますし、調べた内容は他の対象者の方にも応用できます。
自分の中での疑問点が明確になるので、「何を勉強したらいいの?」という事態も避けられます。
要するに、症例報告をまとめることは、最強の勉強方法だと思うのです。
論文を書いて業績をあげよう
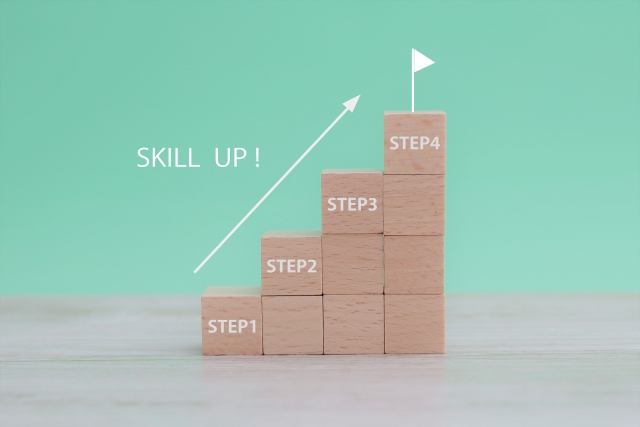
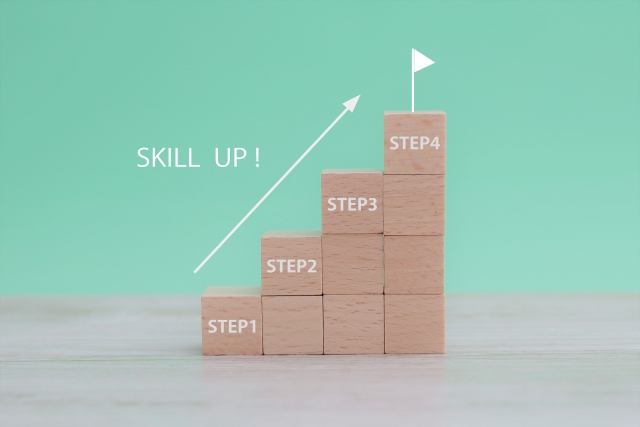
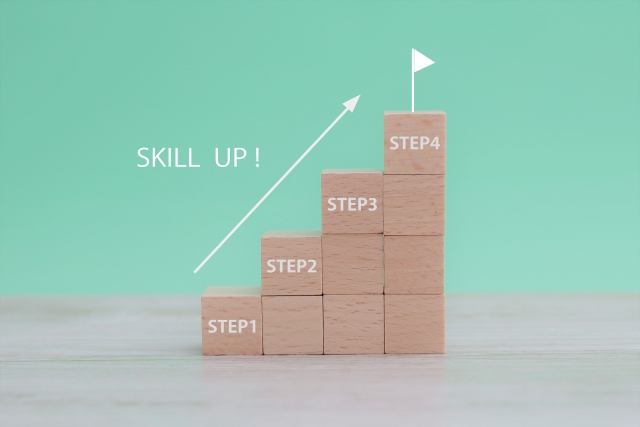
症例報告書が完成したら、論文として学術雑誌に投稿すべきです。
「私が論文なんて、、、無理無理」って思うかもしれないですが、大丈夫です。というか、せっかく必死にまとめた報告書をそのままお蔵入りさせるのはもったいないと思いませんか?
まずは職場の同僚やドクターに症例報告をみてもらって、概ね修正点がなくなったところで投稿に挑戦しましょう!
論文を書く時には、関連論文をたくさん読む必要が出てきます。英語論文はハードル高いな・・・って人は、ぜひ以下の記事もチェックしてください。英語論文でも大丈夫!あなたでも読めますよ。
>>【英語が苦手な療法士:論文の読み方のコツ~ツールを活用セヨ】を読む
論文は査読付きに投稿すべき
投稿するなら、査読付きの学術誌を選択すべきです。ST領域なら、言語聴覚研究、日本摂食嚥下リハビリテーション学会誌、日本コミュニケーション障害学会誌などでしょうか。
査読とは、第三者(その分野に詳しい専門家)が、あなたの論文を読んで掲載に値するかどうかを審査してくれることです。
あなたが論文を投稿すると、査読の先生がコメントをつけて返してくれます。これがまた、良き学びになるのです。
その分野に詳しい第三者の専門家の先生から、あなたの仕事にコメントがもらえるなんて、貴重な機会だと思いませんか?
頂いたコメントに対して返答コメントつけて返信するやりとりを、掲載が許可されるか、拒否されるまで続けることになります。
論文はあなたの名刺代わりになる
査読に耐え、見事に掲載が決まれば、その論文はあなたの名刺代わりになってくれます。
ぜひ、学会などで別刷りを配ったりしてアピールしていきましょう。
臨床現場にいながら、論文を書いている人なんてほとんどいませんから、差別化にもつながりますよ。
僕も論文をきっかけに、セミナー講師や書籍執筆などのチャンスを頂くことができ、仕事の幅が広がりました。
症例報告書に取り組むことは、勉強にもなって、業績につながり、あなたの可能性を広げるきっかけになってくれます。
やるしかないでしょ!?
大学院に行かなくても論文は書ける!



「でもさ。論文なんて大学院に行かないと書けないでしょ」
そう思いますよね。僕もそうでした。
大学の偉い先生の下で論文指導を受けて、初めて書けるものだと思っていました。
もちろん、大学院で論文指導を受けることで、体系的に論文執筆の方法を学べることと思います。
ただ、「大学院に行かないと論文を書けない」というのは間違いです。
実際、僕は大学院に行かずに10本以上、筆頭著者として論文を書いていますから。
でも、できれば論文の書き方については、論文を書いたことのある人に指南を受けた方が良いと思います。
医療系の職場であれば、ドクターや心理士に頼ってみるのも良いと思います。博士課程を出ている人が多いので、基本的には論文指導を受けてきている人たちです。
福祉系の職場で、周りに論文書いたことある人がいないよーって人は、、、大学院に行くか、転職するかした方が早いかもしれないですね。
まとめ:症例報告こそ最強の勉強方法



長くなってしまいましたが、最後までお読みいただきありがとうございました。
ここまでをまとめます。
- 知識は独学で十分に増やしていける
- 臨床スキルは「知識×経験」で高めよう
- 症例報告をまとめることが最強の勉強方法
- 症例報告は論文にして投稿しよう
こんな感じでしょうか。
ただ、将来は大学の教員として働きたいと思っている人は、学位が大切になってくるので大学院を検討した方が良いと思います。
僕のように臨床家として、スキルを高めたいという目的の知識獲得であれば、独学+周囲の人たちの力を借りて、症例報告をまとめていくことが最強の勉強方法だと思うのです。
世の中には、論文作成も業務として認め、応援してくれる職場もあります。
そういったところに身を転じるのも一つの選択肢かもしれないですね。
論文作成に協力的な職場かどうかは、求人の募集要項を見ても分かりません。
このような職場の内部情報については、転職エージェントに相談しちゃうのが一番です。
>>【言語聴覚士におすすめの転職サイト:ベスト3】を確認する
当ブログでは、小児分野の言語聴覚士として働きたい人に向けて、様々な情報を発信しています。
以下のリンクに記事をまとめてありますので、ぜひ、ご覧ください!



