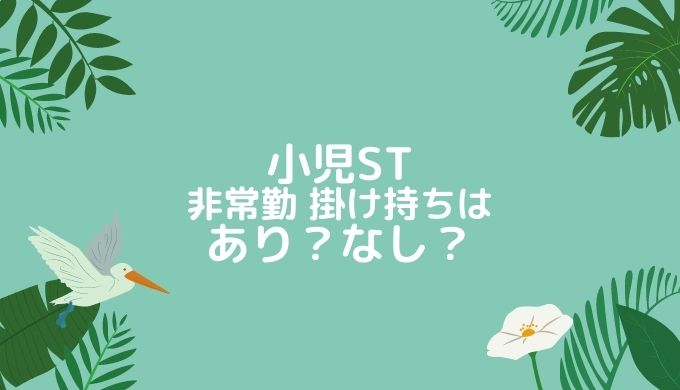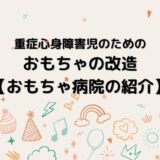小児分野で働きたい言語聴覚士「どうしても小児分野で働きたい。でも、求人が少なくてなかなか常勤採用に行きつけない。なんで小児の求人は少ないんだろう?非常勤の募集ならたくさんあるけど、掛け持ちで働くのはありかな?非常勤の掛け持ちで働く場合に気を付けることがあるなら知りたいな。」
こういった疑問に答えます。



小児分野の言語聴覚士として働きたいと考えたときに、常勤採用の求人情報が少ないことが大きな壁になることが多いと思います。
求人情報をみていると、「非常勤週〇日」といったものなら、小児分野の求人も目につくのではないでしょうか?
1か所の採用では暮らしていけなくても、2~3か所の職場を非常勤で掛け持ちしながら小児分野で働くことはできるのでしょうか。
実際にそのような働き方をしている言語聴覚士もいます。しかし、新卒でそのような道を選ぶ人はほとんどいないようです。なぜでしょうか?
本記事では、小児分野の言語聴覚士が少ない理由や非常勤採用が目立つ理由を考えた上で、小児分野で働く言語聴覚士となるための考え方をお伝えします。
それでは、さっそくお読みください。
目次
なぜ、小児分野の言語聴覚士は少ないのか?



言語聴覚士の有資格者数は2021年時点で36,255名です(日本言語聴覚士協会HPより)。
日本言語聴覚士協会が実施した有職者を対象としたアンケート調査では、言語聴覚士の約3割が小児を対象としていると回答していました。
しかし、実際には成人(中途障害の言語・認知・摂食嚥下)を主な対象とした職場で、小児も割合は少ないものの対象としているといった場所が含まれています。
要するに、小児を専門にみている言語聴覚士はさらに少ないと思われます。
なぜ、小児分野の言語聴覚士は少ないのでしょうか?
小児分野の実習先が少なく、将来のイメージが描きにくい
言語聴覚士を目指す学生と話すと、「小児分野は難しそうなので」といった先入観を持っている場合が多いです。
言語聴覚士の養成校では成人分野も小児分野も同じように学びます。
それなのに、なぜ小児分野は難しいといった先入観をもたれやすいのでしょうか?
まず、小児分野で働く言語聴覚士に出会う機会が少ないといったことがあるかと思います。
小児分野で働く言語聴覚士に出会ったことがないため、自分の将来像がイメージしにくいのではないでしょうか。
学生の多くは臨床実習で現場の言語聴覚士の仕事にふれ、実習をとおして、自分が将来言語聴覚士として働くイメージを明確にもてるようになることも多いのではないかと思います。
しかし、小児分野で働く言語聴覚士は少なく、非常勤採用が多かったり、一人職場であることが多かったりするため、臨床実習を受け入れる余裕がない場合も少なくありません。
要するに、学生は小児分野の臨床実習を受ける機会が限られているため、将来に自分が小児分野で働く具体的なイメージがもてずに「なんだか難しそう・・・」といった先入観だけが先行してしまうのではないでしょうか。
>>小児分野で働く言語聴覚士のイメージをつかむためにはこちらの記事もお読みください。


非常勤での採用が多く給料が低い
小児分野の言語聴覚士としての採用は非常勤が多いため、給料などの待遇面での不安が少なくありません。
そのため、バリバリとフルタイムで働こうとする世代には飛び込みにくい分野です。
結婚して、パートナーの給料で生活が概ねできるようになり、生活費の足しに働くといった場合には良いかもしれませんが、自身の稼ぎで生計を立てなくてはいけないとなると大変です。
そのため、収入の面からも若い世代の言語聴覚士が参入しにくいといった現状があるように思います。
収入に関しては、自分の努力で上げられる側面もありますが、ある程度経験を積んでからでないと難しい場合も多いです。
>>収入UPの方法については、こちらの記事もお読みください。


なぜ、小児分野の言語聴覚士の求人は非常勤の募集が多いのか?



上記のように、小児分野の言語聴覚士の求人は非常勤の募集が多いのはなぜでしょうか?
施設側が経験者を採用したがっている
小児分野の言語聴覚士の求人が出るタイミングとして、すでに働いている人が妊娠・出産などで休みに入る代わりとして「産休代替」として期間限定のパート勤務の募集が出ることが多いです。
そのため、入職後すぐに戦力として働ける人を探している場合が少なくありません。
目的は産休に入る職員の代わりを補いたいということなので、施設側は期間限定での仕事を引き受けてくれる経験者を求めて非常勤での募集をかけるというわけです。
言語聴覚士の認知度が低い
小児の言語聴覚士の認知度は関連職種の間でも高くないのが現状です。
教員を対象としたアンケート調査でさえ、言語聴覚士の存在や専門性を知らないと回答した人が多かったとする結果がでています。
雇用主が言語聴覚士を雇うメリットを感じていない場合には、当然言語聴覚士を採用しようという動きにはなりません。
ただ、実際のところ、お子さんのことばの発達を心配される保護者の方は少ないわけではないため、ニーズは高い領域と思われます。
「ニーズは分かったけど、言語聴覚士が何をするかよく分からない」「なのでとりあえず、非常勤で働いてみてもらおう」と考える雇用主もいるのが現実です。
非常勤を掛け持ちして小児分野の言語聴覚士として働くのはあり?



非常勤を掛け持ちして小児分野の言語聴覚士として働くのはありでしょうか?
結論としては、経済的な余裕があるのであれば非常勤掛け持ちはあり!、新卒で自分の稼ぎで生活しなくてはいけないなら小児を経験できる総合病院などで働きながら小児専門の施設の常勤採用を待つというのが現実的かと思います。
新卒で働く場合、まずは働くことで精いっぱいになってしまうことが多いです。その中で、以下のような確定申告や社会保険の心配を同時に行うことは大変です。
小児専門ではないけれど、仕事の一部で小児をみれる病院(総合病院など)はある程度求人も出てきます。
新卒であれば、あなたが卒業する年に、希望する地域で小児専門の施設の常勤募集が出なかったからといって、その先の人生で小児STになることをあきらめるのはもったいないです。
夢は持ちつつ、将来に希望の職場への転職を視野にいれながら、その時に最善の選択ができると良いと思います。
小児分野の言語聴覚士として非常勤を掛け持ちして働く場合に気を付けること



所得税・住民税
所得税は年収103万円、住民税は年収約100万円(地域により異なる)を超えると支払う必要がでてきます。
所得税・住民税についてはこちらの記事(タウンワーク マガジン)が分かりやすく解説されていました。
確定申告
2か所以上の職場から収入があり、年末調整されていない収入が年間20万円以上ある場合には、確定申告が必要となります。
確定申告については、こちらの記事(クラウド確定申告)が分かりやすく解説されていました。
社会保険
働く日数や時間、収入額によって加入条件は異なりますが、条件に当てはまれば社会保険(職場の健康保険と厚生年金保険)に加入することになります。
加入条件や加入するメリット・デメリットなどについては、こちらの記事(タウンワーク マガジン)が分かりやすく解説されていました。
まとめ:働きながら小児分野の常勤採用をねらおう



「どうしても小児分野で働きたい」という意欲と強い意志がある場合、非常勤を掛け持ちして働くことも個人的にはありだと思っています。
しかし、非常勤では待遇面で不利な場合が多く、収入面での不安はでてくるかもしれません。
また、職場の経営状態によっては、いつまで継続して働けるかも不確実な身分です。
そのため、非常勤として小児分野の経験を積むことはありだと思いますが、将来的に常勤で採用されて働くことをあきらめずに行動し続ける方が良いと思います。
働き始めると、目の前の仕事で精いっぱいになってしまい、将来の自分のこと(就職活動)を行う余裕がなくなってしまうことも少なくありません。
忙しさに負けて、そのままズルズルと非常勤をかけもちして働き続けてしまうのはやめましょう。
将来的に常勤採用を目指したいのであれば、自分のところに小児分野の求人があった場合に情報が集まる仕組みを作っておくことをおすすめします。
そのためには、求人情報がもらえるような小児STのグループに参加したり、転職サイトに登録したりしておくと、働き始めて目の前の仕事で精いっぱいになっている時にも、希望の求人があるかメール等でチェックするだけです。
最近では、リハビリの仕事に特化した求人サイト(例えば、キャリアナビ:大手だから安心!、リハのお仕事:初めての転職ならココ!)も増えてきているので、1~2つくらい登録しておけば希望の求人情報にありつける可能性も上がると思います。
数年前までは、言語聴覚士が小児分野で働くための求人は少なかったのですが、ここ数年で状況は一気に改善してきています。
発達障害などをもつ子どもたちへの療育を手掛ける事業所や企業からの求人も出てきており、むしろ求人・募集はあるけど希望する人がいないといった場所もあります。
以下の転職サイトは無料で登録でき、こうった情報を得ることができますので、今すぐ登録しましょう。
\\ 東京・神奈川の求人に強い //
\\ 関西の求人に強い //
小児分野のSTになりたい!そのための求人が自分に集まるようにしたい!と考える方は以下の記事もお読みください。





転職サイトを使うと求人が集まって便利ということは分かった。だけど、転職サイトって使ったことがないから、登録してからどういう流れで求人情報がもらえるか分からず不安だな。
このような不安を感じる人もいますよね。
こちらの記事では、【リハのお仕事】を例に登録後の流れを解説していますので、お読みください。