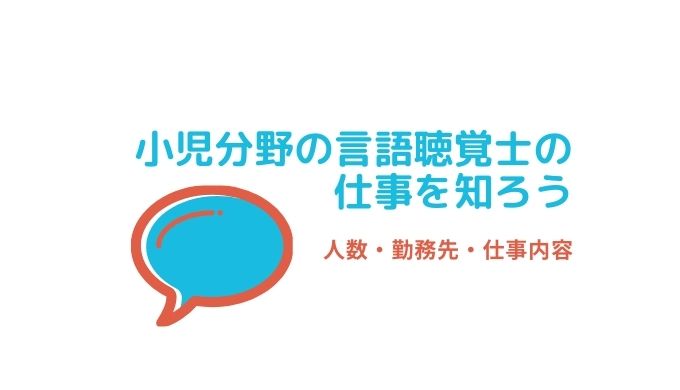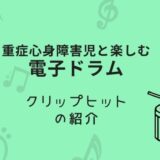就職先に悩んでいる言語聴覚士「小児分野で働く言語聴覚士はどのくらいいるのか?どのようなところで働いているのかを知りたい。また、一日の勤務の流れなども知れると就職先のイメージがつかみやすいかも。」
こういった疑問にこたえます。
本記事では、現役の小児を専門とする言語聴覚士が以下の話題で解説します。
- 小児分野の言語聴覚士の人数
- 小児分野の言語聴覚士が働く場所
- 小児分野の言語聴覚士の一日の勤務の流れ



私は言語聴覚士として15年以上、小児を専門に働いています。本記事では、小児分野での言語聴覚士の仕事内容などを解説していきます。
言語聴覚士の多くは成人を対象とする職場に就職しており、小児分野で働く言語聴覚士はまだまだ多くはありません。
しかし、小児分野で働く言語聴覚士の需要は年々高まってきており、今後さらに活躍の場は広がってくることが予想されます。
現状ではまだ小児分野で働く言語聴覚士は少数派のため、どのような仕事内容なのか?どのような働き方をするのか?こういったことを知る機会が少ないのではないでしょうか。
それでは、さっそくいってみましょう。
最後までお読みいただき、小児分野の言語聴覚士のイメージをつかんでください。
目次
小児分野で働く言語聴覚士の人数



言語聴覚士は、1997年に国家資格となりました。
その年によって多少の変動はありますが、毎年1,500名程度が国家試験に合格して有資格者となっており、有資格者数は2021年時点で36,255名となっています(日本言語聴覚士協会HPより)。
有職者を対象としたアンケート調査(回答数16,206名)によると、7割が医療機関に勤務しており、4,480名が小児の言語・認知を対象としていると回答していました。
この結果からは、言語聴覚士の約3割程度が小児を対象としていると読み取れますが、実際には成人(成人の言語・認知・摂食嚥下)を主な対象とした職場で、小児もみているといった場所が含まれています。
すなわち、小児を専門にみている言語聴覚士はさらに少ないと推測されます。
小児分野の言語聴覚士が働く場所と仕事内容



小児を専門にみる言語聴覚士も医療機関に勤務している場合が多いです。
しかしながら、近年では保健センターやことばの教室などの教育現場、放課後デイサービスを運営する企業などで働く言語聴覚士も増えてきています。
今後、さらに職域は広がっていくのではないかと思います。
小児を専門にしている言語聴覚士ってどこにいるの?と聞かれることがある。
— ゆう@ことばと摂食の発達・療育・リハビリ (@hagukumichild) August 16, 2021
・療育センター
・通園
・病院の小児科や耳鼻科
・児童発達支援
・自治体
などなど。
場所をあげるとそこそこ居そうなのになかなか出会えない。人数が足りていないんだろうな。
そして、僕はTwitterにいる。
総合病院などの小児科
出生時よりなんらかの障害がある場合や、乳幼児健診などで発達の心配を指摘された場合に紹介される場合も多いようです。
そのため、お子さんの発達を評価して、リハビリの必要性などを判断することが求められます。
評価の結果、リハビリ・療育が必要と判断された場合には、地域の療育センターを紹介する場合も多いようです。
そのため、地域資源についての情報を集めておくことやネットワークを構築することが重要になります。
地域によっては、療育センターが近隣にないなど、総合病院が療育の場を担っているところもあるようです。
そういった場合には、総合病院で定期的に言語指導を行うこともあります。
訪問看護ステーション
病院や療育センターに通うことが大変なお子さんを対象とする場合が多いため、重症心身障害児や医療的ケアを必要とするお子さんなどの摂食嚥下に関する支援および前言語期のコミュニケーション支援に関するニーズが高いです。
コミュニケーション支援の中では、ICTを用いた代替コミュニケーション手段を模索したりする場合もあります。
療育センター
知的障害や発達障害をもつお子さんなど、発達に心配を抱えるお子さんを全般的に支援する場所です。
療育センターが地域にある場合には、定期的な指導や療育を全面的に担っている場合が多いです。
そのため、現状では、小児を専門とする言語聴覚士の多くは療育センターに属していることが少なくありません。
療育センターには、理学療法士や作業療法士といったリハビリ関連職種はもちろんのこと、心理士や保育士、栄養士などのお子さんの発達を支える様々な職種が働いています。
また、対象となるお子さんが所属する幼稚園や保育園、通園施設などとの連携も手厚く行っているところが多いです。
保健センター
乳幼児健診の専門フォローとして言語聴覚士が働いている自治体もあるようです。
例えば、3歳時健診でことばの発達を心配されている保護者の話を聞いて、日常の中ですぐに取り組めることをアドバイスしたり、必要に応じて病院や療育センターを紹介したりします。
基本的には保健センターで定期的にことばの指導を行うことは少ないですが、保護者にとってまず最初に出会う専門家となる場合も多いと思われます。
放課後デイサービス(児童発達支援事業)
小学校が終わった後の夕方の時間を過ごす放課後デイサービスで働く言語聴覚士も増えてきています。
放課後デイサービスでの仕事内容は事業所ごとに様々で、保育士さんと同じように集団活動の中に入ってお子さんたちと関わる事業所もあれば、個室が用意されていてお子さんに個別指導を行う事業所もあったりします。
医療機関ではないので、診断や心理検査などの詳細なアセスメントを行う場ではないことがほとんどです。
日々の生活の中からお子さんたちの得手・不得手を把握しながら関わっていくことになります。
現状では、小児分野で働く言語聴覚士の勤務形態は非常勤が多いです。
ただし、上記の療育センターでは常勤採用も多いのが特徴です。
また、近年では放課後デイサービスでも常勤採用が増えてきました。
>>勤務形態についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事もお読みください。
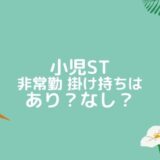
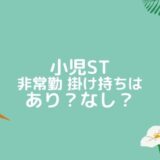
療育センターで働く言語聴覚士の一日(例)



療育センターには、重症心身障害児者の入所施設や通所施設が併設されている場合も多いです。そういった療育センターで働く言語聴覚士の一日を紹介します。
9:00~ 勤務開始
~9:20 朝礼・ミーティング
9:20~12:00 外来の利用児への個別指導
12:00~13:00 入所の利用者への摂食嚥下指導
13:00~14:00 昼食・休憩
14:00~15:00 ケース・カンファレンス
15:00~16:00 外来の利用児への個別指導
16:00~17:00 外来の利用児への集団指導
17:00~17:30 記録(カルテ)記載
17:30 退勤
言語聴覚士は日勤で働く場合はほとんどです。外来で通う利用児への個別指導は1回2~3単位(40~60分)、1日の平均単位数としては、15~18単位(5~6名の指導)である場合が多いと思います。
小児に限った話ではありませんが、言語聴覚士は摂食嚥下の指導を行う関係で、昼食の時間が他のスタッフとずれる場合が多いです。
外来指導がメインの職場であれば、利用児の体調不良などでキャンセルが出るとその分の枠が空くので、そこで報告書やカルテをまとめて記載するような働き方になると思います。
職場にもよりますが、知能検査や発達検査、認知検査などを言語聴覚士が実施するところも多いです。検査実施後は、採点・解釈・報告書の作成が必要になります。
小児分野で働く言語聴覚士はとてもやりがいのある魅力的な仕事だと思います。やりがいや魅力については以下の記事で語っていますので、もしよろしければご覧ください。


まとめ:小児分野で働く言語聴覚士はまだまだ少ない



療育センターではどこも新規利用者が初診を受けられるまでの待機期間が数か月と長くなっているところが多いです。
言語聴覚士による支援を受けたいと思っても、なかなかつながれずに困っている保護者の方も少なくありません。
今後、小児分野の言語聴覚士の需要はますます高まることが予想されます。
まだ働いている人が少ない分野なので働き方のイメージがつきにくいかもしれませんが、本記事がそのイメージづくりの助けになれれば幸いです。
もし、小児分野の言語聴覚士として働くことに興味のある方は、以下の記事もお読みください。
ぜひ、一緒にお子さんたちの成長・発達を支えていきましょう!
>>【小児STになりたい!】小児の言語聴覚士の求人・転職の情報を得る方法に関する記事はこちら


当ブログでは、小児分野の言語聴覚士として働きたい人に向けて、様々な情報を発信しています。
以下のリンクに記事をまとめてありますので、ぜひ、ご覧ください!