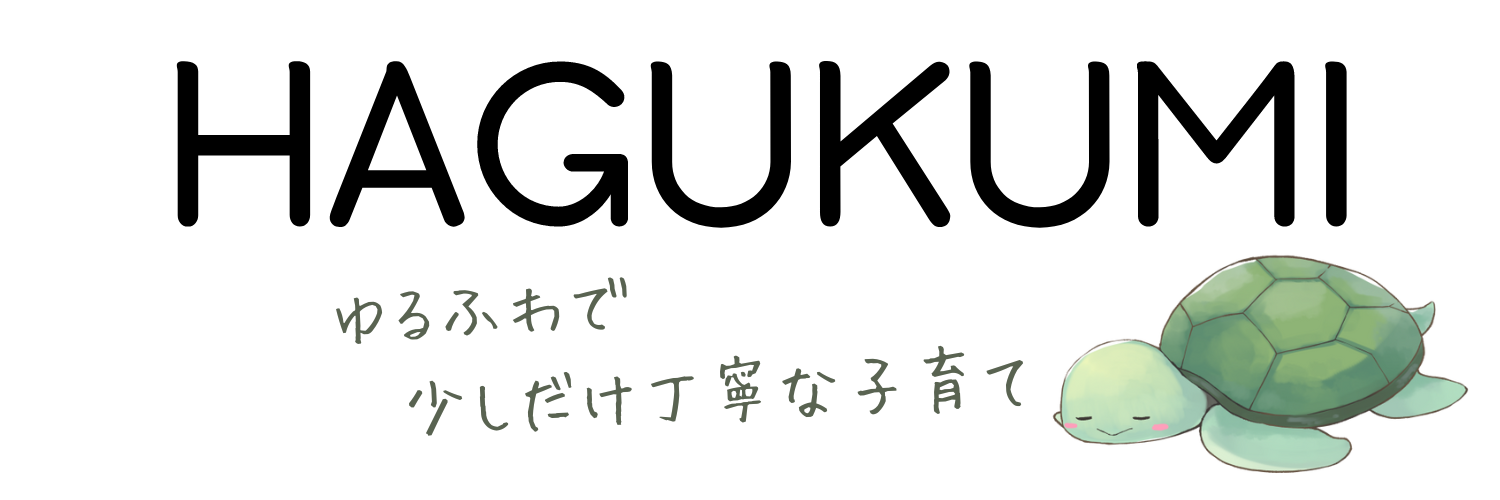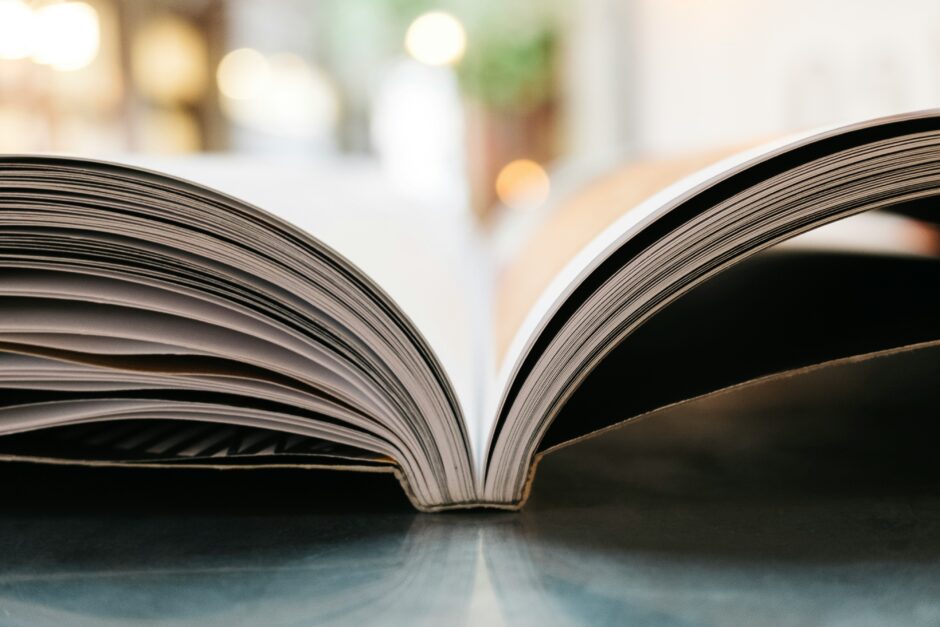「うちの子、なかなか言葉が出ない…」
「どうやって言葉を教えたらいいの?」
子どもの発達、特に「ことば」に関する悩みに関する相談は多いです。
ことばがゆっくりな子を育てる親御さんであれば、不安や焦りから、つい「リンゴは?」「ワンワンは?」と、必死に「単語」を教え込もうとしてしまうこともあるかもしれません。
しかし、そんな時こそ、一度立ち止まって手に取ってほしい一冊があります。
それが、『ことばをはぐくむ 発達に遅れのある子の親と支援者のために』です。
この本は、1993年の初版から読み継がれているロングセラー。
なぜ今、改めてこの本を強くおすすめしたいのか?
それは、この本が「ことばの訓練(トレーニング)」の本ではなく、ことばが育つための「土壌」の作り方を教えてくれる、根本的かつ温かい導きに満ちているからです。
目次
1. この本は「ことばの教え方」の本ではない
この本では「どうやって単語を言わせるか」といったテクニック論をほとんど扱っていません。
でも、これが大事。
私たちが「ことば」と聞くと、つい「単語」や「発音」に目が行きがちです。 しかし、著者の中川先生は一貫して、「ことば」以前の「コミュニケーションの土台」がいかに重要かを説いています。
- 子どもが何に興味を持っているか
- その「楽しい」「好き」という気持ちを、親と共有できているか
- 視線を交わし、思いが通じ合う瞬間がどれだけあるか
ことばは、とにかくインプットすれば育つものではありません。「伝えたい!」という意欲、「伝わった!」という喜び。そのやり取りの積み重ねという豊かな土壌があってこそ、芽を出すものなのだと、この本では優しく、しかし力強く教えてくれます。
2. 「訓練」ではなく「はぐくむ」という視点
タイトルにもある「はぐくむ(育む)」という言葉が、本書のすべてを象徴しています。
焦るあまり、子どもの口元をじっと見て「ほら、言ってごらん!」と促してしまうのは、「訓練」。それは時に、子どもを追い詰め、話すことへのプレッシャーを与えてしまうかもしれません。
そうではなく、まずは子どもと同じものを見て、同じように感じ、一緒に楽しむこと。 子どもが指をさしたら、「あ、ネコさんだね」と、その気持ちを「ことば」という形で代弁してあげること。
本書を読んでいると、「教えなければ」という親や支援者の肩の力がふっと抜け、「ああ、まずはこの子と心から楽しむことから始めよう」と、原点に立ち返らせてくれます。
3. こんな人に読んでほしい「必読書」
この本は、特定の人だけのものではありません。
- 子どもの言葉の遅れに悩み、焦りを感じている親御さん
- 「何をしたら良いかわからない」という不安が、「何をしなくて良いか」「何を大切にすべきか」という安心に変わります。
- 言語聴覚士(ST)を目指す学生さん、新人の支援者さん
- テクニックに走る前に、なぜコミュニケーション支援が必要なのか、その「核」となる部分を学ぶための「バイブル」となります。
- 保育士さん、療育関係者の方々
- 日々の関わりの中で、子どもたちの「伝えたい気持ち」をどう引き出し、支えていくかの具体的なヒントに満ちています。
まとめ:すべての悩める「育て手」のそばに
『ことばをはぐくむ』は、即効性のあるドリルではありません。しかし、何度立ち返っても新しい発見があり、自分の関わり方を見つめ直させてくれる「お守り」のような本です。
もしあなたが今、子どものことばの発達で道に迷い、暗いトンネルの中にいるように感じているなら、この本は必ず、足元を照らす温かい光となってくれるはずです。
「訓練」から「共感」へ。
ことばを「教える」のではなく、ことばが「育つ」のを待つ。
その本質的な喜びと関わり方を、ぜひ本書から学んでみてください。手元に置いて、何度も読み返したくなる、心からおすすめできる一冊です。