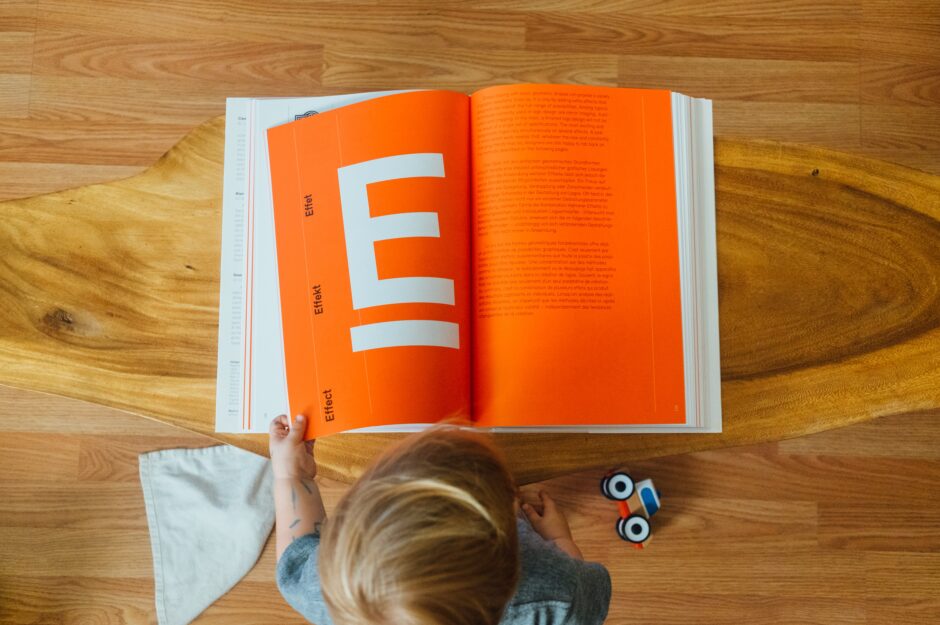保育士「クラスに言葉の発達がゆっくりな子がいる。どんな関わり方をしてあげたら良いのかな?言葉を育てる方法があるなら知りたいな」
こんな悩みをテーマに記事を書いてみようと思います。
- 言葉の発達を育む保育士の関わりとは?
- 言葉の発達の順序【保育の中で確認】
- 【具体例】保育士が言葉の発達を育む関わり
言葉の発達がゆっくりなお子さんへの関わり方って難しいと思います。
どうやったら伝わるのか?どうしたら話せるようになるのか?
関わり方に自信が持てないと、不安につながってしまうことも……。
できれば、自信をもって子どもたちに関わりたいですよね。
そんな中、少し残念なお知らせですが、この記事では言葉の発達を育てるハウツー的な関わりの紹介はありません。
なぜなら、子どもは日々成長しますし、一人ひとり発達の状態が異なります。
そのため、ハウツーでは対処しきれないのです。
では、どうしたらいいのか?
その答えは「発達に関する正しい知識を身につける」だと思います。
目次
言葉の発達を育む保育士の関わりとは?



結論、言葉の発達を育むためには「子どもの発達の状態に合わせた関わり」を地道に続けることが大切。
その中で、ちょっと背伸びをすれば届くくらいの難易度を設定できると良いと思います。
子どもの発達に関わりを合わせることが大切
子どもの発達に合わせた関わりをするためには、以下の2点が大切です。
- 子どもの発達の状態を適切に把握する
- それぞれの発達段階で重要な関わりを理解する
これらを実践するためには、『発達』に関する知識を保育者が身につけることが必要。
ちょっと背伸びをすれば届くくらいがちょうどいい
子どもたちは小さな成長を積み重ねながら発達していきます。
次の発達段階への成長を考えるときには、今できていることから少しだけ背伸びをすれば届くような目標を立ててあげましょう。
このステップが大きすぎるとうまくいかない場合が多いです。
発達については、出来るだけ細かく、小さなステップに分解して理解することが求められます。
言葉の発達の順序【保育の中で確認】



まず、言葉の発達の順序について、保育の中で確認しやすいマイルストーンを理解しましょう。以下は言葉で話せるようになっていくまでの順序です。
- 喃語
- 単語(1語文)
- 2語文
- 3語文
- 複文
- ストーリー
大切なのは年齢よりも順番
発達を学ぶときに、単語は1歳~1歳半頃、2語文は1歳半~2歳、…というように、発達のマイルストーンと獲得年齢をペアにして覚えたのではないでしょうか?
もちろん、獲得すべき年齢も大切。
でも、実際の保育の中で子どもたちとの関わりを考える上では『年齢よりも順番』が重要です。
そして、順番をできるだけ細分化して理解することで、保育の実践で活かせる知識となります。
今できていることを広げることも重要
「今できていることが広がる」ことで、次の発達段階に進めます。
例えば、単語で話せるようなったばかりの頃は「名詞」が中心。
2語文につなげるためには「動詞」などの他の品詞が使えるようになることが必要です。
》2語文の発達に大切なこと | 言葉を育てる2つのポイント
他にも、話し始めたばかりの頃は発音が未熟でも、「音を認識する力」「口を器用に動かす力」が育つことで少しずつ発音が明瞭になっていきます。
》【発音の育ち方】時期別の関わり方:言葉の発達に合わせた声かけが大切
このように、それぞれの段階で、どのように発達が広がるのかを丁寧に理解していくことが大切だと思います。
【具体例】保育士が言葉の発達を育む関わり



少し説明が抽象的だったので、ここでは具体例を示しながら、言葉の発達を育む関わりを紹介します。
- ケース①:単語で話せるようになった子
- ケース②:発音が未熟な子
- ケース③:ひらがながなかなか読めない子
ケース①:単語で話せるようになった子
単語で話せるようになった子が次に目指すのは2語文になります。
そのために、言える単語を広げていくことが必要です。
具体的には、「名詞」に加えて「動詞」「形容詞」が加わることで、「ブーブ、行った」「おっきい、わんわん」などの2語文につながりやすくなりますよね。
「動詞」を広げるためには、子どもがやっている動作を「その場で」言葉にして聞かせてあげるのが効率的。
例えば、子どもが手を洗っていたら「ゴシゴシ」、ボール投げていたら「ポン」など。最初は擬音語・擬態語をたくさん使いながら関わってあげましょう。
「形容詞」を広げる関わりについても同様。子どもが感じていそうな気持ちをその都度、言葉にして聞かせてあげると良いと思います。
ケース②:発音が未熟な子
発音を育てるためには、以下の2つのポイントが重要。
- 音を正確に認識する力
- 口を器用に動かす力
発音は口の中で舌を動かして音を作ります。
音によって獲得される時期が異なり、マ行・バ行などのくちびるで作る音が先、舌で作る音の中でもタ行・カ行は比較的簡単で、サ行・ラ行は後半に獲得されるという特徴があります。
「音の認識」については、擬音語・擬態語が初期の音の認識には重要。その後、じゃんけんグリコのような単語を1音ずつに区切ったり、しりとりのように単語の中の一部の音に注目したりしながら、音の認識が高まっていきます。
ケース③:ひらがながなかなか読めない子
保育園の年長児クラスになると、ひらがなが読めるようになる子が増えてきます。
ひらがなの読みについては、以下の発達が重要です。
- 音の認識
- デコーディング
- 視覚認知
- 語彙力
それぞれの発達については、以下の記事で詳しく解説しています。
》【ひらがなが読めない?】音読の習得に必要な4つのポイント:土台となる力を固めよう
【厳選】保育士が言葉の発達について学ぶ方法
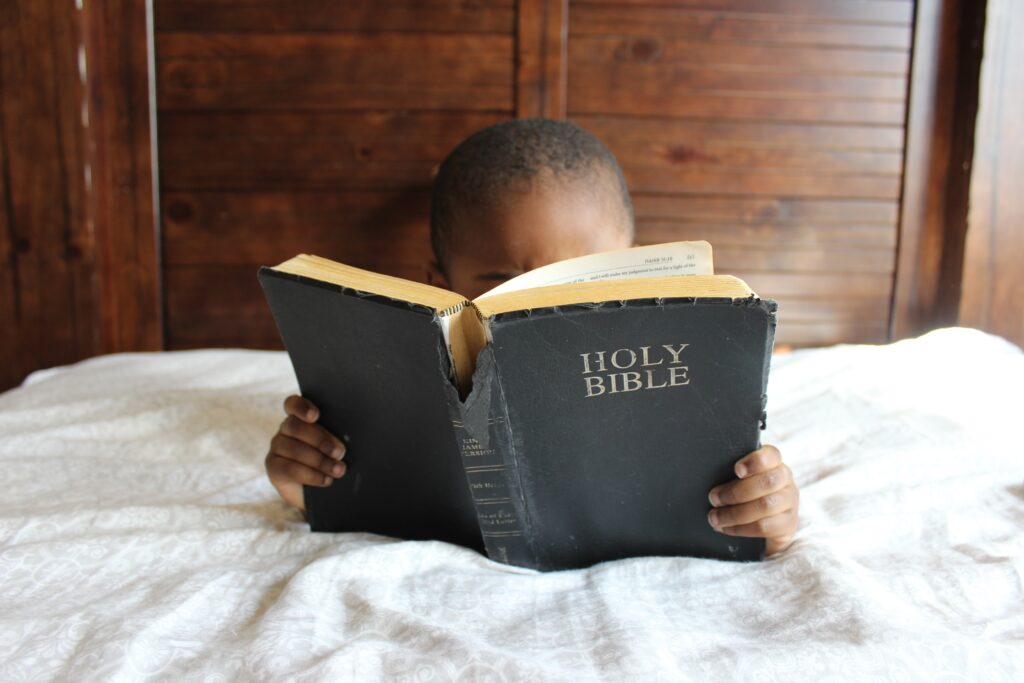
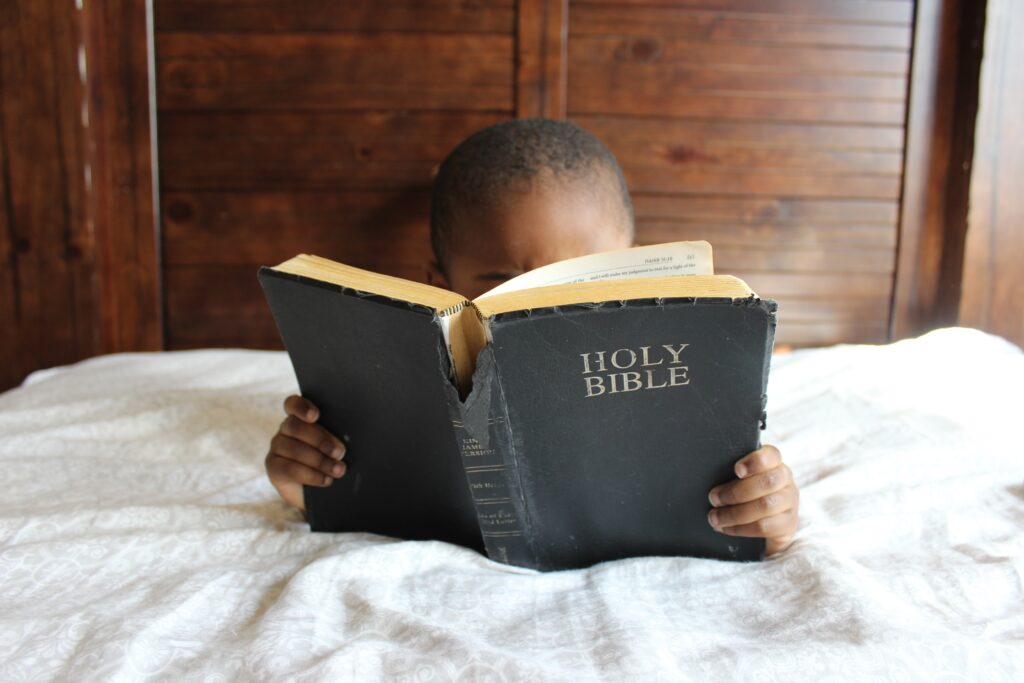
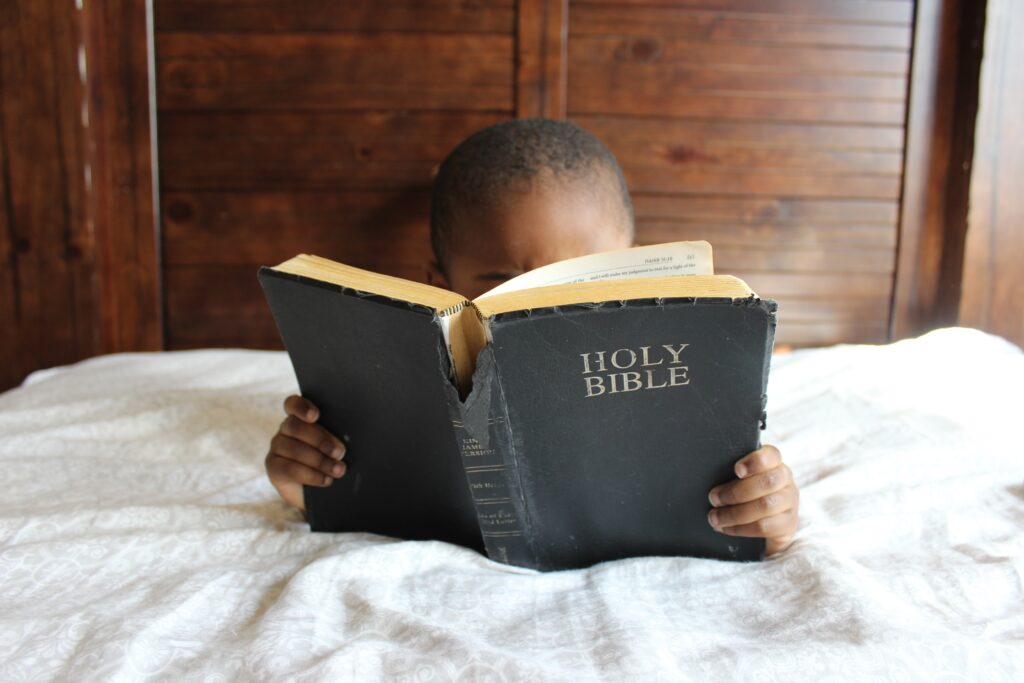
言葉の発達について、分かりやすく解説されている書籍を紹介します。
発達を学ぶのにオススメの書籍
子どもの発達を支援する人は絶対に読むべき本だと思っています。言葉だけではなく、運動や社会性などを赤ちゃんの頃から順に解説してくれています。
関わり方を学ぶのにオススメの書籍
いずれも言語聴覚士の先生が分かりやすく解説してくれています。
言葉の発達を解説したサイト
当ブログでは、言葉の発達について無料で解説しています。ぜひ、お読みください。
働きながら学ぶのもひとつの方法
言葉の発達がゆっくりな子への関わりのような療育的な対応については、療育の現場で働きながら学ぶのも良いと思います。
転職サイトは一度登録してしまえば、後は連絡を待ちつつ、希望の求人に応募するだけです。
以下のサイトへの登録は5分もかからずにできますので、この機会に最初の行動を始めてみましょう。
まとめ:発達を理解して保育の中で言葉を育てよう
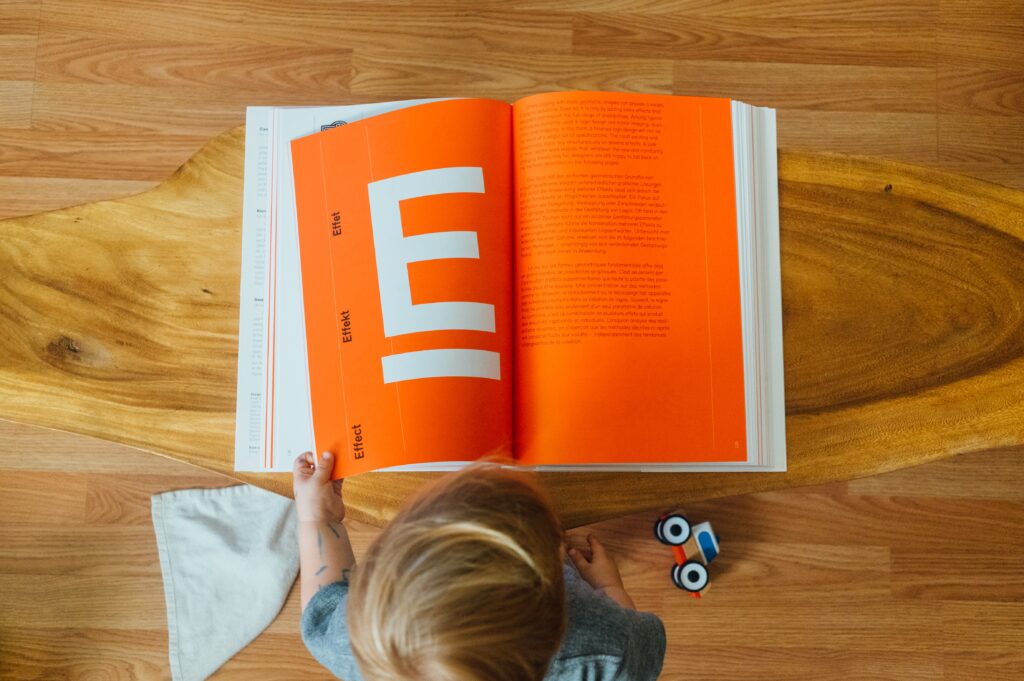
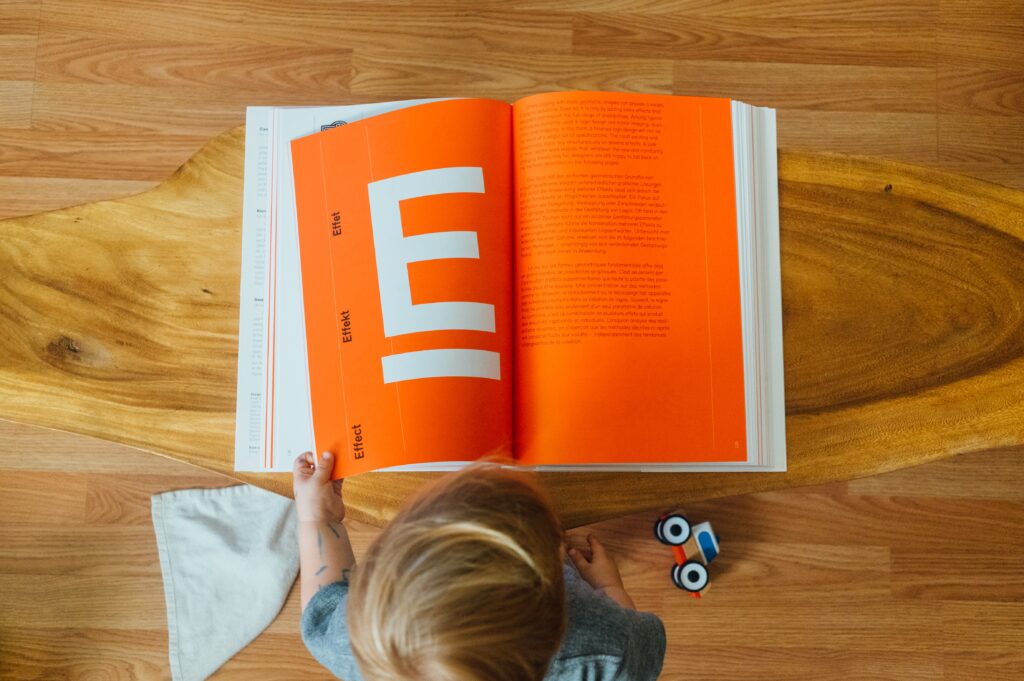
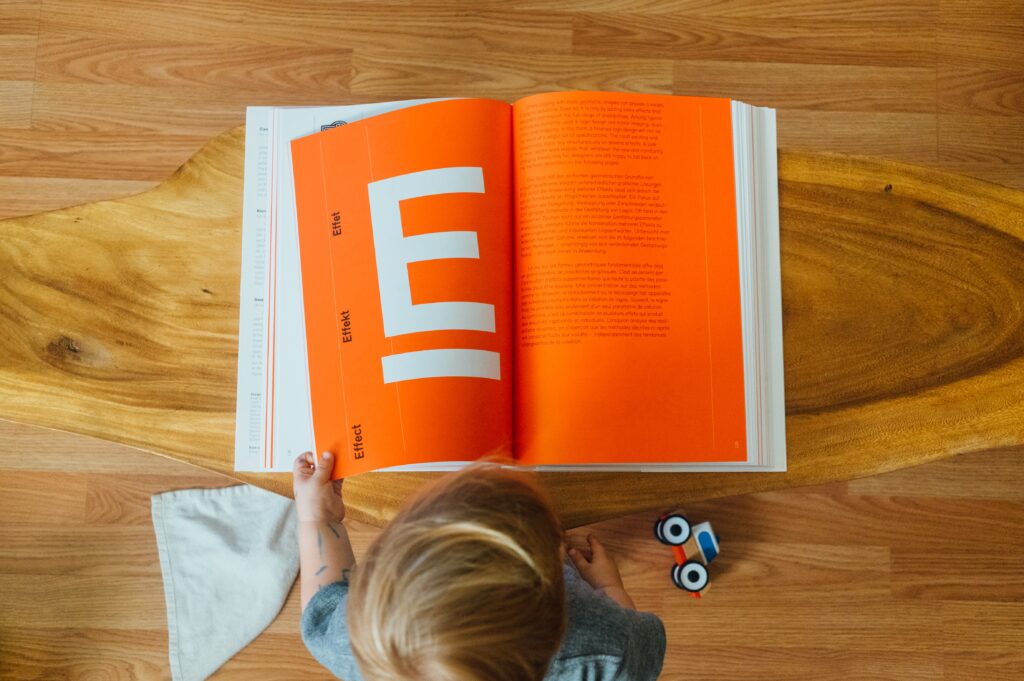
この記事では「保育士が子どもの言葉の発達を育むときに大切にしてほしいこと」を解説しました。
ここまでをまとめます。
- 子どもの発達に関わり方を合わせることが大切
- マイルストーンは年齢より順番が大切
- 発達は細分化して理解すると支援につなげやすい
こんな感じです。
結局のところ、子どもの発達に関する知識を丁寧に積み上げていくことが大切ということですね。
子どもは十人十色なので、ハウツーじゃ対応できないわけですよ。発達を理解すれば、子どもに合わせた対応ができるようになると信じています。
この記事では、言葉の発達を学べる書籍も紹介しました。最近では、専門的な内容を分かりやすく解説する本も増えきていると思います。
より専門的に学びたいって人は療育施設で働きながら学ぶのも一つの方法かもしれません。
以下の記事では、保育士が「気になる子」への関わりを学ぶ時に、療育の現場で学ぶメリットを紹介しています。続いてお読みください。
》【結論】保育士が気になる子への関わり方を学ぶなら、療育施設への就職が良いという話