
保育士「クラスの中で、先の見通しが立たないとパニックになりやすい子がいる。どうやって伝えたら見通しが立つんだろう?」
こういった疑問をテーマに記事を書いてみようと思います。
- 保育の中で見通しを伝えると、落ち着ける場合がある
- 保育の中での見通しの伝え方【3パターン】
- 見通しを立てやすくする環境設定のコツ
場面の切り替えがうまくいかなくて、泣いたり怒ったりしてしまうお子さん、経験ありませんか?
こういった子どもたちが、うまく気持ちを切り替えて保育活動にのってくれたらいいなと思いますよね。
切り替えの苦手さをもつ子の中には、先の見通しを理解することが苦手な子がいるかもしれません。
見通しを伝える意義は?どうやって伝えると伝わりやすいのか?
こういったテーマで解説していきます。
目次
保育の中で見通しを伝えると、落ち着ける場合がある



結論、子どもたちにとって、日々の生活の中で『見通しが立っていること』はとても重要。
見通しが立っている状態→安心感
これが理由です。
未来に何が待っているのか、これが分からないと不安になる。
見通しが立っていない状態とは、この先に何が行われるのかが分からない状態です。
たとえば、大人でも初めて行った場所で、そこで何が行われるか分からないまま、何かの活動が始まったら不安になりませんか?
時々、そんなドキドキ感が最高!って人がいますが、多くはないですよね。
少なくとも僕は不安になります。
このような子たちは、以下のような気持ちなのかも。
- これが終わったら、何か嫌なことが始まるかも
- この遊びは今が終わったら一生できないかも
- 楽しかったこの場所は、もう来れないのかも
極端かもしれませんが、こういった不安を取り除いてあげる必要があるのです。
落ち着いて行動するためには、不安を取り除く必要がある。
なにか不安を抱えている時に、落ち着いて、平常心で行動することは難しいですよね。僕ら大人だって大変。
子どもたちに「落ち着いて行動してほしい」と願うなら、何か不安を抱えていないか?といった視点から見てあげることも大切だと思います。
その不安のひとつに『見通しの立ちにくさ』がある場合も、意外と少なくありません。
保育の中での見通しの伝え方【3パターン】



それでは、保育の中で子どもたちに見通しを伝えるにはどうしたら良いでしょうか?
- 具体物を使った伝え方
- イラストや写真を使った伝え方
- 言葉(口頭)での伝え方
今回は、この3パターンを紹介していきます。
伝え方①:具体物を使用して伝える
まず、試して頂きたいのが「具体物」を使って伝える方法です。
イラストや言葉の理解がまだ未熟な子に伝わりやすいと思います。
例えば、次の活動がお絵かきなら『クレヨン』を見せながら次の行動に誘ってみましょう。
この段階では、ひとつ先の行動を伝えるくらいで十分です。
伝え方②:イラストや写真を使用して伝える
具体物で見通しをもてるようになった子には、イラストや写真でも見通しが立てられるように支援していきましょう。
その理由は、イラストや写真でも理解できるようになった方が、より多くの情報を伝えられるからです。
例えば、写真であれば、ホワイトボードに2~3枚並べて貼ってあげることで、2~3つ先の予定を示すこともできます。学校の時間割みたいなイメージですね。
イラストや写真が良いのは、言葉と違って一度提示した後は、何度でも見返すことができる点。見やすい位置に提示してあげましょう。
伝え方③:言葉(口頭)で伝える
言葉で伝えることで理解できることが増えることも大切です。
なぜなら、言葉で理解できれば具体物や写真などの道具が必要ないので、いつでも、どこでも伝えてあげることができるからです。
とはいえ、子どもたちの中には、視覚情報として伝えてもらった方が理解しやすい子がいます。
その場合には、言葉で伝えることに固執せず、子どもが理解しやすい方法での伝え方を優先してあげてください。
見通しが立たない→不安
不安を感じながらの生活はできるだけ避けてあげるべきだと思います。
》言葉の発達を育む保育士の関わりとは?【成長に合わせた声かけが大切】
保育の中で見通しを立てやすくする環境設定のコツ
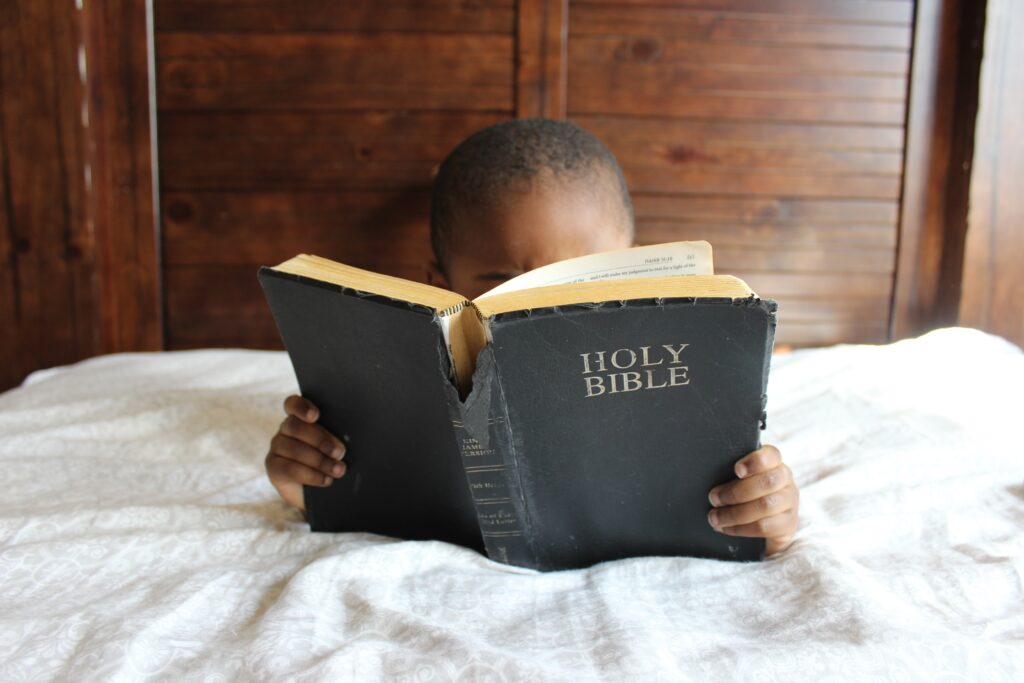
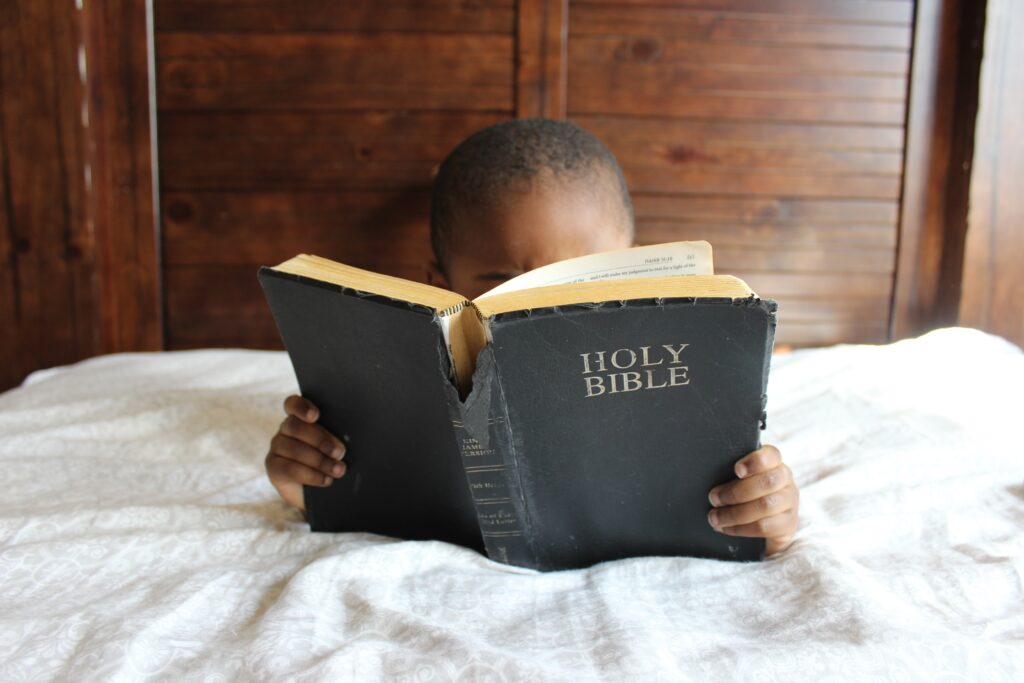
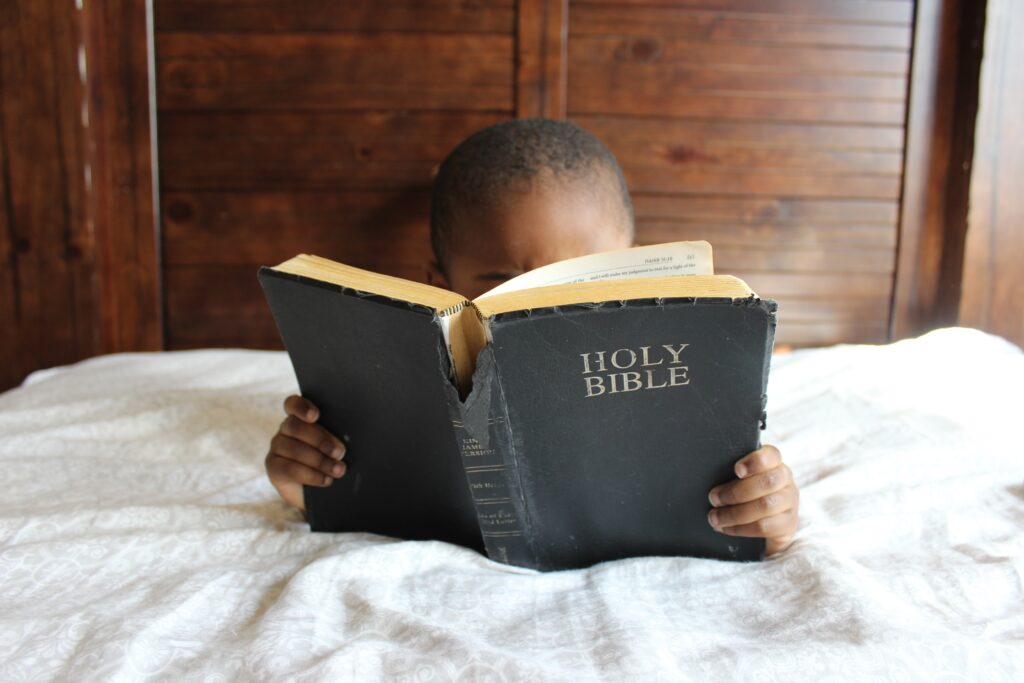
子どもたちが生活の中で見通しを立てやすくするには、上記のような伝え方に加えて、環境設定を工夫してあげることも大切です。
- ルーティーンが見通しを育てる
- シンプルな環境は状況理解を助ける
順番に解説しますね。
ルーティーンが見通しを育てる
毎日繰り返されている流れの中であれば、特に何も伝えなくても見通しをもって行動できる場合があります。
例えば、登園→朝の挨拶→絵本→遊び→…、といったように、活動の流れをある程度一定にしてあげるのも良いでしょう。
時々、「流れを固定しすぎると、柔軟性が育たないのでは?」といった意見もありますが、僕は違うと思っています。
賛否両論あるかもですが、『見通しをもって行動できた経験』をまずはしっかりと積み上げることが大切。その上で、少しずつ柔軟性を育てていけば良いと思っています。
要するに、最初はガッチリと見通しへの支援をしてあげて、成功体験を積ませることを重視するということです。
シンプルな環境は状況理解を助ける
見通しを持ちにくい子たちの中には、周囲の雑多な情報の中から、自分がおかれている状況を適切に理解できていない子がいます。
与えられている情報量が多すぎて、必要な情報をキャッチできていないわけですね。
なので、しっかりと与えられている情報に注目を向けられるように、シンプルな環境を用意してあげましょう。
棚やおもちゃ箱に布をかけるなど、不要なものが見えなくするだけでも刺激量が減ります。
まとめ:保育の中で見通しが伝えることができているか?



『保育の中で見通しを伝えることで、子どもたちが落ち着けることもある』といったテーマで記事を書いてみました。
というわけで、ここまでをまとめます。
- 見通しが立たない→不安につながる
- 不安を取り除かないと落ち着けない
- 伝え方は子どもの発達に合わせた方法で
こんな感じです。
見通しの立ちにくい子は、場面の切り替えがうまく行かなかったりするので、保育中の対応に苦慮することも多いのでは?
でも、困っているのは子どもたちも一緒。
子どもが何に困っていて、どう支援してあげたら良いのか。この記事が、子どもの困り感を考えるきっかけになれたら嬉しいです。
こういった保育のコツに関しては、障害をもつ子の療育の中からヒントを学ぶことができます。
なぜなら、療育的な関わりでは、障害をもつ子にもちゃんと伝わるような丁寧な関わりを得意としているから。
もっと療育的な関わりから保育へのヒントを得たい!という人は、以下の記事もお読みください。
》【結論】保育士が気になる子への関わり方を学ぶなら、療育施設への就職が良いという話



