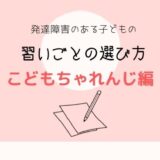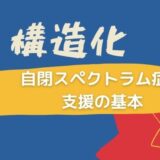ダウン症をもつお子さんの母親「ダウン症の子ってメガネをかけている子が多いわよね。視力が弱くなりやすいのかしら?視力についてはメガネを調整するくらいしかやれることはないのかな?見る力を育てるための遊びなどがあるなら知りたい。」
こういった疑問にこたえます。



私は、言語聴覚士(ST)という資格で、ダウン症をもつお子さんたちのことばの指導・支援を担当しています。見る力はことばの発達にも重要なので、ことばの指導の中でも以下に紹介するような遊びを取り入れています。
本記事では、「見る力」を3つ分けて考えます。
- ①視力:小さいものや遠くのものを見る力
- ②視機能:スムーズな目の動き
- ③視覚認知:見た情報を理解する力
それでは、さっそく始めましょう。
最後まで読んでいただき、お子さんの見る力を育てるためにどのような視点が必要なのかを理解しましょう。
目次
視力:小さいものや遠くのものを見る力
視力とは?
視力とは、どれだけ小さいもの・遠くのものを見る能力のことです。
一般的に、ランドルト環というアルファベットの「C」のような形の切れている部分を報告することで視力を測定します。
しかし、ダウン症のお子さんでは発達がゆっくりであることから、検査の取り組み方がうまく伝わらないこともあります。
障害をもつ子を多く受け入れている大学病院の眼科などでは、ドットやイラストなどランドルト環以外の視力検査も実施できる場合があるので相談してみましょう。
ダウン症のお子さんでは、近視より遠視の割合が多く、乱視も通常よりも多い割合でみられます(Akinci et al., 2009)。
そのため、多くの割合で眼鏡が必要となります。白内障などの異常がみられることも少なくないため、定期的に目の検査を眼科で受けることがおすすめです。
子どもの場合、小学校にあがるくらいまでは視力も成長とともに成長します。異常がある場合にはできるだけ早く発見して、視力矯正を行うことが望ましいといわれています。
眼鏡で視力を補う
眼鏡については、できれば眼科の先生や子どもの眼鏡作りに慣れた販売店と相談しながらお子さんにあったフレームを選びましょう。
ダウン症のお子さんは鼻が小さく低いことが多いので、鼻パットを工夫してもらうとずれおちくなるようです。
また、眼鏡を導入する頃は、活発に動き回ることが楽しい時期とも重なることが多いです。
耐久性にすぐれていて、フレーム全体に角がなく自分や相手を傷つける心配が少ないものを選んであげると良いと思います。
また、眼鏡の落下防止用のグッツを使っている方も多いです。
視機能:スムーズな目の動き
視機能とは?
私たちが物を見るためには、見ようとする物に注意を向ける必要があります。
その後に、両目をしっかり協調させて(両眼視)、ピントを合わせる(調節)ことで物を視野内に固定してじっと見たり(注視)、動くものを目で追ったり(追視)しています。
ダウン症のお子さんでは、これらの目の動きに苦手さがある場合があります(伊藤ら, 2009)。
以下の3つはダウン症児によくある視機能の問題です。
- 斜視:通常は右目も左目も見ようとする物の方に向きますが、片方の目だけ目標の物に向かわず、両眼視が適切に行えていない状態をいいます。ダウン症児では、目が内側にずれる内斜視が多いといわれています。
- 弱視:眼鏡をかけて視力を矯正しようとしても、視力があがらない状態をいいます。何らかの理由で視力が使えない期間が長く続いた場合に、視力の発達がうまくいかずに弱視という状態になることがあります。
- 眼振:目がけいれんしたように動いたり、左右に揺れたりする状態のことです。目の動きを上手にコントロールできな場合に起こり、ダウン症児では多くの割合でみられます。
これらの状態がある場合には、より適切な眼鏡矯正が必要になり、手術で治療を行う場合もあります。
視機能のトレーニング
ダウン症のお子さんたちでは、動くものをしっかり目で追うことが苦手で、すぐに視野から対象物がいなくなってしまうようなことも多いように思っています。そのようなお子さんたちには、以下のような遊びがおすすめです。
ビー玉キャッチ
大人と子どもで机のはじとはじに座り、大人がビー玉を子どもの方に転がします。
転がってきたビー玉を子どもがキャッチ!最初はゆっくり転がしてあげて、子どもには手でキャッチしてもらいましょう。
慣れてきたらスピードアップしたり、手ではなくて何かの容器で捕まえたりすることで難易度を調整することもできます。
風船バレー
風船を落とさないように打ち合うゲームです。
最初は大きめの風船を使うとゆっくりと動くため遊びやすいです。
慣れてきたら少し小さめの風船にしたり、紙を丸めた棒で打ったりしながら難易度を調整してもおもしろいです。
※これら2つの遊びは、ビー玉や風船などの動いてくる情報をしっかりと目で追い続ける練習です。
ビー玉キャッチは自分が動かないので、自分が動き回るような風船バレーよりも簡単かもしれません。
お子さんが7~8割できるレベルから取り組むのが楽しみながら学べるコツです。
視覚認知:見た情報を理解する力
視覚認知とは?
目から入った情報は、脳に送られて情報を分析して理解することで、私たちは視覚情報として認識・理解しています。
その情報の分析には、「物の位置や向き、自分との距離などの空間的な情報を理解する力(空間認知)」「見たものがどのような形や色なのかを理解するような形態的な情報を理解する力(形態認知)」が含まれます。
この空間認知と形態認知は互いに情報を交換しながら物の認識に役立っていますが、それぞれ脳の処理する場所が異なっていることから、お子さんによって育ちやすさ、育ちにくさもあるようです。
このような視覚認知の力は、ことばの発達にも影響を与えます。物の視覚的な情報を正確にとらえられないと、見たものの名前を覚えることにも苦労します。
例えば、それが「犬」なのか、「猫」なのか、「たぬき」なのか、私たちは顔やしっぽなどの視覚的な情報を分析して何の動物なのかを理解します。
同様に、「長い」「広い」「遠い」などの空間情報に関しても視覚情報が重要なことは理解していただけるかと思います。
文字を覚えたり、書いたりするときにも、これらの力は重要になります。
視覚認知のトレーニング
見た情報の形や向きを考えたり、その形が同じなのか・違うのかを判断したりする力などは、小さい頃はパズルやブロックなどの遊びの中では育つことが多いです。
こちらも、お子さんが取り組みやすいレベルから繰り返し取り組んで積み上げるとよいでしょう。
形や向きの情報をとらえる練習として使いやすいおもちゃを、簡単な順から紹介します。
小学生の中~高学年くらいになり、ことばの指示がスムーズに理解できるようになってきたら、家庭でできるビジョントレーニングなどもおすすめです。
まとめ:見る力を育てよう
見る力を大きく3つに分けて解説しました。
- 視力:小さい情報・遠くの情報が見える
- 視機能:スムーズに目を動かす
- 視覚認知:見た情報の理解
ダウン症のお子さんは、見る力に苦手さをもつことが多いです。本記事で紹介したような遊び・トレーニングについては、眼科的な治療が終わってから取り組まれると効果的です。
目や見え方に不安がある場合には、まずは眼科で相談しましょう。
さらに詳しい情報を知りたい方へ

.png)