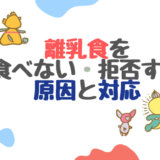ダウン症をもつ子の親「どのように関わってあげたらことばを話せるようになるんだろう?ことばを生活の中で発達させるためのポイントを知りたい。」
こういった疑問に答えます。
- ことばの発達の前提として大切なこと
- ことばを育てるための6つのポイント
- 親子の楽しいコミュニケーションを!



この記事を書いている僕は、言語聴覚士として15年以上、ダウン症をもつ子のことばの発達を支援しています。
同じダウン症をもつ子でも、ことばの発達に関してはかなり個人差が大きいです。
「発達はその子それぞれのペースで…」と頭では分かっていても、「なかなか話せるようにならない」「いつになったら言葉が出るのかな?」と不安を感じてしまうこともありますよね。
ことばの発達について、言語聴覚士に相談したいと思っても、なかなか出会えない…。「どうやって関わってあげたら、この子にとって良いのかな?」と試行錯誤されていることと思います。
この記事では、『ことばを話せるようになる前のダウン症をもつ子に、どのような関わりをすれば「ことばの発達」を促せるのか?』というテーマで解説していきます。
ぜひ、最後までお読みいただき、今日からお子さんとの遊びの中で意識してみてください!
目次
ダウン症児のことばの発達のために、まず聴力を確認しよう



まず、耳の聴こえの状態を確認しましょう。
なぜなら、聴力に問題はことばの発達に影響を与える可能性があるからです。
聴力は耳鼻科で検査できます。聴力検査は検査の種類によっては産まれたばかりの赤ちゃんでも実施できるものがあります。
特に、ダウン症をもつ子は聴力障害を合併している場合が少なくないことから、一度は耳鼻科でチェックしておけると安心です。
聴力検査の方法など、詳しい内容は以下の記事もお読みください。
》耳のきこえは大丈夫?聴力が言葉の発達に大切な理由
ダウン症をもつ子では、耳の穴が小さく狭いため、中耳炎になりやすい子が多いです。
中耳炎になると一時的に聴こえにくい状態となる場合があります。そのため、ことばの発達の面でも治療が大切。
風邪をひいた時などは、耳の状態も気にして医師に相談してみると良いと思います。中耳炎が隠れていることもありますので。
ダウン症児のことばを発達させる6つのポイント



ダウン症をもつ子のことばを発達には、以下の6つのポイントが大切。
- 向かい合って遊ぶ
- 少し大げさにリアクションをする
- お子さんが興味を持って見ている対象物の名前を言って聞かせる
- 身振りやジェスチャーをたくさんつかう
- 子どものジェスチャーにことばを添える
- 擬音語や擬態語をたくさんつかう
順番に解説していきますね。
①:向かい合って遊び、アイコンタクトを増やす
アイコンタクトには『これから、あなたに大切なことを伝えますよ』というサインが含まれていることが最近の研究結果から明らかになってきています。
例えば、相手が視線を逸らしたまま伝えた単語よりも、アイコンタクトをとってから伝えた単語を、子どもたちは効率的に学習したとする研究があります。
アイコンタクトがことばの吸収効率を上げるようなイメージですね。
詳しくは『ナチュラル・ペダゴジー理論』とかで解説されていますので、興味のある方はちょっと読みごたえのある本ですが、お読みいただければ。
ことばの発達に重要なアイコンタクトの頻度を増やすために、「向かい合って遊ぶ」ことをオススメします。
向かい合って遊ぶ時間を増やすためにも、子どもの発達の状態に合った椅子を用意することも大事。
以下の記事は、離乳食用に解説した記事ですが、運動発達別にオススメの椅子を紹介していますので、併せてお読みください。
》 ダウン症をもつ子に使いやすい椅子:運動発達別に紹介
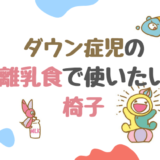
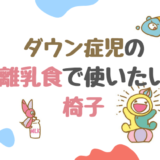
②:大げさなリアクションで、注意を引きつける
大げさなリアクションは、お子さんの注意をひきつけ、あなたが出したメッセージを効率的に届けます。
相手と同じものを見ること、すなわち「自分ー物ー相手」の三角形をつくることは、ことばの発達にとても大切。
「自分ー物ー相手」の三角形を作るためには、相手が何を見ているのかに気づくことが必要です。
あなたが何を見ているのかを子どもに伝えるためにも、大げさなリアクションは役立ちます。
このような『相手と同じものに注意を向ける』という『共同注意』に関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてお読みください。
》言葉の発達に大切な共同注意:子どもと興味を共有しよう


③:子どもが「見ている物」の名前を言って聞かせよう
繰り返しになりますが、相手と同じもの注意を向けるという『共同注意』が成立している場合に、子どもはことばを効率的に学習します。
子どもが見ている物を大人も見るようにすることが、共同注意を成立させるコツ。
例えば、子どもがミニカーで遊んでいたら、子どもの視線の先を追いながら「ブーブだね」「ブーン」などと声かけをしてあげましょう。
子どもにとっては、自分が見ているものの名前がその場で聞こえてくることになるので、ことばの学習が容易になります。
ダウン症をもつ子の共同注意とことばの発達の関係については、海外でも盛んに研究されてきました。
例えば、以下のような研究結果があります。
- 共同注意は認知スキルやことばの発達を促進する(Baldwin, 1991)
- 子どもが興味をもっている物を親に見せ、その物の名前を親が言って聞かせるというやりとりは、ことばを学習する絶好の機会となる(Libertus et al., 2016)
- 親子の共同注意を多く経験した子ほど、その後の理解語彙が多かった(Zampini et al., 2015)
これらの研究結果をまとめると、『大人と一緒のものに注意を向け、共同注意が成立している時に対象物の名前を聞くことで、物の名称を効率的に学ぶことができる』といえるかと思います。
だからこそ、向かい合って遊ぶ中でアイコンタクトや共同注意をたくさん経験させつつ、大げさなリアクションで子どもの注意を引きつけたり、子どもの見ているものを大人が追従して見るような関わりの中でことばを聞かせていくような関わりが良いと考えられます。
④:身振り・ジェスチャーを使って関わろう
身振り・ジェスチャーなどのサイン言語を交えたやりとりは、ダウン症のお子さんのことばの発達に良い影響を与えます。
ある研究では、サイン言語で表現できる語いが増えた後に音声言語が増え、音声で表現できる語彙が増えるとサインで表現する語彙が減る子が多いという結果が出ています(Zampini et al. 2010)。
要するに、サイン言語で自分の気持ちを相手に伝える経験は大切であるということと、サイン言語に取り組んだからといって音声言語が発達しないということはないということ。
例えば、「だっこ!」と言えるようになるまでに、以下のように段階的に発達する子は多いです。
- 最初は両手を広げたジェスチャーのみ
- ➔「っこ(音声)」+ジェスチャー
- ➔「だっこ(音声)」
サイン言語(ジェスチャー)で伝えていた内容が、徐々に音声に置き換わっていくような感じですね。
サイン言語より音声の方が遠くに届けることができる上に、両手がフリーになります。子どもにとって音声の方が便利だから置き換わっていくんでしょうね。
子どもがサイン言語を使えるようになるためには、大人がモデルを見せてあげる必要があります。
両腕を左右に広げて「ぶーん」と飛行機のマネをしたり、両手を頭にあてて「ぼうし、かぶろうか」と声かけをしてあげたり。
この時期は手遊び歌などもたくさん聞かせて・やって見せてあげると喜ぶと思います。
ことばの発達とジェスチャーの関連については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひお読みください。
》言葉の発達に大切なジェスチャー・擬音語・擬態語


基本的には、ジェスチャーはお子さんが分かりやすければどのようなものを使っても良いと思います。
でも、生活の中で使うことばの中には、ジェスチャーで表現しにくい単語もありますよね。例えば、「りんご」「みかん」「ばなな」など。
これらの単語をジェスチャーで表現する際には、手話が参考になります。例えば、「みかん」は手話で皮をむくような手の動きで表現します。
手話の手の動きから意味が推測しやすい語も多いので、子どもにも分かりやすいです。
⑤:子どものジェスチャーにことばを添えよう
子どもがジェスチャーで何かを表現できるようになったら、子どもがジェスチャーで表現した内容をことばにして返してあげるような関わりをしましょう。
ジェスチャーをことばに置き換えるような関わりをすることで、子どもが「サイン言語→音声言語」と移行することを助けることができます。
例えば、子どもが「飲む」のジェスチャーで飲み物を要求した時には、「飲みたいね」などとことばにして返してあげる。
このようなサイン言語から音声言語への移行に関しては、以下のような研究でも効果が示されています。
以下のような論文が報告されています。
- 定型発達児の子がジェスチャーから音声言語に移行する時に、親が子どものジェスチャーを言葉に置き換える関わりをすることで、ことばでの表現モデルをその場で示していた(Goldin-Meadow et al., 2007)
- 自閉スペクトラム症児、ダウン症児でも、ジェスチャーをことばで置き換える関わりで経験した語彙は、後にことばで言えるようになりやすかった(Dimitrova et al., 2015)
- ダウン症児へのジェスチャーやサイン言語を中心とした介入により、コミュニケーションが豊かになる(Wright et al.2013; Yoder & Warren, 2002)
要するに、障害の有無や種類に関係なく、『サイン言語を音声言語に置き換えるような関わりは、コミュニケーションを豊かにし、ことばを育てる有効な関わり方』といえると思います。
⑥:擬音語・擬態語をつかって関わろう
擬音語・擬態語を使って関わることも、ことばの発達を促すことにつながります。
なぜなら、「ワンワン」「ピョンピョン」などの音の繰り返しのある単語は、子どもにとって覚えやすく、言いやすいことばだからです。
また、擬音語・擬態語は、その音から意味が推測しやすいといった特徴があります。例えば、「プタプタ」と「バトバト」のどちらが騒がしい印象を受けますか?
どちらも、実在しない擬態語ですが、なんとなく「バトバト」の方が騒がしく感じた人が多いのではないでしょうか。要するに、「擬音語・擬態語は音から意味が理解しやすいことば」ということですね。
そのため、生活の中でたくさん使って聞かせることで、理解できる言葉を増やすことができます。
擬音語・擬態語がことばの発達を促すということに関連する論文を1つ紹介します。
- Infant-directed speech (IDS)は、子どもの注意を大人に引き寄せるのに役立ち、ことばを覚えることにもプラスの影響を与える(Englund et al., 2020)
Infant-directed speech (IDS)とは、簡単に言えば赤ちゃんことばの特徴です。大人は幼い子と関わる時に、自然と声が高くなり、おおげさなイントネーションで、擬音語・擬態語を多く使います。
このような話しかけ方の特徴は、子どものことばの発達を促すことにも役立っているわけですね。
擬音語・擬態語の重要性については、以下の記事でも詳しく解説しています。
》ダウン症児の語彙を広げて2語文へつなげる関わり


まとめ:親子で楽しいコミュニケーションを!
-520x300.png)
-520x300.png)
-520x300.png)
この記事では『ダウン症のお子さんがことばを話せるようになるまでに大切な関わりのポイント』を解説しました。
日常の中での行いたい関わりのポイント以下の6つです。
- 向かい合って遊ぶ
- 少し大げさにリアクションをする
- お子さんが興味を持って見ている対象物の名前を言って聞かせる
- 身振りやジェスチャーをたくさんつかう
- 子どものジェスチャーにことばを添える
- 擬音語や擬態語をたくさんつかう
これらを意識した関わりがことばの土台を作ります。
「でも、これを全部やらないとダメなの?ちょっと大変そう…」って思いますよね。
その答えは『できるところから始めましょう』です。毎日の関わりの中に、取り組みやすそうなものを1つでも、2つでも組み込めればOK。
なによりも大切なのが親子で楽しいコミュニケーションの時間を過ごすこと。あまり肩に力を入れすぎず、できるところから、ゆっくりと焦らずに取り組んでいきましょう。
今回はここまで。
ダウン症もつ子に関する記事は『【STが解説】ダウン症をもつお子さんの療育のポイント』にまとめてあります。お子さんの成長に合わせて、お読みいただけたらと思います。

.png)