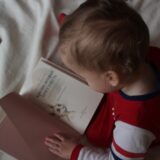「毎日、”幼稚園でなにしてきたの?”って聞いているけど、答えられない。どうしたら教えてくれるようになるのかな?」
こういったお悩みをテーマに記事を書いてみようと思います。
- なぜ、幼稚園でのことを話せないのか?
- どうすれば、話せるようになるのか?
- 伝え方・質問の仕方のコツ



幼稚園に通い始めると、子どもが日中どのように過ごしているのか実際に見ることができません。
そのため、「楽しく通えているかな?」「困ったことはないかな?」と心配になることもありますよね。
でも、ことばの発達が幼い時期だと、子どもに幼稚園でのことを質問しても上手く答えられず、もどかしい想いをすることも多いのではないでしょうか。
この記事では、「幼稚園でのことを話す」ということが難しい理由を解説した上で、どのように支援してあげるべきかを紹介します。
今日から取り組める内容になっていますので、最後までお読みください。
なぜ、幼稚園でのことを話せないのか?



まず、理由を知ることが大事。ここでは「言葉の発達」という視点から考えてみましょう。
言葉の発達という視点から考える
会話の発達には、以下のような原則があります。
- 目の前の話題→目の前にないことの話題
- 今、ここの話題→過去や未来の話題
おうちの中で目の前のおもちゃに関してはたくさん話せるようになっても、幼稚園での出来事(過去)を思い出しながら話すことは大変なことです。
過去の話題で話すのは難しいこと
幼稚園でのことを話すためには、以下のような力が必要になります。
- 目の前にないものを説明する力
- 過去のことを覚えておく力
もう少し詳しく解説しますね。
幼稚園でのことは、すでに終わったことなので目の前にありませんよね。当たり前ですが。でも、これを相手と共有しないと会話は成り立ちません。
例えば、幼稚園の砂場で遊んだとしたら、その様子を相手が想像できるように伝える必要があります。
でも、ことばの発達が幼い時期では、相手が思い浮かべやすいように分かりやすく説明することは大変。
目の前にない「過去の話題」を相手と共有することは難しさから、幼稚園のことを話せないのかもしれません。
幼稚園でのことを話すためには、自分の経験を覚えておく必要があります。
その日のことを覚えておくことくらい簡単そうに思えますが、子どもたちにとっては結構大変なことなんです。
特に、「今」「あとで」「このまえ」などの時制に関する語彙の認識が進んでくるまでは、子どもの記憶の時系列はあいまいな場合が多いように感じます。
どうすれば、幼稚園でのことを話せるようになるのか?



答えはシンプル。話せない理由に対して支援しましょう。
質問:難しい質問を浴びせ続ければできるようになりますか?
たまに、幼稚園でのことを話せるようになるために「毎日、幼稚園でやったことを質問してください」といわれることがあります。
でも、よく考えてみてください。難しい質問をただ浴びせたところで、その質問にこたえられるようにはならないですよね。
もしかしたら、パターン的に「何した?」→「ブロック」という答えを覚えるかもしれませんが、内容が真実でないなら意味がありません。
じゃあ、どうすればいいのか?それは『子どもに伝わるように質問する』ということを積み重ねるのが良いと思います。
話題を視覚化しよう
休日に公園に出かけた時などに、子どもの写真を撮っておきましょう。スマホでOKです。
自宅に帰ってから、公園でとった写真を見せながら会話をしてみましょう。話題となる公園の風景が目の前にあるので、話しやすくなります。
まずは、『過去の話題で会話をする』という経験を、親子の共通の体験の中で積み重ねてみましょう。
幼稚園でのことをする時には、幼稚園で作って持って帰ってきた制作物について会話をするのもオススメです。
要するに、話題となる“もの”を視覚的に確認できるようにしておくことで、過去の話題で話しやすくなります。
直近の話題から始めよう
記憶への負荷を軽減するために、直近の話題で会話をしてみると良いでしょう。
例えば、幼稚園に迎えに行ったときに砂場で遊んでいたなら、「砂場でなに作ったの?」と聞いてみたり。
直前の出来事の方が記憶に残っている場合が多いので答えられるかもしれません。
【コツ】答えやすい質問の仕方
まずは、上記で紹介した「話題の視覚化」「直近の話題」を試してみてほしいと思います。
それに加えて、以下の配慮をしてあげることで、さらに会話がしやすくなるかも。
- 場面を限定する
- 簡単な疑問詞を使う
- Yes-Noで答えられる質問をまぜる
「幼稚園でなにしたの?」と漠然と聞かれても、何を答えていいのか困ってしまう子もいます。
「給食は何を食べたの?」とか「制作は何を作ったの?」といったように、場面を限定してあげると答えやすいです。
「どうして?」「なんで?」といった質問よりも「なに?」「だれ?」といった質問の方が答えやすくなります。
例えば、「給食でなに食べたの?」「だれと食べたの?」といったように。
印象としては、「なに?」→「だれ?」→「どこ?」→「いつ?」→「なんで?」の順で難しいように感じます。
Yes-Noで答えられる質問をまぜながら会話をすると続きやすくなります。
例えば、「〇〇くん、いた?」「転んだ?」など。質問もできるだけ短く聞いてあげると良いと思います。
幼稚園でのことを話すことだけが重要ではない



当たり前ですが、「会話が楽しい!」という気持ちを育てることが最優先です。
会話=楽しい、と思える経験を大切に
この記事では、言葉の発達という視点から「幼稚園でのことを話す」を考えてみました。
でも、幼稚園でのことを話せるだけの発達を遂げていたとしても「話したい!」という気持ちがなければ話さないですよね。
話したい気持ちをはぐくむためには、日頃から「話したことをキャッチしてもらえた」という経験の積み重ねが大事。
会話はキャッチボールに例えられるように、「投げる→キャッチ」の繰り返しがコミュニケーションの意欲を育てると思います。
幼稚園での話にこだわる必要はない
「幼稚園でのことを話す」をテーマに解説しましたが、要するに『過去の話題で話す』という力を育てることが大切。
なので、なにも幼稚園での出来事にこだわる必要はないのです。
「今日の朝ごはんのパン、おいしかったね」とか、「公園に大きいバッタいたね」とか。
親子での共通体験を話題にするだけでも、会話は発達していきます。
話題を共有することが大切
それでは、今回はここまでにしようと思います。
繰り返しになりますが、相手と話題を共有することが大切。話題の共有を成功させるために、以下のような配慮をしてあげるとうまくいくかもしれません。
- 話題の視覚化
- 直近の話題
- 場面を限定した質問
- 簡単な疑問詞を使った質問
- Yes-Noで答えられる質問