
「うちの子、しりとりができない。何歳までにしりとりができないとダメなのかな?」
こういった心配をテーマに記事を書いてみようと思います。
- しりとりはいつからできるのか?
- なぜ、しりとりが大切なのか?
- しりとりを教えるコツ【5ステップ練習法】



この記事を書いている僕は、言語聴覚士という資格で子どものことばの発達を支援しています。
周りの子がしりとりができるようになる中、自分の子がなかなかできるようにならないと心配になりますよね。
しりとりを教えようと思っても、どのように教えたら良いのか分からずに苦労していませんか?
この記事では、しりとりの教え方のコツを5ステップで紹介します。
でも、その前に『しりとりができるために必要な力』と『しりとりが発達に大切な理由』を解説してみようと思います。
しりとりはいつからできるのか?
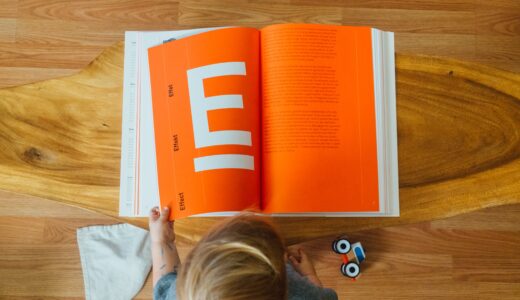
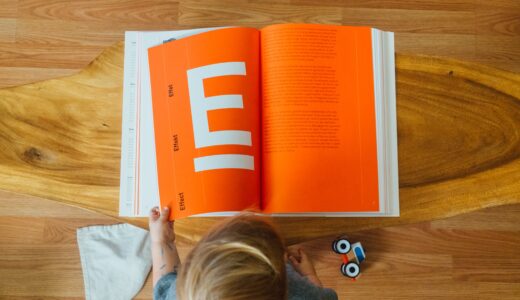
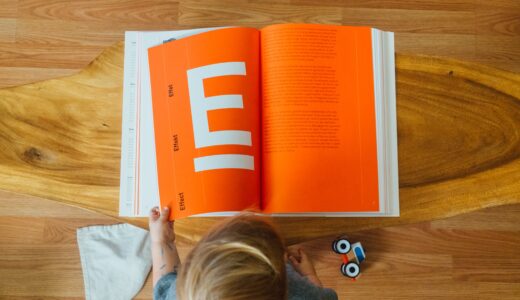
結論、しりとりは4~5歳くらいにできるようになります。
でも、大切なのは年齢よりも『しりとりができるために必要な力』を知ることです。
4~5歳でしりとりができるようになる【一般論】
しりとりは、4~5歳でできる子が多いです。
でも、このような「〇歳になるとできるようになる」という考え方は、分かりやすいようですが役に立ちません。
なぜなら、なにか新しいことができるようになるためには、その基礎となる力が身についている必要があるからです。
例えるなら、次のような感じ。
※バットの振り方がわからない人には、ホームランは打てない
当たり前ですよね。ホームランを打つためには、ちゃんとバットを振れたほうが良い。
発達を考える時も、「〇歳になったら…」ではなく、「〇〇ができるようになるために必要な力は何か?」と考えてみましょう。
そうすることで、子どもに必要な関わりが見えてきます。
しりとりができるようになるためには、以下のような力が必要です。
- 単語の最後の音を取り出す
- 取り出した音から単語を想起する
例えば、しりとりができるためには、「たいこ」の『最後の音は「こ」』ということが分かる必要があります。
さらに、自分が知っている語彙の中から『「こ」が最初につく単語』を探して言わなくてはいけません。
『達成したい目標の土台となる力は何か?』という視点で掘り下げて考えてみましょう。
例えば、「単語の最後の音を取り出す」ためには、以下のような力が必要です。
- 単語の最後の音を取り出す
(たいこ:「こ」) - →単語をつくる音の順番が分かる
(たいこ:「た」→「い」→「こ」) - →単語の音を正確に聞き取る
(たいこ:〇「たいこ」、✕「たいと」)
このように土台となる力を掘り下げた上で、子どもが『どこまで理解できていて、何が分からないのか?』というラインを見つけましょう。
練習すべきは、そのラインの内容・難易度です。要するに、評価・見立てが大切ということですね。
なぜ、しりとりが大切なのか?



しりとりは「発音」や「読み書き」の基礎となります。
「発音」と「読み書き」に共通する土台の力
発音と読み書きの発達には、以下のような『音を認識する力』が必要です。
- 単語の音の数が分かる
- 単語の音の順番が分かる
上記は、「てれび」なら単語の中に3つの音が含まれていて、「て」「れ」「び」という順番に並んでいるということに気づく力です。
これらの力が未熟な場合、発音や読み書きの時に、“テレビ”→「てび」というように音の数を誤ったり、「てべり」と音の並びが変わってしまったりすることがあります。
「発音」「読み書き」に必要なのは、しりとりができることではなく、『しりとりができるほどに音の認識が育つこと』です。
要するに、しりとりを通して「音の認識」を育てることが、「発音」「読み書き」の発達につながるということ。
そのため、「音の認識」の発達の順番に沿って練習していくことで、以下のような好循環がうまれます。
音の認識が育つ
→しりとりが上手くなる
→発音や読み書きが育つ
しりとりだけ特訓しても、うまくいかない場合が多いということですね。
発音や読み書きの発達については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、併せてお読みください。
もうひとつ大切なのが、しりとりはあくまで「音遊び」だということ。
読み書きなどは、どうしても「お勉強」といったイメージがありますが、しりとりは遊び感覚で取り組めます。
だからこそ、しりとりを“訓練”するのではなく、毎日の楽しい遊びの時間として取り組むような意識をもちたいですね。
しりとりを教えるコツ【5ステップ練習法】



しりとりの練習は、以下の5ステップで練習すると積み上げやすいです。
- ①:韻を楽しむ
- ②:単語の拍をとる
- ③:特定の音から単語を想起する
- ④:単語から音を取り出す
- ⑤:しりとりを練習する
しりとりの練習をしているようで、実は『音の認識』を育てているということをお忘れなく。
それぞれについて、もう少し具体的に紹介しますね。
「単語の中に含まれる音がおもしろい!」という経験は大切です。
例えば、「おもちゃのチャチャチャ」のリズムで「だいこんはコンコンコン」「にんじんはジンジンジン」など、様々な単語で楽しんでみるのも良いと思います。
その他には「アルパカパカパカやってきて」みたいな韻を楽しむ絵本などもオススメ。
お子さんが楽しめそうなものを選んでみてください。
「単語の中にいくつ音が含まれているか」という意識を育てましょう。
例えば、単語の音に合わせて手拍子をするのもオススメ。「たいこ」なら「た」「い」「こ」と言いながら手を叩く感じです。
これならお風呂でもできますね。
その他には、サイコロの目に「いぬ」「こあら」などのイラストのシールを貼った「すごろく」もおもしろいです。「いぬ」が出たら「い」「ぬ」と2マス進めるようにします。
「“あ”で始まる単語は?」というように特定の音から単語を想起する力も育てていきましょう。
最初は、選択肢の中から選ぶようにすると取り組みやすいと思います。例えば、好きな図鑑の中から「“き”で始まるのは?」と聞いて指さしてもらったり。
慣れてきたら、図鑑は広げずに聞いてみるなど、少しずつ言葉だけで考えられるように進めていけると良いと思います。
以下の順番で、単語の中から音を取り出すことが難しくなります。
- 最初の音を取り出す
- 最後の音を取り出す
- 真ん中の音を取り出す
単語の音の数だけ積み木を並べて、「ココの音は?」と積み木をヒントにすると分かりやすくなるかもしれません。
練習用のプリントも用意したので、お試しください。
》【言語聴覚士が作成】ことばの発達プリント:家庭療育
まずは、しりとりカードやしりとりパズルのように、イラストを利用した練習がオススメです。
しりとりの順にイラストを並べられるようになってきたら、ことばだけでのしりとりにも挑戦してみましょう。
まとめ:しりとりは文字や発音の発達につながる



この記事では、『しりとりがどのようにできるようになるのか?』というテーマで解説しました。
ここまでをまとめます。
- 音を認識する力が、しりとりの土台の力となる
- 発音や読み書きの発達にも、音の認識は大切
- 発達に合わせた課題で音の認識を育てよう
こんな感じです。
しりとりに限らず、子どもの発達を考える時には「発達の順序」を理解することが大切です。
目標となる行動が可能となるためには、背景にどのような力が必要なのか?
土台となる力を丁寧に紐解くことで、子どもに必要な関わりが見えてくると思っています。
以下のリンクは「幼児期のことばの発達がどのような順序で進むのか?」といった内容を解説した記事です。
》言葉の発達段階:完全ガイド【子どもの獲得順序に沿って徹底解説】


ぜひ、併せてお読みください。
それでは、今回はここまで。最後までお読みいただき、ありがとうございました。



