先日、以下のようなお問い合わせを頂きました。
「ルールのある遊びに参加できず、いつも一人遊びになってしまいます。どうやったらルールが理解できるようになり、お友達と遊べるようになるのでしょうか?」
今回は、こういったテーマで記事を書いてみようと思います。
- ルールのある遊びの発達の仕方
- ルールのある遊びの発達を促すコツ
- 具体例(ルール遊びを育てる関わり)

お子さんは、集団遊びの中でどのように困っているでしょうか?
この記事を読んでいただいているあなたも、子どもの集団遊びへの参加に関してご心配されているかと思います。
ルールのある遊びができるようになるためには、その土台から丁寧に成長させていくことが必要です。
では、その土台とは何か?
この記事では、ルールのある遊びができるようになるまでの発達の経過と、発達を促す関わりの具体例を解説します。
ぜひ最後までお読みください。
目次
ルールのある遊びの発達の仕方



当たり前ですが、いきなり複雑なルールは理解できません。子どもたちは簡単なルールから、少しずつ分かるようになっていきます。
ルールは簡単なものから順に理解が進む
以下のようなポイントで子どもを観察すると、現状の発達が見やすいのではないかと思います。
- 順番:〇〇君の次は〇〇の番、など
- 役割交代:僕が投げる、君がキャッチ、など
- ルール理解:同じ絵ならもらう、など
おおよそ、この順番で発達は進んでいきます。
そして、それぞれの項目が、どのくらいできるようになっているかを把握することが大切です。
当然ですが、2人で順番を守るのと、10人で順番を守るのでは難易度が異なります。
また、普段は順番が守れても、本人が大好きな活動で順番を待つことは大変な子がいるかもしれません。
どういった活動なら順番が守れるのか?ということを丁寧に観察しましょう。
遊びの中でそれぞれの役割を理解して、その役割を柔軟に交代しながら遊ぶ力も、集団遊びの中では大切になります。
たとえば、ボーリングで「投げる人」「ピンを立てる人」で役割を分けるなど。
ただ順番を待つだけではなく、それぞれの役割を持ちながら遊ぶ点で少し難しくなりますね。
順番と役割交代の力を土台に、簡単なルールを守って遊べるようになっていきます。
たとえば、神経衰弱などのように「数字がそろったら場に出す」といったルールを理解することなど。
勝ち負けや感情のコントロールなど、様々な要素が含まれてくるので課題が見つけにくくなりますが、子どもが何に困っているのか丁寧に観察するのが大切です。
※まず、子どもが「順番」「役割交代」「ルール理解」について、何ができて、何が難しいのかを把握しましょう。
できることを色々なゲームで経験することも大切
例えば、ブランコで順番が守れるようになったら、すべり台などの他の玩具でも順番を待ってみるなど。
今、できていることを横展開して、様々な場面で経験していくことも大切。
できるようになったことが、他の活動でも応用できるようになることも立派な成長です。
ルールのある遊びの発達を促すコツとは?



結論、「求めるルールを守れるような課題設定にする」です。
自然とルールが守れちゃうように設定する
環境を工夫して、求められているルールを守りやすくしてあげましょう。
具体的には、待つ場所に足型を用意して目立たせる、取り組む順番をスケジュールとして示すなど。
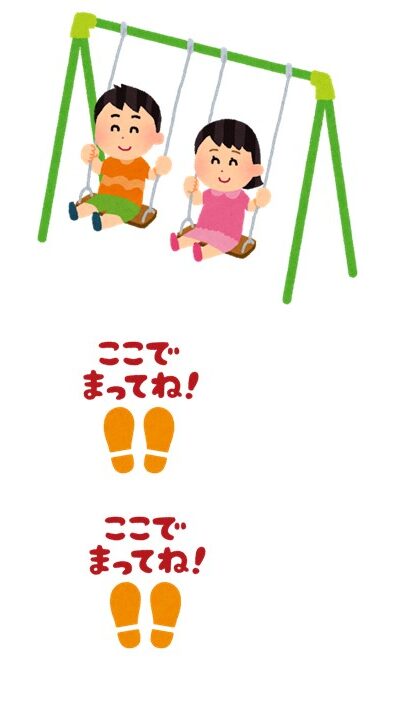
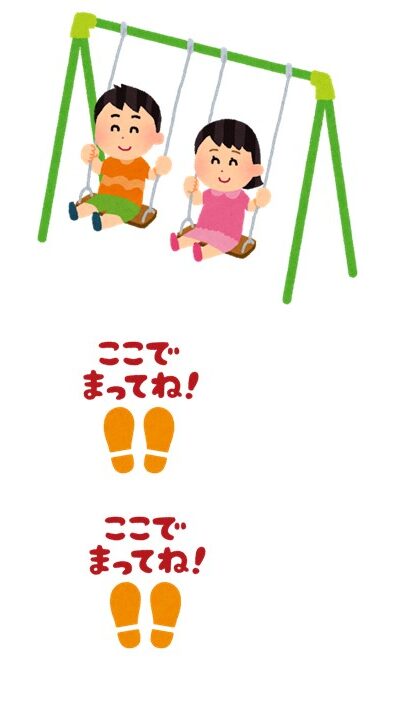
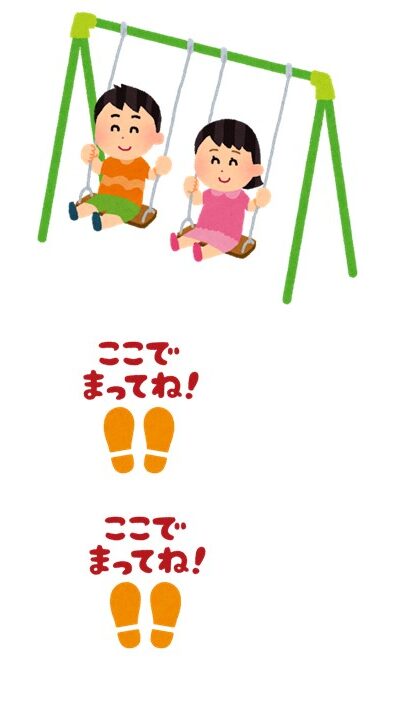
まずは環境調整することで、子どもに「上手くできた!」ということを経験させましょう。
ルールを守れている時に褒める
もうひとつ大切なのが、「ルールを守れている時に褒める」ということ。
ルールを守っている最中に褒められることで、その行動が持続しやすくなります。また、本人にとっても頻回に褒められることで自信につながると思います。
「ピンを立ててくれてありがとう」「負けそうだけどあきらめずに頑張っててカッコイイよ」など。
子どもに合わせて声かけをしてあげましょう。
まずは大人と1対1で
最初のうちは、大人と1対1の中で練習すると良いと思います。そうすることで、子どもが成功しやすくなりますからね。
まずは大人との間で成功体験を積み、安定してできるようになったら、子どもとの間で取り組んでみると良いかもしれません。
ルールのある遊びを発達させる関わり方の具体例



それでは、実際に僕が療育の中で子どもたちに「ルールのある遊び」を経験させるために行う課題を紹介しますね。


黒ひげ危機一発は『順番』を理解するのに取り組みやすいゲームです。
最初は、大人がが刀を刺したら、1本だけ子どもに「次は〇〇君の番」と言って渡します。こうすることで、自然と順番を守れていますよね。
慣れてきたら、「次は誰の番だっけ?」などと質問を入れつつ、順番を理解できているかを確認するのも良いと思います。
徐々に、場に刀を出して、自分で順番を判断できるように促していけばOKです。


ボーリングは『役割交代』を意識するのに取り組みやすいゲームです。
「ボールを転がす人」と「ピンを立てる人」に分かれます。
この時に、場所を固定するのがコツ。転がす人は椅子、立てる人は枠の中など。
ボールを転がし終わったら「交代」の声かけで場所をチェンジします。慣れてきたら、「2回ずつやったら交代」などのバリエーションを出しても良いかも。


おつきさまバランスゲームは、ルールが単純なので初期に導入することが多いです。
ルールを理解してもらうために、最初は「子ども一人で」取り組んでもらいます。子どもがサイコロを転がして積木をのせたら、また子どもがサイコロを転がして…、といった感じ。
ルールを理解するまでは、「順番」や「役割交代」の要素は入れないようにします。覚えてほしいことは、できるだけシンプルにしましょう。
ルールが分かったら、順番・役割交代の要素を入れて、一緒に楽しみます。


上記のおつきさまバランスゲームができるくらい、ルール理解がしっかりしてきたら神経衰弱などもできるかもしれません。
神経衰弱を初めてやるなら、トランプよりもテディ・メモリーのようなイラストのものを使うのがオススメ。
最初は6枚くらいから始めて、徐々に枚数を増やしていくと良いと思います。
勝ち負けにこだわる子は?
これに関しては、賛否両論あるかもですが、僕は「基本、勝たせてあげる」で良いと思っています。
特に幼児期に関しては、ゲームを通して育てたいことは「相手と楽しい時間を過ごすこと」だと思っています。なので、子どもが穏やかに過ごせることを優先しても良いのではないでしょうか。
子どもが勝っていて機嫌が良い時に、「次は勝ってもいい?」と事前に心構えをさせておくと受け入れられたりすることもあります。
それも無理なら、途中で「負けそう、ヤバイ!」といったドキドキ感だけ与えて、最終的には勝たせてあげたり。
成長とともに、負けても大丈夫な日がいつか訪れる子が多いです。
まとめ:簡単なゲームからコツコツと、ルールのある遊びを覚えよう



今回は、「ルールのある遊びに参加できない…」といったご相談にこたえる形で記事を書いてみました。
ここまでをまとめます。
- 順番、役割交代、ルール理解という視点で子どもの発達を把握しよう
- 今できていることを、他の活動に横展開することも大切
- 子どもが無理なく取り組める遊びの例を紹介
こんな感じでした。
お子さんが「ルールのある遊びを楽しめるようになるために、今から取り組めること」が見つかったのであれば嬉しいです。



