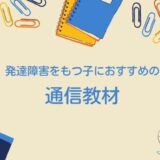「テレビを見せすぎているせいで言葉の発達が遅いのかな?なんでテレビが言語発達に悪影響なんだろう?メディアと上手く付き合うコツがあるなら知りたいな」
こういった悩みにこたえます。
- テレビが言葉の発達に悪影響な理由
- 上手にメディアと付き合うコツ
- 視聴時間を減らすための戦略



この記事を書いている僕は、子どもの言語発達に関する専門家(言語聴覚士)として働いています。
「子どもがテレビばかり見ている」「動画の時間を減らしたい」と思っていませんか?
また、「テレビを見せすぎているせいで言葉の発達が遅いのかも……」と悩んでいませんか?
最近の研究からも、テレビなどのメディアの見せっぱなしは言語発達に良い影響を与えないことが示されてきています。
でも、現在の生活の中から、各種のメディアを取っ払うことなんて現実的ではありませんよね。
そこで、この記事では『生活の中でメディアとうまく付き合っていく方法』を紹介します。
「なぜ、メディアが言語発達に悪影響を与えるのか?」ということを理解して、そこを補うような関わりをしていくことが大切です。
ぜひ、最後までお読みいただき、生活の中に取り入れてみてください。
目次
テレビの見せすぎで「言葉の発達」は遅れるの?



結論からいうと、テレビの見せ方で言葉の発達への影響は変わってくるようです。
今やテレビやスマホなどのメディアは生活の中にあって当たり前になってきました。
テレビや動画を見ることで興味が広がることもありますし、一概に悪いものでもないような気がしますよね。
でも……
メディア視聴は言葉の発達を妨げるとする研究結果は多い
メディア視聴と言葉の発達の関係性に関しては世界的に注目されています。
このテーマで医学論文を調べると『メディア視聴は言葉の発達を妨げる可能性がある』と結論づけているものが目立ちます。
例えば……
- 研究①:Zimmermanらの調査(2007 J Pediatr)
- 研究②:DeLoacheらの調査(2010 Psychol Sci)
- 研究③:Sundqvistらの調査(2021 Front Psychol)
これらの研究では、特に1歳半未満の乳児への影響が大きいことをうかがわせるような結果が出ています。
そして、テレビや動画を見せっぱなしにすると最も言葉の発達に悪い影響が出ていましたが、親の関わりが加わることでメディア視聴の悪い影響が弱まる可能性も示されていました。
そもそも、なぜ、メディア視聴が言葉の発達を妨げるのでしょうか?
メディア視聴が言葉の発達を妨げる要因
メディア視聴と実際のコミュニケーションの最も大きな違いは『一方的か双方向的か』といった点です。
子どもたちは、『双方向』のコミュニケーションから効率的に言葉を学びます。
例えば、生後9ヶ月の赤ちゃんが新しい言語を「①:人とのやりとりを通して聞いた場合」と「②:動画の視聴で聞いた場合」では、「①:人とのやりとり」の方が言語を学べたとする研究は有名です(Kuhl et al., 2003 Proc Natl Acad Sci USA)。
すなわち、言葉の発達に重要なのは、実際のやりとりのように視線を合わせ、相手の様子を見ながら、適切なタイミングで声かけすることであり、テレビや動画のように一方的に言語を浴びせるのではないということですね。
とはいえ、生活の中に当たり前のようにあるメディア。全く触れることなく子育てをするなんて現実的ではありません。
メディアとは、どのように付き合ってくべきなのでしょうか?
テレビなどのメディアとの上手な付き合い方



メディアとの付き合い方については『小児科医会の提言』、現状の親子のメディア活用の実態については『ベネッセの調査』が参考になります。
小児科医会「子どもとメディアの問題に対する提言」
日本小児科医会が2004年に「子どもとメディアの問題に対する提言」を出しています。
1.2歳までのテレビ・ビデオ視聴は控えましょう。
2.授乳中、食事中のテレビ・ビデオの視聴は止めましょう。
3.すべてのメディアへ接触する総時間を制限することが重要です。1日2時間までを目安と考えます。テレビゲームは1日30分までを目安と考えます。
4.子ども部屋にはテレビ、ビデオ、パソコンを置かないようにしましょう。
5.保護者と子どもでメディアを上手に利用するルールを作りましょう。
日本小児科医会 子どもとメディア委員会
ベネッセ「乳幼児の親子のメディア活用調査レポート」
ベネッセ教育総合研究所では、2018年に「乳幼児の親子のメディア活用調査」を実施しています。
スマホに関する調査結果の概要を抜粋します。
・2~3歳児の約2割がほぼ毎日スマホと接触している
・しかし、スマホなどのメディアを長時間利用している家庭はごくわずかである。
・外遊びや絵本を読むなどの時間が過去に比較して減少しているわけでもない。
・1日の生活の中にバランスよくメディアを取り入れようと保護者が配慮している様子がうかがえる
ベネッセ教育総合研究所
全体として、メディアと上手く付き合っている親子が多いといった結果のようでした。
しかし、財務省が公開している「未就学児等のICT利活用に係る保護者の意識に関する調査」では『外出での待ち時間や母親が家事をしている時にスマホに触れている』という回答の割合が増加していると報告もしています。
親子で会話をしながらメディアを楽しむ大切さ
テレビなどのメディアを子育ての中で使うなら『親子で一緒に見て、内容について会話をする』ことをおすすめします。
親子で会話をしながらメディアを楽しむことで、双方向性のコミュニケーションの中でメディアにふれることができます。
実際に『子どもと一緒にメディアを見たり聞いたりするだけでなく、メディアの内容について会話をすることで言葉の発達に良い影響を与える』という研究結果も出てきています(Sundqvist et al., 2021 Front Psychol)
- ×:メディアに子守りをさせる
- 〇:メディアを一緒に使って楽しむ
こういった意識で、親子で楽しみながらコミュニケーションをとっていくことが大切です。
テレビなどのメディアを減らした先輩パパ・ママの戦略!
テレビやスマホなどのメディアの視聴時間を減らすことに成功した先輩パパ・ママの戦略を紹介しますね。
①:テレビの擬人化!
②:時間の視覚化!
③:他の楽しみに誘導!
戦略①:テレビの擬人化!
「テレビさんが疲れちゃったみたい」などの声かけが有効でした!
2歳頃のお子さんだと、身の回りのものに命があるかのような声かけをすると納得してくれる子もいますよね。
テレビを早めに切り上げることができた時には、「ありがとう!って言っているね」など感謝の気持ちも一緒に伝えてあげましょう。
このような関わりの中で、自信や優しさも育っていきます。
戦略②:時間の視覚化!
「砂時計を使って終わりの時間を予告しておいたら、自分で区切りをつけられることが増えてきました」
時間の見通しが立ちにくい子だと、急に終わりにされたような気がして怒ってしまうのかも。
砂時計などで時間を目で見て分かるようにしてあげることで、「終わりの見通し」がたって「終了の心の準備」ができる子もいます。
「〇〇したら・・・」といった指示の意味が分かるようになってきた頃に試してみても良いと思います。
戦略③:他の楽しみに誘導!
「テレビ以外の楽しみが増えたら視聴時間が減ってきました。うちの子は習い事のダンスがはまったみたい。家でも踊っています」
テレビよりも夢中になれるものを見つけてあげることも大切です。
興味の幅が広がりにくい子なら、テレビの内容をきっかけに他の媒体に広げるのも良いかも。
たとえば、「テレビで出てくるキャラクターを絵本で読む」「テレビで見た内容を実際に自分でもやってみる」など。
少しずつでも興味を広げてあげることで、メディア視聴の時間が減るかもしれません。
テレビなどのメディアに関するよくある疑問



メディア視聴に関してよくある質問への回答です。
①:みんなどのくらいテレビを見せてるの?
②:教育系のアプリはどうなの?
③:小さい頃に見せすぎた時間は取り返せない?
疑問①:みんなどのくらいテレビを見せてるの?
ベネッセ教育総合研究所の調査では、「テレビ番組」を見る時間は以下のとおりで、家庭によって差があるようでした。
- 30分以下:23.5%
- 1時間:30.4%
- 2時間:23.3%
- 3時間以上:23.0%
小児科医会の提言にあるように『2時間以内』の家庭が過半数のようです。
その他にも、DVDやスマホ・タブレットなどのメディアを合計して、2時間以内におさえるように努力していきましょう。
疑問②:教育系のアプリはどうなの?
教育系のアプリも基本的にはテレビなどのメディアと同じように考えていけると良いと思います。
一方的な情報の受け取りよりも、双方向性のコミュニケーションが大切です。
ひとりで黙々と取り組ませるよりは、アプリの内容について会話しながら取り組みましょう。
疑問③:小さい頃に見せすぎた時間は取り返せない?
時間は取り返せなくても、これから積み上げていくことはできます!
でも、だからといって急に「テレビを見せない」「ゲームをやらせない」というのは、子どもにとってもしんどいかも。
まずは親子でメディアの内容について会話をしながら楽しむところから始めていきましょう。
まとめ:メディアは生活の中にバランスよく取り入れよう!



この記事では『テレビなどのメディアが言葉の発達に与える影響』について解説しました。
ここまでをまとめます。
- メディア視聴に双方向性のやりとりを組み込むべき
- 親子でメディアの内容について会話するのが大切
- 0にするのではなく上手く付き合う意識を持とう
こんな感じでしょうか。
言葉の発達には、相手との活きたコミュニケーションの経験が不可欠です。
テレビや動画などのメディアばかりにならないよう、おもちゃ遊びや外遊びも毎日の生活の中に取り入れていきましょう。
「テレビを上回る楽しみ」を見つけられれば、テレビは自然と卒業していくかもしれないですしね。
とはいえ、「なかなかテレビ以外の遊びにさそえなくて…」という人は、思い切って児童館に行くなど、場所を変えてしまうのも良いかも。
家の中でテレビが見えていると、どうしても見たくなってしまう子も多いですから。
あとは、動画を見せるのであれば、幼児向けの通信教材のコンテンツ(DVDなど)を使うのも手です。
この記事で紹介したベネッセも、家庭でのメディア視聴に関する調査をしたうえで、幼児向け通信教材(こどもちゃれんじ)も開発しています。
子どもとの会話のネタになるような、実体験につなげやすいようなコンテンツを見つけていけると良いかもしれませんね。
動画などのメディアは見せっ放しにするのではなく『内容について会話をしながら一緒に見る』という付き合い方がオススメです。