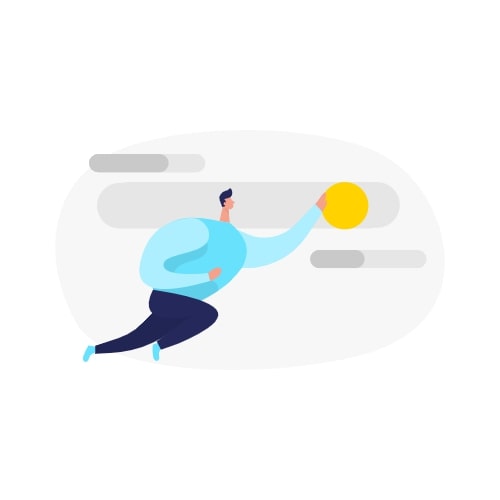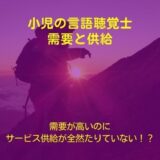「子どもがなかなか言葉で話せるようにならない…。たくさん話しかけてあげているのになんでかな?どうやって関わってあげたらいいのか知りたい」
こういったテーマで記事を書いてみようと思います。
- なぜ、ジェスチャーや擬音語が大切なのか?
- 子どものジェスチャー・擬音語を育てるコツ
- ことばにつなげる効果的な関わり方



なかなか子どもが話せるようにならないと、心配になってしまいますよね。「子どもの発達は個人差が大きいと分かっていても、心ばかりが焦ってしまう」という人もいるのではないでしょうか。
でも、どうやって関わってあげたら子どもの言葉の発達を伸ばしてあげられるかが分からない…という人も多いですよね。
実は、ジェスチャーや擬音語・擬態語は、ことばで話す前~話し始めの段階の子の言語発達を促すことが分かってきています。
そこで、この記事では生活の中でどのように言葉を発達させる関わりを取り入れていけばよいかを解説します。
それではさっそくお読みください。
目次
ジェスチャーや擬音語・擬態語が言葉の発達に大切な理由



子どもにとって、言葉よりも簡単な方法である「ジェスチャー」「擬音語・擬態語」で意思伝達を経験することが大切。
言葉で話せるようになるまでの発達過程
当たり前ですが、子どもたちは突然あるときに言葉で話せるようになるわけではありません。
「ジェスチャー」→「擬音語・擬態語」→「成人語」
上記のような順番で、意思伝達の手段を発達させていく子が多いです。
例えば、『飛行機』の語彙なら以下のような順序。
- ①:両腕を左右に広げたジェスチャー
- ②:「ビューン」などの擬態語
- ③:「ひこうき」という音声
要するに、「飛行機」などの音声で話せるようになる前の段階では、ジェスチャーや擬音語・擬態語を育てることが重要ということ。
では、ジェスチャーや擬音語・擬態語は、なぜことばで話せるようになる前段階として重要なのでしょうか。
ジェスチャーがことばの前段階として大切な理由
「相手に意志を伝える手段」として、ジェスチャーを使用する経験がことばにつながっていきます。
子どもがまだ話すことができない時期では、ジェスチャーは相手に要求を伝えるための大切な手段です。
この時期に育みたいのが「コミュニケーションの意欲」
言葉で話せなくてもジェスチャーで伝えることができた経験は、『自分の気持ちが伝わった!』という自信につながり、コミュニケーションの意欲を高めます。
コミュニケーション意欲は『ことばで話す力の土台』となるため、ジェスチャーで気持ちを表現する経験は、ことばの発達に大切。
コミュニケーション意欲(伝えたい気持ち)が、ことばの発達に大切である理由については、以下の記事で詳しく解説しています。


擬音語・擬態語がことばの前段階として大切な理由
擬音語・擬態語は『言いやすく・覚えやすい』という特徴があるため、ことばの前段階として大切です。
なぜなら、擬音語・擬態語には「トントン」「ピョンピョン」のように音が繰り返されてる語彙が多く含まれています。
音の繰り返しが多い擬音語→記憶力が未熟な子でも覚えやすい
要するに、子どもはいきなり成人語のような複雑な音の組み合わせを覚えるのは難しいので、単純な音の繰り返しでできている擬音語・擬態語から学習します。
擬音語や擬態語は、動詞をあらわすことも多いです。例えば以下のような語彙ですね。
- 「ゴクゴク」(飲む)
- 「モグモグ」(食べる)
- 「ゴシゴシ」(洗う)
言葉の発達に大切なジェスチャー・擬音語・擬態語を育てる関わり



上記のように、ジェスチャーや擬音語・擬態語は子どものことばの発達の土台になります。具体的には、以下を生活の中で意識すると良いと思います。
- 大人がジェスチャーを使って子どもに関わる
- 子どものジェスチャーにことばを添える
- 擬音語・擬態語を使って子どもに関わる
順番に解説しますね。
大人が身振り・ジェスチャーをたくさん使って関わろう
身振りやジェスチャーを交えたやりとりは、子どものことばを発達させることが分かってきています。
子どもの言語は、最初は両手を広げてジェスチャー(だっこ)のみ➔「っこ」+ジェスチャー➔「だっこ」といったように段階的に発達していきます。
とはいえ、いきなりお子さんが身振り・ジェスチャーを使うことはできません。
まず、大人がモデルを見せてあげることが必要
両腕を左右に広げて「ぶーん」と飛行機の真似をしたり、両手を頭にあてて「ぼうし、かぶろうか」と声かけをしてあげましょう。
お子さんがジェスチャーを使えるようになるためには、まずは周囲の大人が使うジェスチャーの意味を理解することが必要です。
この時期は手遊び歌などもたくさん聞かせて・やって見せてあげると喜ぶ子が多いと思います。
基本的には、ジェスチャーはお子さんが分かりやすければどのようなものを使っても良いと思います。
しかし、日常でつかう語彙の中には、ジェスチャーで表現がしにくい単語もありますよね。例えば、以下のような語彙はジェスチャーで表現しにくいのでは?
- りんご
- みかん
- だいこん
上記のような単語をジェスチャーで表現する際には、手話が参考になります。例えば、「みかん」の手話は皮をむくような手の動きで表現するので、直感的に分かりやすいですよね。
手話については、分かりやすい書籍もたくさん出ているので、参考にしてみてください。
子どものジェスチャーにことばを添えよう
子どもが使用したジェスチャーに大人がことばを添えるように関わってあげることは、子どもが音声で表現する力を発達させるのに役立ちます。
たとえば、子どもが「飲むジェスチャー」で飲みものを要求したときに、「あっ!飲みたいんだね」などというように大人がことばを添えてから要求をかなえてあげるような感じで関わってみましょう。



でも、ジェスチャーばかりやらせていたら、ことばで話さなくなりませんか?
実際のことばの指導の中でも、保護者の方からこのような質問をいただくことは多いです。
この質問への回答は、Zampini et al.が検証してくれています。この研究の対象はダウン症をもつお子さんで、ことばの発達が全体的にゆっくりな子たちです。
この子らの「ジェスチャーの種類と総数」、「表出語彙の種類と総数」を評価したところ、表出語彙が増える前はジェスチャーが優位なものの、表出語彙が増えてくるとジェスチャーの使用は減少していました。
この研究結果から、ジェスチャーは成長にともなって言葉に置き換わっていくことが分かります。
これはおそらく、意思伝達の手段として、ジェスチャーよりもことばの方が子どもたちにとって便利だからだと思います。
ジェスチャーは遠くの人に届けにくいですし、手がふさがっていると伝えられないことも多い。その一方で、ことばは少し遠いところでも届けることができ、両手におもちゃを持っていても伝えられます。
子どもたちは、ジェスチャーよりも効率的に意思伝達できる方法(音声)へと伝達方法をシフトしていくと考えられます。
よって、ジェスチャーをたくさん使うことは、むしろ言語獲得には有利であり、ジェスチャーが増えてきたら「そろそろ語彙が広がるかな?」と期待しても良いことが多いのかもしれません。
擬音語や擬態語をたくさん使いながら遊ぼう
簡単に言うと、子どもたちにとって「わんわん」「ぴょんぴょん」などの繰り返しのある擬音語は覚えやすいことばです。また、「びゅーん」「しゅっ」などの擬態語も、ことばから意味が想像しやすいものとなります。
生活の中で、このような擬音語や擬態語をたくさん使って関わってあげながら、まずは理解できることばを増やすことを目標としましょう。
お子さんがみているもの、やっている動作に対して、その場その場で実況中継するように声かけしてあげると子どもたちはことばを覚えやすくなります。
以下は「擬音語・擬態語」がたくさん描かれた教材・おもちゃです。楽しみながら取り組めるのでオススメですよ。
ちなみに、ことばを育てるオノマトペカード『あいうえお編』は、Kindle Unlimitedの読み放題対象になっています。Kindle Unlimitedは初月無料で利用できるので、気軽にお試しできますね。
ことばを話せるようになる前に、子どもたちはことばを理解できるようになります。
そして、ことばはいきなり大人が使う言葉を理解できるようになるのではなく、擬態語や擬音語の理解から始まる場合が多いです。
興味深いことに、私たち大人は小さいお子さんと関わる時に、自然と少し声が高くなり、おおげさなイントネーションで、擬音語・擬態語を多く用います。
これは、Infant-directed speech (IDS)やマザリーズなどと呼ばれており、日本語に限らずほとんどの言語でみられる子どもに対する大人の関わり方です。
このIDSやマザリーズは、子どもの注意を大人にひきよせるのに役立っており、ことばを覚えることにもプラスの影響を与えることが分かっています(例えば、Englund et al., 2020)
まとめ:ジェスチャー・擬音語・擬態語は言葉の発達に大切なこと
この記事では、ジェスチャーや擬音語・擬態語がことばの発達に大切であることを解説しました。
毎日の関わりの中で意識したい3つのポイントは以下です。
- 大人が身振り・ジェスチャーをたくさん使って関わる
- 子どものジェスチャーにことばを添える
- 擬音語や擬態語をたくさん使いながら遊ぶ
これらは、ことばが出る前の子どもたちには、特に大切にしていただきたい関わりのポイントです。
子どもの発達の状態に合わせた必要な関わりを、楽しみつつ、焦らず・コツコツと続けていきましょう。
当サイトでは【言葉の発達【完全ガイド】発達の順序に沿って解説!】の記事に、ことばの発達に関する記事をまとめて紹介しています。
ことばの発達の順番に記事を並べていますので、お子さんの発達の状態に合わせてお読みいただけます。
\クリックして記事へ移動!/