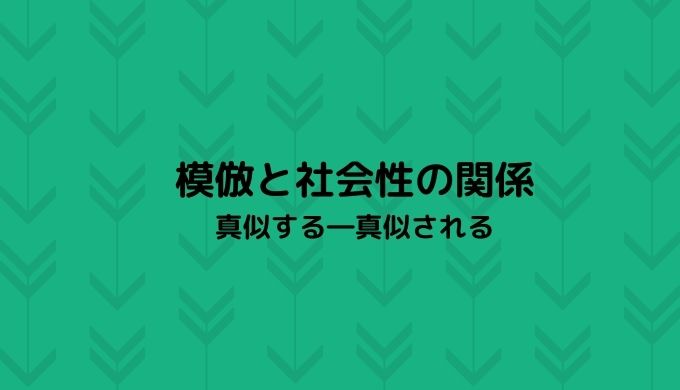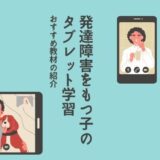模倣すること、模倣されることは社会性を育てるきっかけになります。小さい頃に子どもたちは相手の真似をすること、相手から真似されることを好み繰り返します。
これに関して、先日、このようなツイートをしました。
【逆模倣】
— ゆう@ことばと摂食の発達・療育・リハビリ (@hagukumichild) July 26, 2021
お子さんがやっている動作を大人が真似しながら関わってみましょう。自分の行動を真似されることで、自分の行動が相手に変化を与えることができることを学べます。これがコミュニケーションの意欲となり、ことばの基礎につながっていきます。
本記事では、相手の行動を真似すること(模倣)、大人が子どもの模倣を真似すること(逆模倣)について、もう少し深めてみたいと思います。

私は発達がゆっくりなお子さんや発達障害をもつお子さんたちに、ことば・コミュニケーションの支援を言語聴覚士(ST)として行っています。その経験や知識から、今回は「模倣」をテーマに深めてみたいと思います。
それでは、さっそくお読みください。
目次
模倣と相手の意図理解
あかちゃんは生後9ヶ月ごろから相手の行動を真似することが増えます。
大人が日ごろおこなっている歯磨きなどの行為を、じっと観察して、真似しようとします。
大人の真似をするのは、子どもが周囲の人に興味をもっている証拠です。
その後のことばの発達や、生活習慣・身辺自立の成長のために大切な能力につながっていきます。
模倣に関するおもしろい研究をひとつ紹介します。
毛布をかぶっていて両手を使うことのできない状態の大人が頭でライトのスイッチを押す姿をみせる場合と、手が使える状態の大人が頭でスイッチを押す姿を見せる場合で、子どもがどのような方法でスイッチをつけるのかを調査した研究があります(Gergely et al., 2002)。
要するに、手が使えないから頭でスイッチをつけたということを認識できるかどうかが子どもには問われています。
結果、生後14カ月児のほとんどで、手が使える状況なのにわざわざ頭でスイッチを押す姿をみた場合に、子どもも同じように頭でスイッチを押しました。
逆に、手が使えないからしょうがなく頭でスイッチを押す姿を見た場合には、頭ではなく手でスイッチを押しました。
この結果から、生後14カ月ですでに、相手の行為の意図を理解したうえで模倣することができる可能性を示しています。
すなわち、1歳過ぎころから相手の行動をただ単純に真似するだけではなく、相手が何をしようとしているのかを理解したうえで模倣ができるようになってくるといえます。
模倣と共感
相手のしぐさや癖、振る舞いを無意識的に模倣し模倣されることで、互いの信頼や好感が高まります。
これを「カメレオン効果」といいます(Chartrand et al., 1999)。
たとえば、相手がふいに頭をかくと自分も頭を触ってしまうようなことがありませんか?
このような自分の行動をさりげなく真似する相手には好感をおぼえやすく、また好感をおぼえている相手の行動は無意識に模倣してしまいやすいようです。
では、「模倣する―模倣される」経験が共感や信頼性を高めるのはいつごろから始まるのでしょうか?
あかちゃんは、生後6か月を過ぎてから相手の行動を模倣しはじめます。
そして、「模倣されている」ことに気づくのは生後9~14カ月頃だといわれています。乳児は自分を模倣する相手に注意をより長く向けるだけでなく、笑顔を増やします(Agnetta et al., 2004)。
おもしろいことに、自分の行為を模倣した人に対して、援助や協力をより多く求めようとするなど社会的な行動をより多くとろうとします(Carpenter et al., 2013)。
ようするに、生後1年未満のあかちゃんでさえ、自分の行動を真似してくれるような相手には好意を示しやすく、その好意を原動力に社会性を育むきっかになるといえるのではないでしょうか。
また、「模倣する―模倣される」経験は、脳の活動も変化させることが分かってきています。
「模倣する―される」と脳の情動や報酬に関する部位が賦活します。
このような研究結果から、相手の行動を模倣したり、模倣されたりといった経験は、共感も育てる可能性があるのではないかといわれています。
まとめ:模倣は社会性の基礎となる
模倣には相手の意図理解や共感を育てる可能性があることを解説しました。
お子さんの社会性を育てていくために、「模倣する―模倣される」経験を大切にしてあげてほしいと思います。
お子さんが大人の真似をしてくれたら、それを喜んで褒めてあげる。
大人もお子さんの行動を真似しながら関わってあげる。
この繰り返しが社会性を育むきっかけとなります。