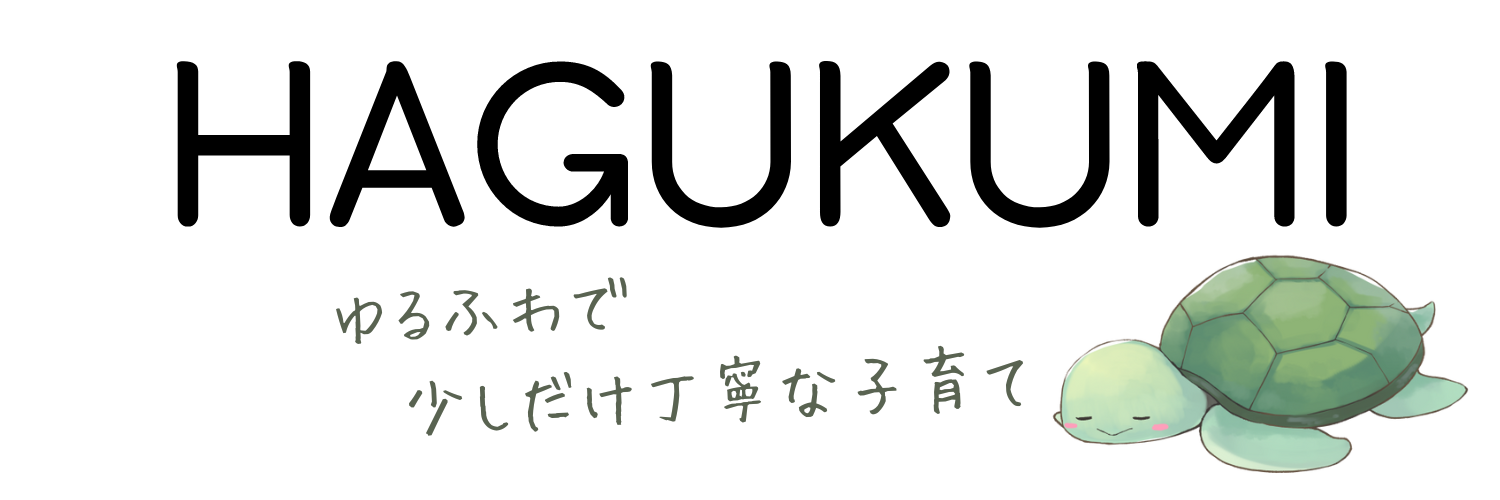日々、保護者の方々から「どうやったら、子どものことばが増えますか?」「読み書きにつながる遊びはありますか?」というご相談をいただきます。
ドリルや「お勉強」は、親子ともに疲れてしまいますよね。
そこで今回は、遊びながら「ことばの力」を伸ばすカードゲームをご紹介します。
それが、「もじぴったん」。 僕も実際の言語指導でよく使用しています。
「ああ、知ってる!言葉を作るゲームでしょ?」と思った方もいるのでは? このゲームには子どもたちの将来の「読み書き能力」に直結する、本当に大切な要素が詰まっているんです。
なぜ、私たち言語聴覚士がこのゲームをおすすめするのか。 その「秘密」を、専門的な視点からお伝えしていきますね。
目次
秘密①:ことばの「音」を意識する力(音韻意識)が育つ
いきなり専門用語が出てきましたが、これが一番大切なポイントです。
「音韻意識(おんいんいしき)」とは、簡単に言えば「ことばを“音”のまとまりとして認識し、遊ぶ力」のこと。
例えば、「りんご」という言葉を、「り」「ん」「ご」という3つの音に分解したり、「『り』んご」の最初の音は「り」だな、などと気づく力のことです。
この「音韻意識」は、ひらがなの読み書きを習得するための“土台”となります。 この土台がしっかりしていないと、文字を読めるようになる段階でつまずきやすくなります。
「もじぴったん」が、どう効くの?
「もじぴったん」は、まさにこの「音韻意識」のトレーニングに最適です。
- 「ことば」が「音」のカードになる 「いぬ」という言葉を作るとき、子どもは「い」のカードと「ぬ」のカードを物理的にくっつけます。 1音が1枚ずつのカードになっているので、単語がいくつの音で出来ているのかを把握しやすくなっています。
- 音の「入れ替え遊び」が自然に発生する 「『ね』『こ』」のカードの隣に、「『い』『ぬ』」のカードを置いたとします。 「あ、『ねこ』の『ね』を『い』に変えたら…『いこ』?そんな言葉ないね」 「じゃあ、『いぬ』の『ぬ』を『こ』に変えたら…『いこ』?こんな風に、音(カード)を入れ替えたり、足したり、引いたりする「音の操作」が、ゲームの中で自然に発生します。これは、ドリルなどでは学びにくい、生きたトレーニングです。
秘密②:「知っている言葉」を引き出す力が鍛えられる
「もじぴったん」は、語彙力(ボキャブラリー)を増やすだけでなく、「すでに知っている言葉を、必要な時に引き出す力(=語彙検索)」を強力に鍛えます。
発達に特性のあるお子さんの中には、言葉をたくさん知っていても、会話の中でパッと「それ」を思い出すのが苦手な子がいます。
「もじぴったん」が、どう効くの?
このゲームは、「『あ』から始まる言葉、なーんだ?」というクイズとは違います。 場にある「か」のカードと、自分の手持ちの「さ」のカードを見て、「あ、『か』と『さ』で…『かさ』(傘)だ!」とひらめく必要があります。
- 制限(カード)があるからこそ、脳がフル回転する 「『か』と『さ』を使って作れる言葉」という制限の中で、自分の“ことばの引き出し”を必死に探します。「かさ」「さか」「かさぶた…『ぶ』と『た』がないな…」 この「探す→見つける→当てはめる」というプロセスこそが、コミュニケーションで言葉を思い出す力と全く同じなのです。
- 親子の「言葉シャワー」が生まれる 子どもが「き」のカードしか出せなくても、すかさずお父さん・お母さんが「『りん』を足して…『きりん』だ!」「『の』を足して『きの』…『きのこ』!『こ』も探そう!」とサポートできます。 子どもは、自分の1枚のカードから、知らなかった言葉(きりん、きのこ)が生まれる成功体験を積むことができます。
秘密③:「見える」から、やる気が続く
発達支援の現場で私たちが大切にしているのが、**「視覚的なサポート」**です。 耳から聞くだけの情報よりも、目で見てわかる情報の方が、子どもたちは理解しやすく、安心できます。
「もじぴったん」が、どう効くの?
- 「ことば」が「モノ」になる 「ことば」という目に見えないものが、「もじカード」という具体的なモノになります。これは、視覚的に物事を捉えるのが得意なお子さんにとって、非常に理解しやすい形です。
- 「できた!」が目に見える 自分が作った言葉が、盤面(テーブルの上)に広がっていきます。自分がどれだけ言葉を作ったか、どれだけ「陣地」を広げたかが一目瞭然です。 この「達成感の見える化」が、「もっとやりたい!」という意欲を引き出します。
+αのアドバイス
このゲームを、お子さんの発達に合わせて楽しく学ぶためのヒントをいくつかご紹介します。
- ルールは「ゆるく」でOK 最初は点数計算など、難しいルールは無視しましょう。「知ってる言葉を1個作れたら、拍手!」で十分です。まずは「言葉を作るって楽しい!」と感じてもらうことが最優先です。
- 「2文字・3文字」から始めよう 「いぬ」「ねこ」「くるま」「りんご」など、身近な2〜3文字の言葉を作ることからスタートします。使うカードの枚数も、最初は「あいうえお」と「かきくけこ」だけ…のように絞ると、探しやすくなります。
- 「テーマ」を決めてみよう 「今日は“食べ物”の言葉だけ作ってみよう!」「“動物”はどこにいるかな?」とテーマを決めると、お子さんの“ことばの引き出し”が開きやすくなります。
- 「辞書」や「図鑑」を相棒に 「『きりん』って作れたけど、どんな動物だっけ?」 「『すいか』ってどんな味だっけ?」 そうしたら、すぐに図鑑や辞書(絵辞書でもOK)で一緒に調べてみましょう。言葉と「実物・イメージ」が結びつき、語彙が定着します。
まとめ
「もじぴったん」というカードゲーム1つで、いろいろなことが学べます。
ことばを「音」として捉える力(音韻意識)を育て、 自分の知っている言葉を引き出す力(語彙検索)を鍛え、 それを「楽しい!」と思わせてくれる。
これらすべてが、お子さんの「ことばの土台」を強くしなやかに育ててくれます。
親子で楽しい時間を過ごしながら、ことばを育んでいきましょう!