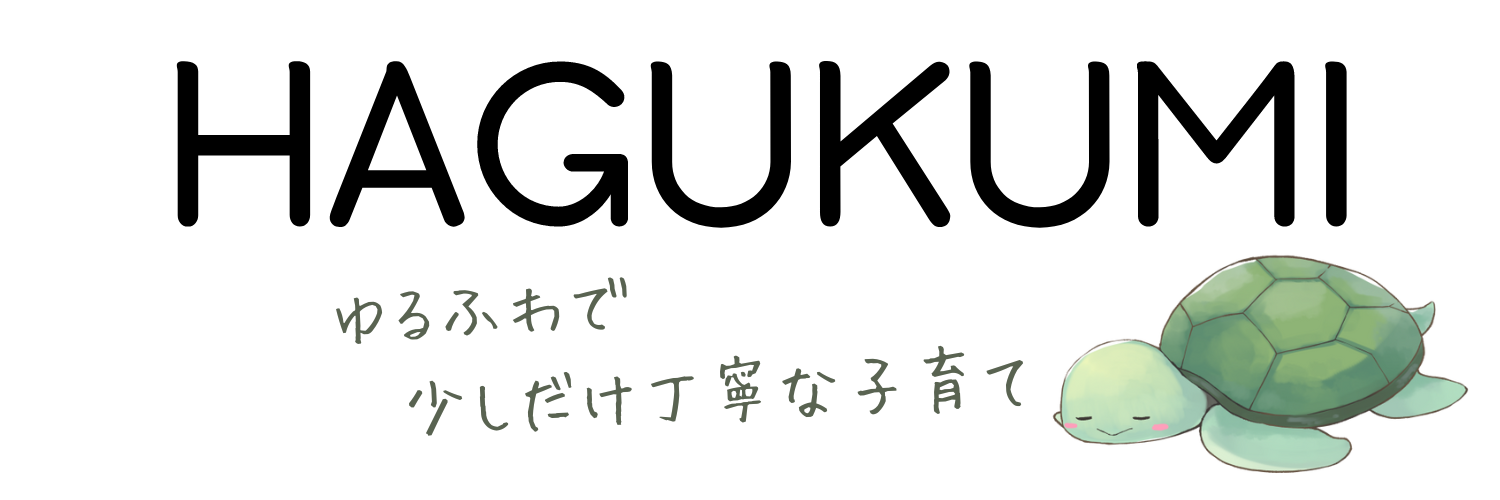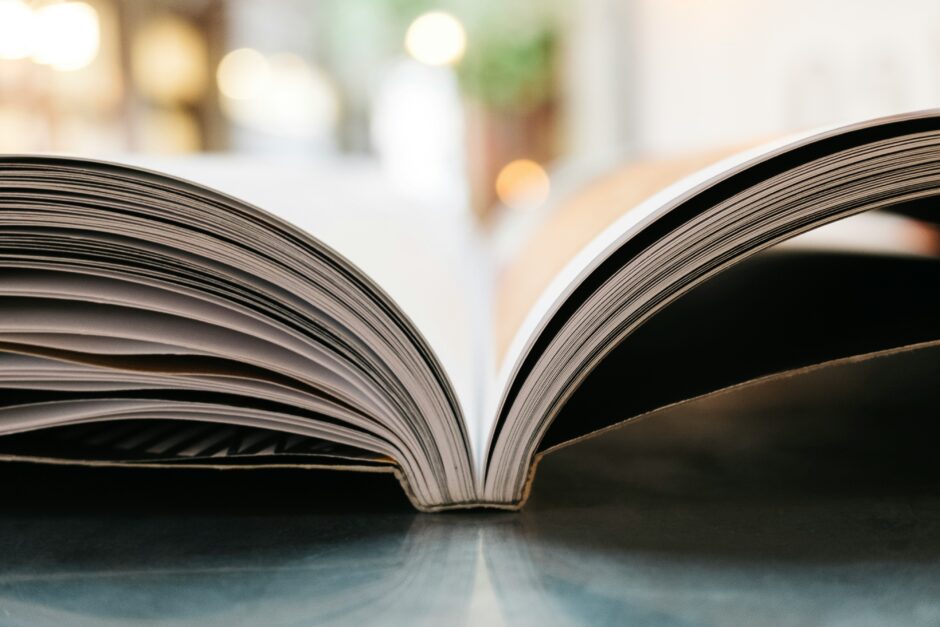日々、自閉スペクトラム症(ASD)のお子さんたちと向き合う中で、こんな悩みを抱えていませんか?
- 「なかなか目が合わない、他者への関心が育ちにくい…」
- 「言葉は出てきたけれど、一方的で『やりとり』にならない…」
- 「スキルは教えても、実生活や遊びの場面で『自発的に』使ってくれない…」
こうした課題の「根っこ」にある社会的コミュニケーションの土台に、真正面からアプローチする画期的なモデルが「JASPER(ジャスパー)」です。
そしてこの度、その具体的な実践方法を日本語で詳細に解説した『JASPER実践マニュアル: 自閉スペクトラム症児のための早期支援モデル』が刊行されました。
今日は、なぜこの本が私たちの臨床を「変える」ほどのインパクトを持つのか、その魅力を徹底的にご紹介します。
目次
そもそもJASPERとは?
JASPERは、UCLAのキャシー・カスラーリ博士らによって開発された、エビデンスに基づく早期支援モデルです。以下の4つの重要な領域の頭文字をとっています。
- Joint Attention (共同注意)
- Symbolic Play (象徴あそび)
- Engagement (参加・関与)
- Regulation (調整)
JASPERが画期的なのは、単に「言葉を教える」「問題行動を減らす」といった表面的なスキル訓練に留まらない点です。
ASDのお子さんが「他者と関わることの楽しさ」に気づき、「自ら学び、発達していく力」そのものを引き出すことに焦点を当てています。これは、私たちが目指す「般化(はんか)」や「自発性」に直結するアプローチです。
なぜ「マニュアル」が今、必要なのか?
「JASPERの理論は素晴らしい。でも、どうやって自分の臨床に落とし込めば…?」
そう思っていた専門家は僕だけではないはずです。本書は、まさにその「理論と実践のギャップ」を埋めてくれます。
このマニュアルが「必携」である理由は、次の3点。
1. 「知っている」から「できる」へ導く具体性
本書は、JASPERを実践するための具体的なステップが、驚くほど詳細に記述されています。
- 評価: お子さんの発達レベル(共同注意や遊びの段階)をどう見立てるか。
- 目標設定: その子に今必要な「次のステップ」は何か。
- 介入戦略: レベルに合わせた「6つの戦略」(環境設定、模倣、プロンプト等)を、どのタイミングで、どのように使うか。
セッションの構成、おもちゃの選び方、親への指導方法まで、明日からすぐに試せる「臨床の武器」が詰まっています。
2. 「自然なやりとり」を意図的に生み出す技術
JASPERは、子ども主導の「遊び」の中で展開されます。しかし、それは「ただ遊んでいる」のではありません。
本書を読めば、一見自然に見えるやりとりの中で、療育者がいかに「意図的に」共同注意や象徴あそびの機会を仕掛け、子どもの自発性を引き出しているか、その高度な技術が分かります。
「子どもが楽しそうにしているけれど、これで本当に発達が促せているか不安…」という悩みを抱えるセラピストにとって、自分の実践に「確かな軸」を与えてくれる一冊です。
3. 豊富な事例とトラブルシューティング
マニュアルにありがちな「理想論」だけでは終わりません。
- 「全くおもちゃに興味を示さない子」
- 「すぐに癇癪(かんしゃく)を起こしてしまう子」
- 「こだわりが強く、遊びが広がらない子」
こうした臨床で直面する「あるある」な困難に対し、JASPERの枠組みでどう対応すべきか、具体的な事例と共に解説されています。
この本が、あなたの臨床をどう変えるか
このマニュアルを読み終え、実践に移そうとするとき、あなたのお子さんを見る「視点」が変わっているはずです。
- 「言葉が出ない」→「まずは、視線を共有する楽しさを伝えよう」
- 「遊びが続かない」→「この子の興味を引く『仕掛け』を作ってみよう」
お子さんの小さな「できた!」を見逃さず、それを確実な発達のステップへとつなげていく。そんな「手応えのある臨床」を可能にしてくれます。
まとめ:今、この本を手にするべき人
- 言語聴覚士(ST)、作業療法士(OT)、臨床心理士/公認心理師
- 児童発達支援や放課後等デイサービスに携わる方
- 保育士、幼稚園教諭、特別支援教育の先生
- 小児科医、児童精神科医
JASPERは、単なる一つの技法ではありません。子どもたちの発達の「土台」を育むという、私たちが最も大切にすべき臨床哲学そのものです。
「目の前のお子さんの『未来』を、もっと豊かにしたい」
そう願う全ての専門家に、本書を心からお勧めします。 ぜひ、この「JASPER実践マニュアル」を手に取り、臨床をアップデートしましょう。