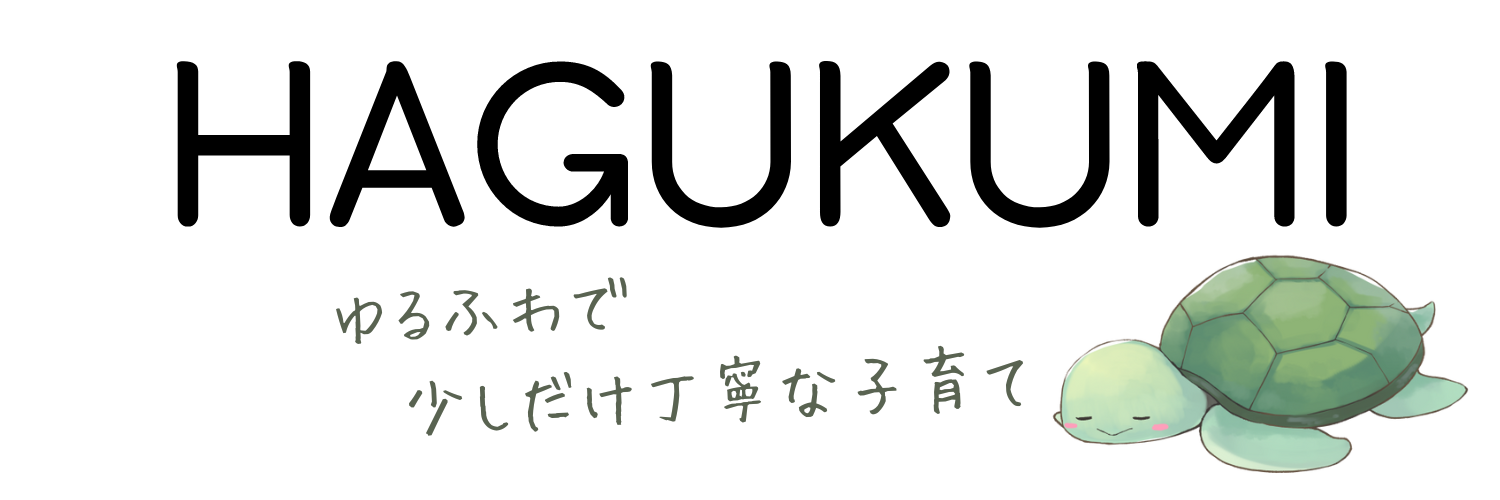インフルエンザもよくなり、だいぶ動けるようになってきました。 とはいえ、まだ療養期間で出勤ができないため、家で論文をじっくりと読んでみました。
Hustad先生らによる、子どもの「発話明瞭度(Intelligibility)」が、どれくらいの年齢でどの程度発達するのかを調べた研究論文です(JSLHR, 2021) 。
Hustad, K. C., Mahr, T. J., Natzke, P., & Rathouz, P. J. (2021). Speech Development Between 30 and 119 Months in Typical Children I: Intelligibility Growth Curves for Single-Word and Multiword Productions. Journal of speech, language, and hearing research : JSLHR, 64(10), 3707–3719. https://doi.org/10.1044/2021_JSLHR-21-00142
これが、非常に興味深かったです。
これまで、「子どもの言葉はどれくらい周りに通じるか」という基準は、結構「親の主観」に頼ったものが多かったんです 。一般的には、「4歳(47ヶ月)になる頃には、ほぼ100%通じる」といわれることもありますよね。
でも、この研究で「知らない大人」が客観的に聞いた場合、結果はかなり違いました。
この研究では、平均的な(50パーセンタイルの)子どもが90%の明瞭度に達するのは、だいたい5歳(62ヶ月)を過ぎてから、という結果でした 。
親が思う「100%通じる」と、客観的な「90%」の間には、1年以上の大きなギャップがあるわけです 。 これはやっぱり、親は普段から子どもの発音のクセや言い間違いを(無意識に)補正して聞いているからなんだろうな、と 。
もう一つ面白かったのは、「単語」で話すより「文」で話した方が、明瞭度が高かった(聞き取りやすかった)ことです。
4歳(48ヶ月)以降は、一貫して「文(多語文)」の方が「単語(単語)」よりも聞き取りやすい、という結果が出ていました 。
普通に考えると、単語の方がハッキリ発音できて、文になると曖昧になりそうですよね。 でも、聞き手にとっては、文脈(コンテキスト)がある方が、多少不明瞭な部分があっても「こういうことを言いたいのかな?」と推測が働く。だから結果的に「通じやすく」なる 。 コミュニケーションって、音の正確さだけで成り立ってるわけじゃないんだな、と改めて感じさせられました。
とはいえ、臨床的に「支援が必要かどうか」を判断する基準も必要です。 この研究では、発達にばらつきがあることを認めた上で、「4歳(48ヶ月)の時点で、少なくとも50%は(知らない人にも)通じるべき」という一つの目安を示してくれています 。
AIが色々なことを教えてくれる時代になりましたが、こういう地道なデータを取って客観的な基準を示してくれる研究は、本当に価値があるなと(当たり前のことですが)再認識しました。
とても勉強になる論文でした。